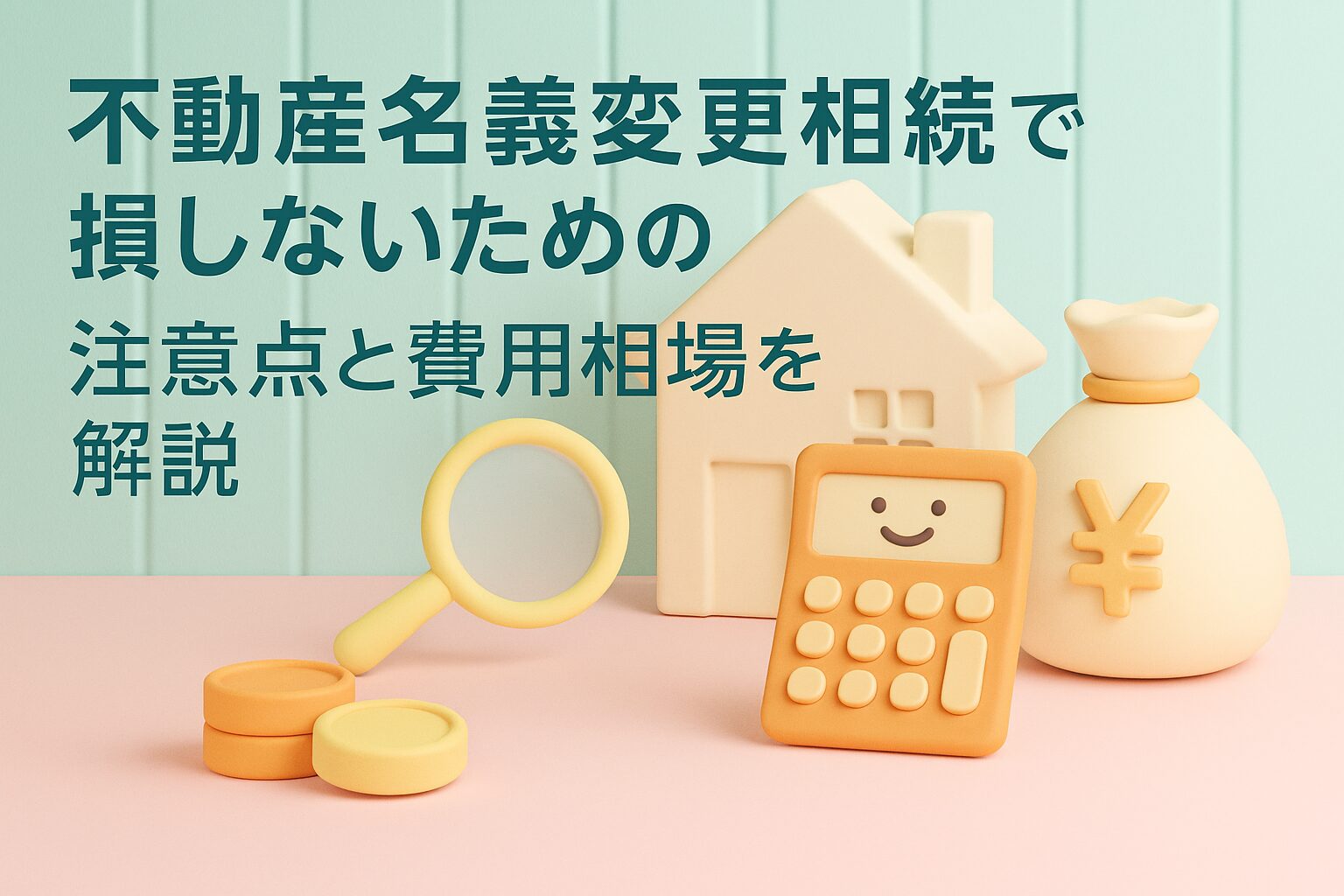
ご家族が亡くなられ、心落ち着かない日々をお過ごしのことと存じます。そんな中、ふと頭をよぎるのが「不動産の名義変更、相続の件、一体どうすれば…?」という悩みですよね。僕、終活・相続の専門家カズも、そんな不安な声に15年以上寄り添ってきました。
正直なところ、亡くなった親の土地名義変更をしないとどうなるか、そのリスクは意外と大きいんです。家の名義変更を死亡後いつまでに手続きすべきか、相続と名義変更の違いと判断基準は何か、そもそも不動産の相続名義変更を自分で行う流れと注意点って…?と、疑問が尽きないと思います。
この記事では、不動産の相続名義変更に必要な書類とその取得方法、法務局への提出手順、さらには気になる費用の内訳と節約方法まで、まるっと解説します。
例えば3000万の不動産を相続した場合の相続税の目安や、家の名義が親のままの場合の相続税の影響といった、お金の話も具体的にしていきますので、ぜひ最後までついてきてくださいね!
- 相続登記の基本と2024年からの義務化のポイント
- 自分で不動産の名義変更手続きを進める具体的な流れ
- ケース別の必要書類一覧と費用の全体像
- 相続登記を放置した場合の具体的なリスクと対策
 コンサルタント @KAZU
コンサルタント @KAZU相続が起きた後、不動産の名義変更は多くの方が初めて経験する手続きです。専門用語も多く、何から手をつけていいか分からなくなるお気持ち、本当によく分かります。この記事では、僕カズが皆さんの隣を一緒に歩くような気持ちで、専門的な内容を一つひとつ丁寧に解説していきます。まずは全体像を掴むことから始めましょう!
不動産名義変更相続の基本と放置するリスク


相続と名義変更の違いと判断基準とは
こんにちは!終活・相続の専門家カズです。さて、相続が始まると「相続」と「名義変更」という言葉が飛び交いますが、この二つの違い、意外と混乱しませんか?ここでしっかり整理しておきましょう。
まず結論から言うと、「相続」は亡くなった方の財産(不動産や預貯金など)を受け継ぐ権利そのものを指します。これは法律に基づいて自動的に発生するものです。一方、「名義変更(相続登記)」は、その受け継いだ不動産が「誰のものになったのか」を公的に登録し、第三者に主張できるようにする手続きのことです。
例えるなら、「相続」が新しいゲームソフトを手に入れる権利を得た状態だとすれば、「名義変更(相続登記)」はそのゲームソフトに自分の名前を書いて、「これは僕のだぞ!」とみんなに知らせる行為みたいなものですね。名前を書いておかないと、後から「それ、本当に君の?」と言われたときに証明するのが大変になります。
では、判断基準は何かというと、これは非常にシンプルです。不動産を相続した場合は、必ず名義変更(相続登記)が必要、と覚えておきましょう。2024年4月1日から法律が変わり、この手続きが義務になったため、「やる・やらない」の選択肢は基本的になくなった、と考えてください。
注意点:相続放棄との違い
もし財産よりも借金が多い場合など、相続そのものをしたくない場合は「相続放棄」という手続きを家庭裁判所で行う必要があります。これは名義変更とは全く別の手続きで、相続開始を知った時から3ヶ月以内という期限があるので注意が必要です。
▼相続放棄について詳しく知りたい方はこちら
相続放棄の手続きと注意点を徹底解説!後悔しない進め方とは
不動産名義変更相続はいつまでに手続きすべきか


「手続きが義務になったのは分かったけど、じゃあ一体いつまでにやればいいの?」というご質問、本当によくいただきます。これも結論からお伝えしますね。
相続登記の義務化により、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」に登記申請をしなければならない、と定められました。
…ちょっと法律の言葉は難しいですよね(笑)。もっと分かりやすく言うと、「自分が不動産を相続したと知った日から3年以内」に手続きをしてください、ということです。多くの場合、「ご家族が亡くなった日」や、遺言書がなく遺産分割の話し合い(協議)がまとまった日が基準になります。
相続登記の義務化は法律で定められています
これまで任意だった不動産の相続登記は、所有者不明の土地問題を解決するため、2024年4月1日から義務化されました。
この法改正は、不動産登記法の改正によるもので、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」の登記申請が義務付けられています。正当な理由なく怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
僕が担当したお客様で、10年前に亡くなったお父様名義の不動産をずっと放置していた方がいらっしゃいました。その方は義務化のニュースを見て慌ててご相談に来られましたが、幸いにも過料(罰金)が科される前に対処できました。
この法律は過去の相続にも適用されるので、「うちは昔の話だから大丈夫」とは思わずに、一度確認してみることを強くお勧めします。
3年の起算点が変わるケース
例えば、遺言書で不動産を相続した場合は「ご家族が亡くなったこと」と「遺言書の内容」を知った日がスタート地点です。遺産分割協議で取得者が決まった場合は「協議がまとまった日」がスタートになります。ケースによって起算点が変わるのが少しややこしいポイントですね。
▼遺言書の準備や書き方が気になる方はこちら
初心者でも安心!遺言書書き方の完全手順
家の名義変更は死亡後いつまでに済ませるべきか
前述の通り、法律上の期限は「相続を知ってから3年以内」です。ただ、僕たち専門家の視点から言わせていただくと、「できるだけ早く、理想は1年以内」に済ませておくことをお勧めします。
なぜなら、時間が経てば経つほど、手続きがどんどん複雑化するリスクがあるからです。僕が経験した典型的な失敗談を一つお話ししますね。
あるご家庭で、お父様が亡くなった後、ご兄弟の仲が良かったため「まあ、実家は長男が継ぐだろうし、急がなくてもいいね」と名義変更を後回しにしていました。しかし、5年後にその長男さんが突然亡くなってしまったのです。
すると、相続権は長男さんの奥さんと子供たち、そして元の相続人である他のご兄弟にも広がり(数次相続と言います)、関係者が一気に増えてしまいました。話し合いは難航し、書類のやり取りだけでも大変な時間と労力がかかってしまったのです。
このように、時間が経つと相続人が増えたり、認知症などで判断能力が低下する方が出たりと、予期せぬトラブルが発生しがちです。法律の期限は3年ですが、ご自身の家族を守るためにも、相続が発生したら速やかに手続きに着手するのが一番の得策と言えますね。
▼認知症による資産凍結リスクへの備えにはこちらも
家族信託の落とし穴とは?契約前に知るべき注意点15選
亡くなった親の土地名義変更しないとどうなるリスク


「3年以内にやらないと、何か罰則があるの?」という点も気になりますよね。はい、正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
しかし、リスクはそれだけではありません。むしろ、これからお話しするリスクの方が、皆さんの生活に直接的な影響を与えるかもしれません。
所有者不明土地は全国で約24%に
法務省の調査によると、不動産登記簿上で所有者の所在がすぐに確認できない土地の割合は、全体の約24%にものぼることが判明しています。特に、最後の登記から50年以上経過している土地の割合が高い傾向にあります。
相続登記が適切に行われないまま世代交代が進むことで、権利関係が複雑化し、公共事業や災害復興の妨げになるなどの社会問題につながっています。
| リスクの種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 不動産を売れない・担保にできない | 亡くなった方の名義のままでは、不動産を売却したり、ローンを組む際の担保に設定したりすることが一切できません。いざという時に不動産を活用できなくなります。 |
| 権利関係が複雑化する | 前の項目でお話しした通り、相続人が増えてしまい、遺産分割の話し合い(協議)がまとまらなくなるケースです。最悪の場合、裁判所の調停や審判が必要になることもあります。 |
| 他の相続人に持ち分を売却される | 法定相続分に従った登記がされていないと、相続人の一人が自分の持ち分だけを第三者に売却してしまう可能性があります。そうなると、全く知らない人と不動産を共有する事態になりかねません。 |
| 不動産が差し押さえられる | 相続人の誰かに借金があると、その人の法定相続分が債権者に差し押さえられてしまうリスクがあります。 |
僕のお客様で、空き家になった実家を売却して施設の入居費用に充てようと考えていた方がいました。しかし、名義変更をしていなかったため、売却活動を始めることができず、その間に他の相続人の気が変わってしまい、結局売却できなかった…という悲しいケースもありました。
このように、放置することで「いざという時の選択肢」が奪われてしまうのが、一番のデメリットかもしれません。
家の名義が親のままの場合の相続税への影響
「名義変更と相続税って関係あるの?」というのも、よくある疑問です。結論から言うと、名義変更(相続登記)をする・しないに関わらず、課税対象となる遺産があれば相続税は発生します。
つまり、「名義変更していないから、うちは相続税を払わなくていい」ということにはなりません。むしろ、名義が親のままだと、税金面で不利になる可能性があるので注意が必要です。
例えば、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった、相続税を大幅に節税できる特例があります。これらの特例を適用するには、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに遺産分割が確定し、誰がどの不動産を相続するかが決まっている必要があります。
豆知識:相続税の申告と登記は別物
相続税の申告・納税は税務署に対して行い、期限は10ヶ月以内です。一方、不動産の名義変更(相続登記)は法務局に対して行い、期限は3年以内です。管轄も期限も全く違う手続きなので、混同しないようにしましょう。
▼相続税の基本や計算方法を詳しく知りたい方はこちら
相続税計算の基本と節税のコツを図解で徹底解説
名義変更を先延ばしにして遺産分割協議がまとまらないと、これらの特例が使えず、本来払わなくてよかったはずの多額の税金を納めることになりかねません。僕の経験上、相続税の申告が必要な方は、申告準備と並行して、速やかに遺産分割の話し合いと登記申請の準備を進めるのがベストな流れです。



ここまで、相続登記の基本である「期限」と「放置リスク」について解説しました。法律上の罰則も重要ですが、それ以上に「家族関係の複雑化」や「財産の塩漬け」といったリスクの方が深刻な場合が多いです。面倒に感じる気持ちは分かりますが、未来の家族のためにも、早めの行動を心がけることが大切ですね。
不動産名義変更相続を自分で行う手順と費用


不動産相続名義変更を自分で行う流れと注意点
「よし、自分でやってみよう!」と決意した方のために、ここからは具体的な手続きの流れを僕、カズがナビゲートしますね!大まかな流れは以下のようになります。
自分でやる相続登記の7ステップ
- 対象不動産の特定と登記情報確認
- 戸籍謄本など必要書類の収集
- 相続人の確定
- 遺産分割協議書の作成(必要な場合)
- 登記申請書の作成
- 登録免許税の納付
- 法務局へ書類を提出(申請)
一つずつ見ていきましょう。まず、①で名義変更する不動産を正確に把握します。固定資産税の納税通知書などを参考に、法務局で「登記事項証明書」を取得して、現在の名義や権利関係を確認するんです。これが全てのスタートですね。
次に、②と③は並行して進めます。亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の現在の戸籍謄本などを集めて、誰が法的な相続人なのかを確定させる、非常に重要な作業です。
④は法定相続分と異なる分け方をする場合に必要です。相続人全員で話し合い、合意した内容を書面にし、全員が実印を押します。ここで揉めてしまうと、先へ進めなくなります。
⑤〜⑦が最後の仕上げです。法務局のウェブサイトにある雛形などを参考に申請書を作成し、必要な税金を納めて、全ての書類を不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。これでミッション完了です!
注意点:時間と手間がかかる覚悟を!
自分で行う最大のメリットは司法書士への報酬がかからないことですが、デメリットは相当な時間と手間がかかることです。特に戸籍の収集は、本籍地が色々変わっていると複数の役所に請求する必要があり、数ヶ月かかることもあります。
また、書類に不備があると法務局から何度も訂正を求められる「補正」の連絡が来て、心が折れそうになる方も少なくありません(笑)。
不動産相続名義変更の必要書類と取得方法


手続きの中でも、特に皆さんが「大変だ…」と感じるのが、この必要書類の収集です。ケースによって若干異なりますが、一般的な「遺産分割協議」による相続登記の必要書類を一覧にまとめてみました。
| 誰の書類? | 書類の名前 | 取得場所 |
|---|---|---|
| 亡くなった方(被相続人) | 出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 過去の本籍地があった市区町村役場 |
| 住民票の除票(または戸籍の附票) | 最後の住所地があった市区町村役場 | |
| 相続人全員 | 現在の戸籍謄本 | 現在の本籍地がある市区町村役場 |
| 遺産分割協議書 | 自分で作成(または専門家に依頼) | |
| 印鑑証明書 | 住所地の市区町村役場 | |
| 不動産を相続する方 | 住民票 | 住所地の市区町村役場 |
| その他 | 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場(東京23区は都税事務所) |
見てるだけでちょっと気が遠くなりそうですよね(笑)。特に大変なのが、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍集めです。
これは、他に隠れた相続人がいないかを証明するために絶対に必要な書類なんです。僕の経験では、ご高齢で何度も転籍されている方だと、戸籍が5〜10通以上になることもザラにあります。郵送で請求することもできますが、一つずつ過去に遡って請求していくので、非常に根気がいる作業です。
これらの書類は、ほとんどが市区町村役場で取得できます。マイナンバーカードがあればコンビニで取得できるものもありますが、改製原戸籍などは役所の窓口か郵送での請求が基本となります。
必要書類の法務局への提出手順と注意点
苦労して集めた書類と、作成した登記申請書。いよいよ法務局へ提出です!提出方法は主に3つあります。
- 窓口へ持参:不動産の所在地を管轄する法務局へ直接持って行く方法です。書類の不備をその場で指摘してもらえる可能性があり、初心者の方には一番安心かもしれません。
- 郵送:法務局へ書類一式を郵送する方法です。遠方の場合に便利ですが、書類は必ず「書留郵便」で送るようにしてください。
- オンライン申請:専用ソフトやマイナンバーカードが必要で、操作も複雑なため、一般の方が利用するにはハードルがかなり高いのが現状です。
僕が個人的にお勧めするのは、やはり①の窓口持参ですね。法務局には「登記相談」の窓口が設置されていることが多いので、提出前に一度そこで書類一式をチェックしてもらうと、ミスの可能性をぐっと減らせます。ただし、相談は予約が必要な場合が多いので、事前に管轄の法務局のウェブサイトを確認してくださいね。
参考情報サイト: 法務局「不動産登記の申請手続」
URL: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan3.html
提出時の注意点:書類の順番とホチキス
申請書を一番上にして、集めた書類を順番に重ねて提出します。このとき、申請書と収入印紙を貼る台紙、委任状などはホチキスでまとめて「合綴(がってつ)」し、ページの間に契印(けいいん)を押す必要があります。戸籍謄本などの原本還付(返却)を受けたい書類は、コピーを付けて別にまとめておきます。このあたりの作法が細かくて、初めての方には少し難しいポイントかもしれません。
不動産相続名義変更の費用の内訳と節約方法


「結局、いくらかかるの?」というお金の話、大事ですよね。相続登記にかかる費用は、大きく分けて「実費」と「専門家への報酬」の2つです。
1.実費(自分でやっても必ずかかる費用)
- 登録免許税:これが費用の大部分を占めます。不動産の固定資産評価額の0.4%が税額です。例えば、評価額が2,000万円なら、税金は8万円になります。
- 書類取得費用:戸籍謄本(1通450円)、印鑑証明書(1通300円程度)、住民票(1通300円程度)、登記事項証明書(1通600円)など、書類を集めるための手数料です。相続人の数にもよりますが、大体5,000円〜20,000円くらいになることが多いです。
- その他:郵送費や交通費などです。
2.専門家(司法書士)への報酬
司法書士に手続きを依頼した場合にかかる費用です。事務所によって料金体系は異なりますが、一般的な相続登記であれば10万円〜15万円程度が相場と言われています。
では、どうすれば費用を節約できるか?一番の節約方法は、やはり自分で手続きを行うことです。これができれば、司法書士報酬の10万円以上を浮かせることができます。
ただ、前述の通り、かなりの時間と労力がかかります。「平日は仕事で役所や法務局に行けない」「書類集めや作成に自信がない」という方は、時間と安心を買うという意味で専門家に依頼するのも一つの賢い選択です。途中で挫折して結局依頼することになると、かえって時間がかかってしまうこともありますからね。ご自身の状況に合わせて判断するのが良いでしょう。
3000万の不動産相続における相続税の目安
ここで少し、相続税の話にも触れておきましょう。「うちの実家、評価額が3000万円くらいなんだけど、相続税はかかるの?」というご相談もよく受けます。
相続税には「基礎控除」という非課税枠があります。これを超えた部分に対して、相続税が課税される仕組みです。基礎控除額の計算式はシンプルです。
相続税がかかるのは全体の約1割
国税庁の発表によると、亡くなられた方のうち、実際に相続税の課税対象となったのは全体の9.6%(令和4年分)でした。つまり、約9割の相続では相続税は発生していません。
これは、遺産総額が「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」で計算される基礎控除額を下回るためです。不動産の評価額が高くても、この基礎控除の範囲内であれば相続税の心配は不要なケースがほとんどです。
【基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)】
例えば、相続人が奥さんと子供2人(合計3人)の場合、基礎控除額は 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円 となります。このケースでは、不動産3,000万円の他に預貯金などが1,800万円以上なければ、相続税はかからない、ということになります。
つまり、不動産の評価額が3,000万円であっても、遺産総額が基礎控除の範囲内であれば相続税は0円です。日本の相続で相続税がかかるのは、全体の1割にも満たないと言われています。多くの場合、相続税の心配は不要なケースがほとんどなんです。
ただし、遺産が基礎控額を超える可能性がある場合は、必ず税理士などの専門家に相談してくださいね。相続税の計算は非常に複雑で、特例の適用など専門的な判断が必要になります。
▼ご自身のケースで相続税がかかるか、まずはこちらでチェック!
相続税計算の基本と節税のコツを図解で徹底解説
相続登記自分でやった体験談から学ぶ失敗回避のコツ


僕がこれまでに見てきた、ご自身で相続登記にチャレンジした方の「あるある失敗談」から、失敗を回避するコツを伝授します!
失敗談1:戸籍が足りなかった…
「亡くなった父の戸籍、全部集めたつもりが、法務局で『生まれる前の、おじいさんの戸籍(改製原戸籍)が足りません』と言われてしまった…」というケース。これは本当に多いです。昔の戸籍は手書きで解読が難しく、どこまで遡ればいいか分かりにくいんですよね。
【回避のコツ】
役所の窓口で戸籍を請求する際に、「相続登記で使うので、出生から死亡まで繋がるものを全てください」と明確に伝えるのがポイントです。「この一つ前の戸籍はどこの役所に請求すればいいですか?」と聞けば、教えてくれることも多いですよ。
失敗談2:書類の有効期限が切れていた…
「遺産分割協議書に添付する印鑑証明書、半年前に取っておいたものを使ったら、法務局では受け付けてもらえなかった!」というケース。相続登記自体には印鑑証明書の有効期限はありませんが、金融機関などでは「発行後3ヶ月または6ヶ月以内」と定められていることが多く、他の手続きと混同してしまう方がいます。
【回避のコツ】
遺産分割協議書への署名・押印の日が近づいてから、相続人全員でタイミングを合わせて取得するようにしましょう。
失敗談3:登録免許税の計算を間違えた…
「固定資産評価額の証明書、最新年度のものが必要とは知らず、去年のものを使って税額を計算してしまった…」というケース。登録免許税は、登記を申請する年度の評価額で計算する必要があります。
【回避のコツ】
固定資産評価証明書は、毎年4月1日に新しい年度のものに切り替わります。申請のタイミングに合わせて、必ず最新年度のものを取得してください。
これらの失敗は、誰にでも起こりうることです。一つひとつ確認しながら、焦らずに進めることが成功への一番の近道ですね。
不動産名義変更相続に関するよくある質問(FAQ)
まとめ:不動産名義変更相続は計画的に進めよう
- 不動産の名義変更(相続登記)は2024年4月から義務化された
- 手続きの期限は「相続を知った日から3年以内」
- 期限を過ぎると10万円以下の過料が科される可能性がある
- 放置すると不動産の売却や活用ができないリスクがある
- 時間が経つと相続人が増え権利関係が複雑化する
- 名義変更と相続税は別物だが関連性はある
- 遺産分割がまとまらないと相続税の特例が使えない場合がある
- 自分で手続きする最大のメリットは費用の節約
- 自分でやるには多くの時間と手間がかかるのがデメリット
- 手続きは不動産の特定、書類収集、申請書作成、提出の流れで進む
- 一番大変なのは亡くなった方の出生まで遡る戸籍集め
- 法務局への提出は窓口持参が初心者にはおすすめ
- かかる費用の大半は登録免許税(固定資産評価額の0.4%)
- 相続税は基礎控除額を超えなければかからない
- 自分でやる際は書類の不足や期限切れに注意が必要



最後までお読みいただき、ありがとうございました!不動産の相続登記は、確かに複雑で大変な手続きです。でも、一つひとつのステップを理解し、計画的に進めれば、ご自身でやり遂げることも十分に可能です。この記事が、皆さんの不安を少しでも和らげ、次の一歩を踏み出すきっかけになれば、僕カズとしてこれ以上嬉しいことはありません。
▼あわせて読みたい関連記事▼












