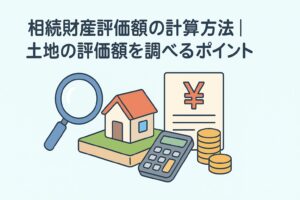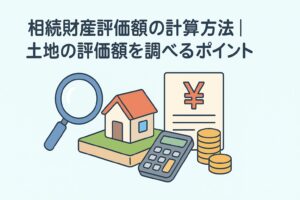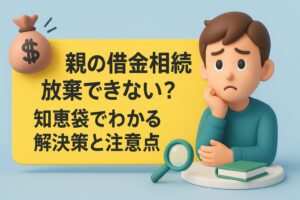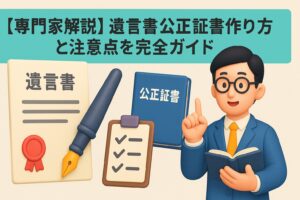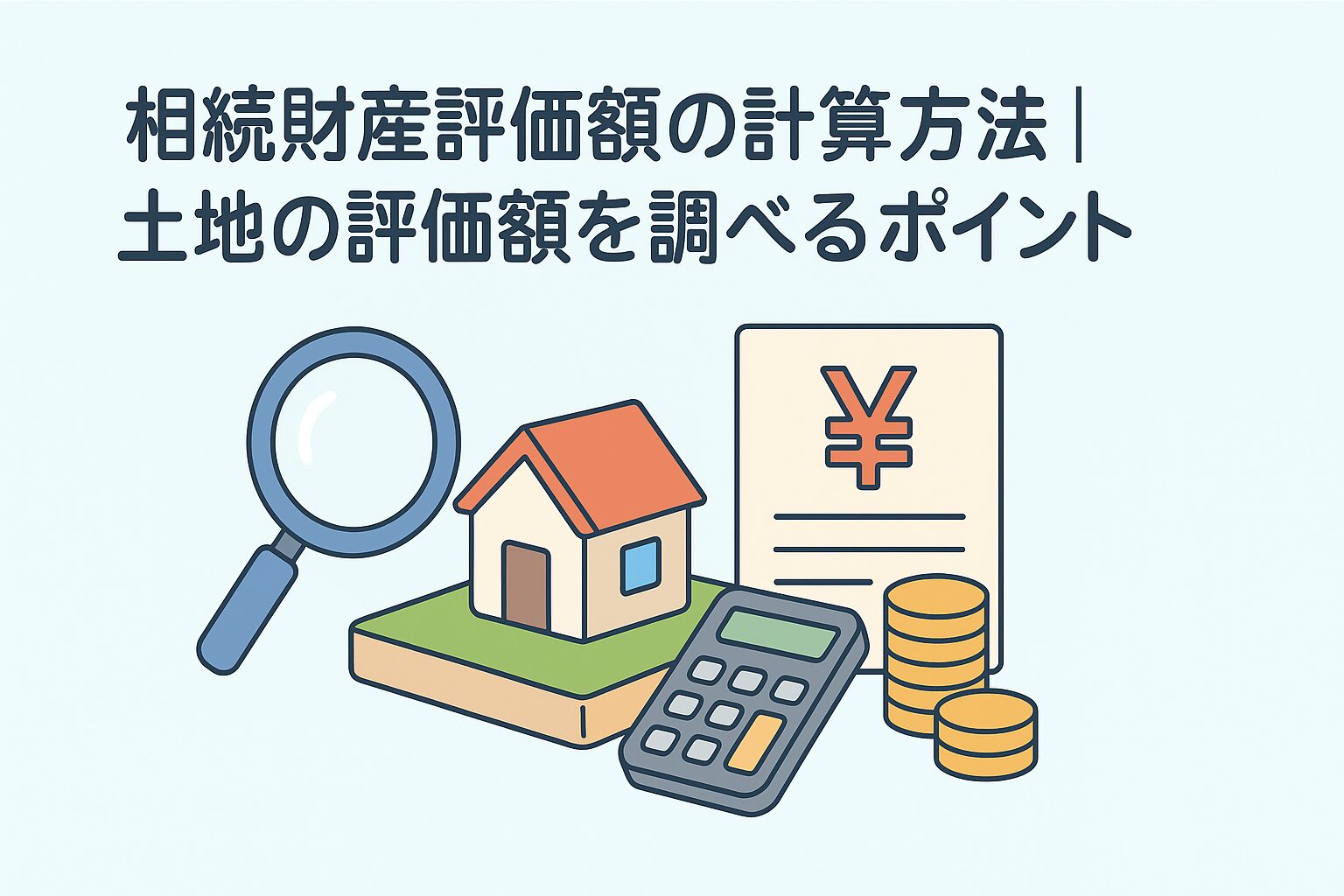
「相続評価額はどうやって計算するのですか?」とか「遺産の評価額はどうやって調べますか?」なんて、特に相続での土地の評価額の調べ方で頭を抱えていませんか?僕、専門家のカズもそういったご相談を本当によくいただきます。
結論から言うと、相続財産評価額の計算方法は、相続税評価額について国税庁が定めたルールに基づいて行います。特に土地評価額の計算は、路線価や相続税評価額と関係の深い固定資産税評価額を使って、相続税の土地評価を自分で行うことも可能なんですよ。
ただし、土地の形状が複雑だったりすると、相続税評価額の土地の計算方法がちょっとややこしくなるケースもあります。自分で評価する際には、相続税の固定資産税評価額はどこを見るか、といったポイントを押さえておくことが大切です。
この記事では、相続税評価額の調べ方の基本から、具体的な計算方法、さらには便利な相続税の土地計算シミュレーションの活用法まで、まるっと分かりやすく解説していきますね!
- 相続財産評価額の基本的な考え方がわかる
- 土地の評価額を計算する2つの方法を理解できる
- 自分で評価額を調べる具体的な手順がわかる
- 専門家に相談すべきケースを見極められる
 コンサルタント @KAZU
コンサルタント @KAZU相続って、言葉を聞くだけで「難しそう…」って思っちゃいますよね。でも大丈夫!特に評価額の計算は、一つ一つのステップを理解すれば、自分で「おおよその金額」を把握することは十分可能です。
まずはこの記事で基本のキを掴んで、漠然とした終活とは何か?という不安を解消していきましょう。
僕がしっかりナビゲートしますから、安心してくださいね!
相続財産評価額の計算方法の基礎知識


相続税評価額の調べ方の基本
こんにちは!相続専門家のカズです。さて、相続の話になると必ず出てくる「相続税評価額」という言葉。これって一体何なのでしょうか。言葉の響きからして、少し難しく感じてしまうかもしれませんね。
一言で言うと、これは「相続税を計算するために国が定めた財産の価値(評価額)」のことです。私たちが普段不動産屋さんで見る「売買価格(時価)」や、ニュースで聞く「公示価格」とは異なる、相続税専用の特別なモノサシだと考えてください。
なぜこのような特別な評価額が必要かというと、課税の公平性を保つためです。もし評価方法が人それぞれだったら、同じ価値の財産でも人によって相続税額が変わってしまい、不公平が生じますよね。それを防ぐために、国は財産の種類ごとに統一の計算ルールを設けているのです。
例えば、預貯金であれば亡くなったその日の残高が評価額となり非常にシンプルですが、不動産や株式、ゴルフ会員権などは、それぞれ個別のルールに従って評価額を算出し、最終的な相続税の計算へと進みます。
まずはこの大原則、「相続税評価額は、市場で売れる価格とは違う特別な価額なんだな」という点をしっかり押さえておきましょう。
【相続財産の約3割は「土地」】
国税庁の統計によると、相続税が課税された財産の価額構成比では「土地」が約3割を占め、現金・預貯金等に次いで2番目に大きな割合となっています。このことからも、相続税額を正確に把握するためには、土地の評価額を正しく計算することがいかに重要であるかがわかります。
(出典:【相続財産の約3割は「土地」】
国税庁の統計によると、相続税が課税された財産の価額構成比では「土地」が約3割を占め、現金・預貯金等に次いで2番目に大きな割合となっています。このことからも、相続税額を正確に把握するためには、土地の評価額を正しく計算することがいかに重要であるかがわかります。
(出典:国税庁「令和4年分 相続税の申告事績の概要」)
相続税評価額と固定資産税評価額の関係


不動産の評価額の話で、もう一つ切っても切れない関係にあるのが「固定資産税評価額」です。これは、毎年春ごろに市町村から送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されている価額で、固定資産税や都市計画税、不動産取得税などの計算の基になるものです。
この二つは目的が異なりますが、特に関係が深いのが建物の評価です。建物の相続税評価額は、驚くほどシンプルで、
建物の相続税評価額 = 固定資産税評価額 × 1.0
となり、つまり固定資産税評価額そのものが、そのまま相続税評価額として使われます。これは、評価の手間を簡略化するためでもあります。
一方で土地の場合は、後ほど詳しく解説する「倍率方式」という計算方法で、この固定資産税評価額を直接の計算基礎として使用します。このように、固定資産税評価額は、特に相続不動産の評価額を調べる上で、なくてはならない非常に重要な情報なのです。
ポイントのまとめ
- 建物の場合:固定資産税評価額が、そのまま相続税評価額になる。
- 土地の場合:「倍率方式」という評価方法で、計算の基礎として使用される。
相続税の固定資産税評価額はどこを見るか
「じゃあ、その大事な固定資産税評価額はどこに書いてあるの?」という疑問が当然湧きますよね。ご安心ください、確認方法はいくつかあり、決して難しくありません。
最も簡単なのは、毎年4月~6月頃に、その年の1月1日時点の不動産所有者宛に市町村から郵送されてくる「固定資産税・都市計画税 納税通知書」を確認する方法です。
この通知書には、「課税明細書」という書類が同封されています。ここには、所有している土地や家屋一つ一つの所在地、地番、面積、そして評価額などが詳細に記載されています。その中の「価格」または「評価額」という項目に記載されている金額、これが固定資産税評価額にあたります。
もし手元に納税通知書が見当たらない、あるいは紛失してしまった場合は、不動産が所在する市区町村の役所(東京23区の場合は都税事務所)の窓口で「固定資産評価証明書」を発行してもらうことで確認できます。
本人確認書類や手数料が必要になる場合がありますので、事前に役所のホームページなどで確認しておくとスムーズですよ。
豆知識:評価替えについて
土地や家屋の固定資産税評価額は、地価の変動などを反映させるため、原則として3年に一度、評価額を見直す「評価替え」という制度があります。相続税の計算で使うのは、亡くなった年(相続開始年)の評価額ですので、古い年度の書類と間違えないように注意が必要です。
相続税評価額は国税庁の通達が基準
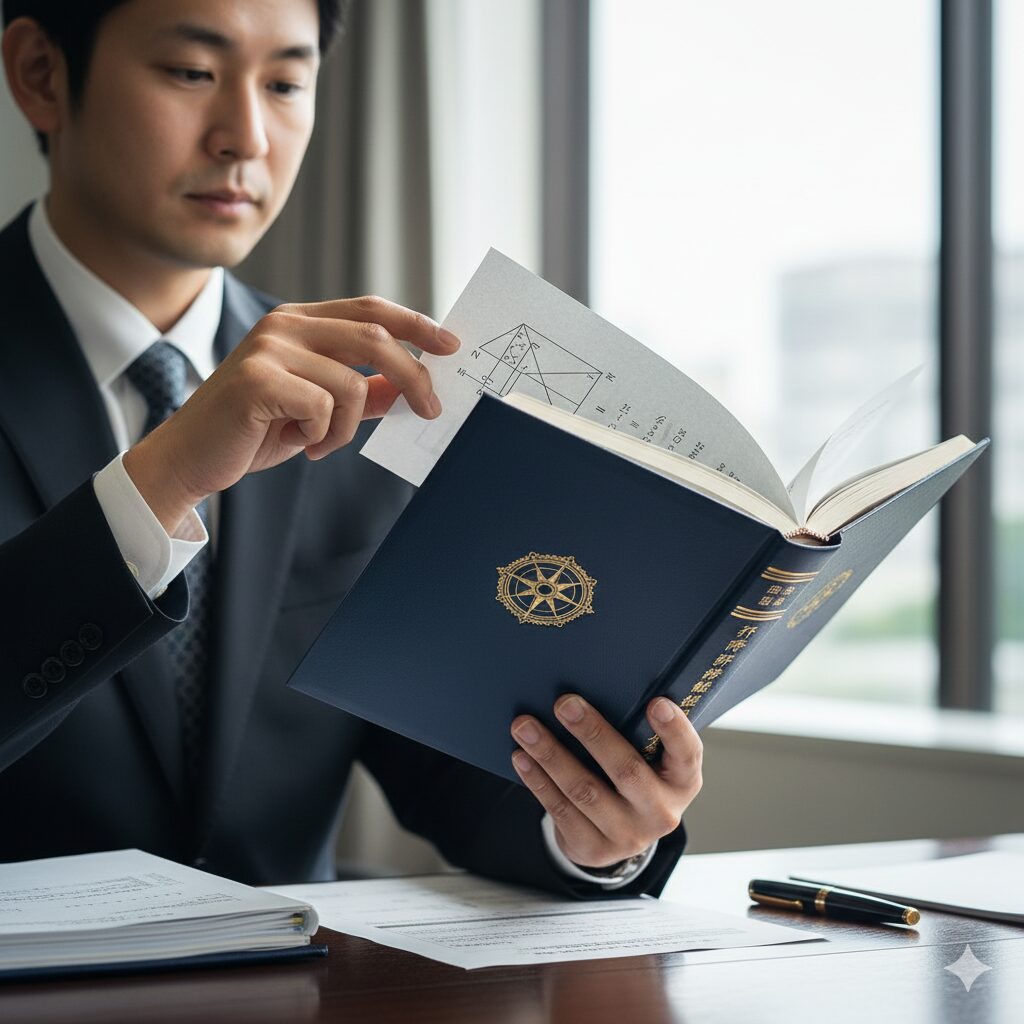
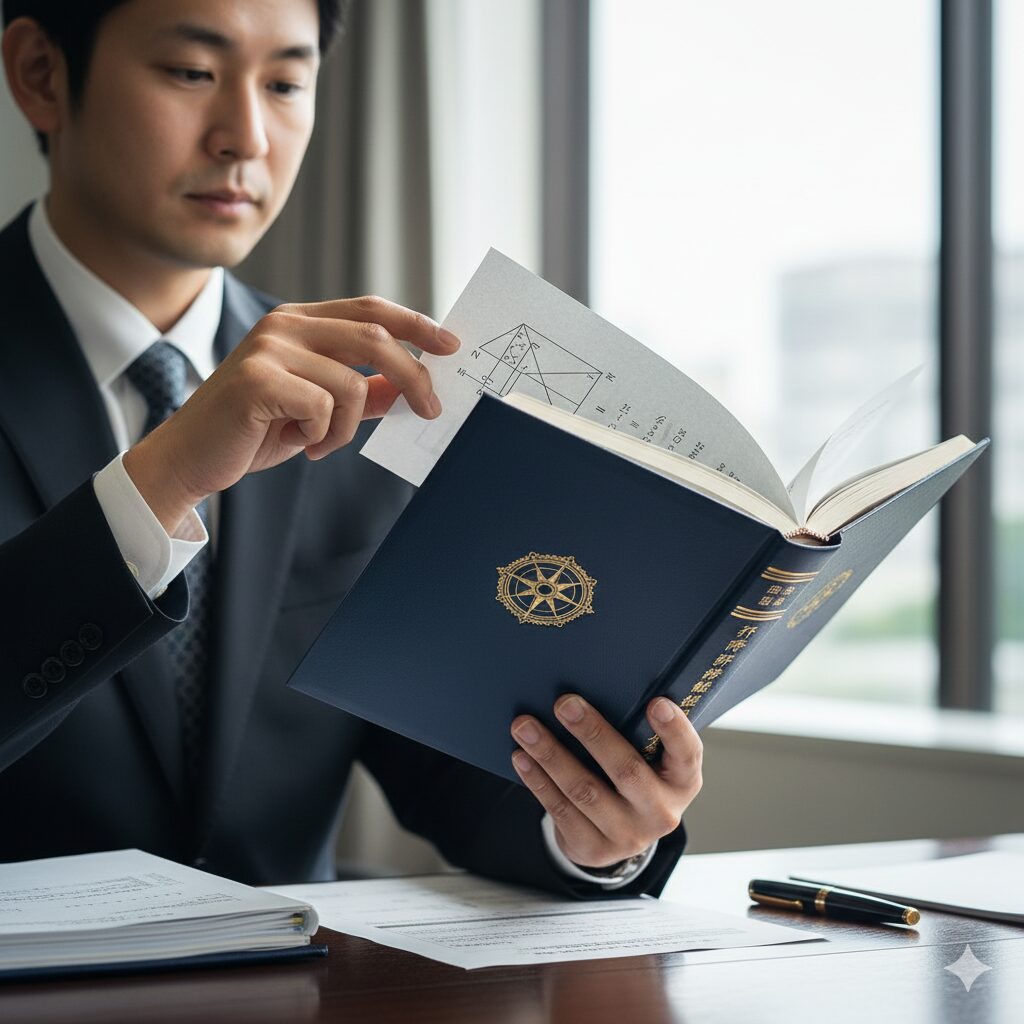
これまでお話ししてきた相続税評価額の様々な計算ルールですが、これは税理士が個々の判断で決めているわけではありません。すべての評価方法の根拠となっているのが、国税庁が定めている「財産評価基本通達」というものです。
これは、いわば相続財産を評価するための公式ルールブックであり、法律のような効力を持つ行政内部の規則です。預貯金や不動産はもちろん、株式、保険、書画骨董に至るまで、あらゆる財産の評価方法がこの通達で詳細に定められています。
この通達があるおかげで、日本全国どこでも、どの税理士が計算しても、原則として同じ財産は同じ評価額となり、課税の公平性が保たれるわけです。
もちろん、通達の文言は専門的で、一般の方がすべてを読み解くのは困難です。しかし、「国の定めた公平なルールに基づいて計算されているんだな」と知っておくだけでも、相続税に対する漠然とした不安が少し和らぐのではないでしょうか。
路線価と相続税評価額の基本
土地の評価方法を語る上で絶対に外せないのが「路線価(ろせんか)」です。これは、市街地の主要な道路に面した標準的な宅地1平方メートルあたりの評価額のことで、毎年7月初旬に国税庁から公表されます。
路線価は、国税庁のウェブサイト「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で、誰でも無料で閲覧することができます。
サイト上で住所を検索していくと、地図上に道路ごとに「300C」といった数字とアルファベットが表示されます。この数字が1平方メートルあたりの価額(千円単位)を意味します。(例:300C → 300,000円/㎡)
一般的に、この路線価は地価公示価格(正常な取引における時価の目安)の80%程度の水準になるように設定されています。
これは、売買価格の短期的な変動の影響を直接受けないようにし、安定した課税基準とするための配慮です。都市部のほとんどの宅地は、この路線価を用いて評価額を計算する「路線価方式」が採用されます。
相続財産に土地が含まれる方は、まずこの路線価を調べてみることが評価額を知る第一歩となります。
【評価額は「時価」ではない点に注意】
相続税計算で用いる土地の評価額は、実際の市場価格(時価)とは異なります。国税庁が定める「路線価」は地価公示価格の80%程度、「固定資産税評価額」は70%程度を目安に設定されています。
そのため、相続した土地を売却して納税資金に充てる場合などは、評価額と売却可能額に差があることを念頭に置いておく必要があります。
(参照:国税庁 財産評価基本通達)



どうでしょう、少しずつ評価額の全体像が見えてきましたか?特に土地の評価は「路線価方式」と「倍率方式」という2つの方法があって、ここが一番のポイントになります。
どちらを使うかは土地の場所によって決まっているので、次の章でその見分け方と具体的な計算方法を一緒に見ていきましょう。
ここを乗り越えれば、あなたも相続財産評価マスターに一歩近づきますよ!
土地の相続財産評価額の計算方法


相続税評価額の土地の計算方法
さて、いよいよ本丸、土地の相続税評価額の具体的な計算方法についてです。土地の評価方法は、前述の通り、主に以下の2つの方式があります。このどちらを用いるかは自分で選べるわけではなく、土地の所在地によってあらかじめ決められています。
- 路線価方式:主に市街地的形態を形成する地域に適用されます。
- 倍率方式:主に路線価が定められていない郊外や農村部、山林などに適用されます。
ご自身の土地がどちらに該当するかは、国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で所在地を検索すればすぐに判明します。
検索結果として路線価が定められた地図(路線価図)が表示されれば「路線価方式」、表示されなければ「評価倍率表」から該当する倍率を探し出して「倍率方式」で計算する、という流れになります。
相続した土地の評価額の調べ方


それでは、それぞれの方式での具体的な調べ方と計算手順を、もう少し詳しく見ていきましょう。
路線価方式の場合
路線価方式は、土地の正面路線価を基に、その土地の個別の形状などを加味して評価額を算出する方法です。基本的な計算式は以下の通りです。
路線価 × 各種補正率 × 土地の面積(地積) = 相続税評価額
【具体的なステップ】
- 路線価を調べる:国税庁の路線価図で、評価したい土地が面している道路に付された路線価(1㎡あたりの価額)を確認します。
- 各種補正を適用する:土地の形状は千差万別です。きれいな正方形や長方形とは限らず、奥行きが極端に長かったり、間口が狭かったり、角地だったりします。これらの個別要因による利用価値の違いを評価額に反映させるため、「補正」を行います。代表的なものに「奥行価格補正率」があります。
- 面積を乗じる:法務局で取得した登記簿謄本(全部事項証明書)や、固定資産税の課税明細書に記載されている正確な面積(地積)を掛け合わせます。
路線価方式の計算例
【条件】
- 正面路線価:200,000円/㎡
- 土地の面積:150㎡
- 土地の形状は整っており、各種補正は不要なケース
計算式:200,000円 × 150㎡ = 30,000,000円
この場合の相続税評価額は3,000万円となります。
倍率方式の場合
倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地を評価する方法で、計算は非常にシンプルです。
固定資産税評価額 × 国税庁が定める倍率 = 相続税評価額
【ステップ】
- 固定資産税評価額を調べる:固定資産税の納税通知書に同封の「課税明細書」で、該当する土地の「価格」または「評価額」を確認します。
- 倍率を調べる:国税庁の評価倍率表で、その土地の所在地および地目(宅地、田、畑など)に応じた倍率を確認します。宅地の場合、多くは「1.1」倍と定められています。
- 掛け合わせる:上記2つの数値を掛け合わせるだけで、相続税評価額が算出できます。
注意点
倍率方式で用いる「固定資産税評価額」は、必ず相続が発生した年度のものを使用してください。年度が異なると評価額も変わる可能性があるため、注意が必要です。
土地評価額の計算のポイント
土地の評価額をより正確に計算するためには、いくつか重要なポイントがあります。特に評価額に大きな影響を与えるのが、路線価方式における「各種補正」の適用です。
例えば、同じ面積の土地でも、道路に広く面した使いやすい土地と、道路に接する間口が2mしかない細長い土地では、その価値は大きく異なります。このような個別の事情を評価額に正しく反映させるのが補正の役割です。代表的な補正には以下のようなものがあります。
| 補正の種類 | 内容 |
|---|---|
| 奥行価格補正 | 道路からの奥行距離が標準的なものより長い、または短い場合に適用 |
| 不整形地補正 | 土地の形が正方形や長方形でない、いびつな形の場合に適用 |
| 間口狭小補正 | 道路に接している間口が狭い場合に適用 |
| 側方路線影響加算 | 角地など、正面と側方の2つの道路に接している場合に適用(評価額が上がる) |
| がけ地補正 | 土地の一部にがけ地が含まれている場合に適用 |
これらの補正計算は非常に専門的で、適用を誤ると評価額が大きく変わってしまいます。
特に、土地の形状が複雑な場合や、複数の道路に接している場合などは、無理に自分で計算せず、相続税に詳しい税理士に相談するのが最も安全で確実な方法と言えるでしょう。
評価額を正しく算出した後は、不動産をどのように分割するかも重要な検討事項になります。
相続税の土地評価を自分で行うには


ここまで読んで、「思ったより複雑だな…」と感じた方と、「このくらいなら自分でもできそうかも?」と感じた方に分かれるかもしれませんね。相続税の土地評価を自分で行うことには、当然ながらメリットとデメリットが存在します。
自分で評価する場合のメリット
- 専門家への報酬が不要:税理士に依頼する費用(一般的に遺産総額の0.5%~1.0%程度)を節約できます。
- 財産への理解が深まる:自ら資料を集め、計算することで、相続する財産の価値や状況を深く理解することができます。
自分で評価する場合のデメリットとリスク
- 計算ミス・評価誤りのリスク:特に各種補正や特例の適用を見落とすことで、本来よりも高い税額を納めてしまう可能性があります。
- 過少申告のリスク:逆に評価額を低く見積もりすぎると、税務調査で指摘され、過少申告加算税や延滞税といったペナルティが課される恐れがあります。財産が多い場合は、相続放棄の手続きも視野に入れる必要があります。
- 多大な時間と労力:市役所や法務局での資料収集、慣れない計算作業など、相当な時間と手間がかかることを覚悟する必要があります。
結論として、相続財産が預貯金と自宅の土地・建物のみで、その土地の形状もシンプル、といったケースであればご自身で挑戦するのも一つの手です。
しかし、土地が複数ある、形状が複雑、貸している土地がある、など少しでも不安な要素があれば、専門家である税理士に相談することを強くおすすめします。
【相続税申告の約86%は税理士が関与】
土地評価の複雑さもあり、相続税申告の多くは専門家である税理士に依頼されています。国税庁の発表によると、令和4事務年度における相続税の実地調査以外の申告では、税理士の関与割合は86.1%に上ります。特に土地の評価には専門知識が不可欠なため、計算に不安がある場合は専門家への相談が一般的です。
(出典:国税庁「令和4事務年度 国税庁実績評価書」)
相続税の土地計算シミュレーション活用法
「専門家に頼む前に、まずは大まかな金額だけでも知りたい!」というニーズは非常に多いです。そんな時に役立つのが、インターネット上で公開されている相続税の土地評価額を簡易的に計算できるシミュレーションサイトです。
税理士法人などが提供しているものが多く、住所や地番、面積、路線価などを入力するだけで、おおよその評価額を自動で算出してくれる非常に便利なツールです。
これらのサイトを活用することで、相続税がかかりそうかどうかの当たりをつけたり、遺産分割を話し合う際の参考資料にしたりすることができます。
ただし、これらのシミュレーションには限界もあります。ほとんどのサイトでは、前述したような複雑な各種補正率が考慮されていません。
そのため、算出されるのはあくまでも「補正前の基本的な評価額」であり、実際の申告で使う正確な価額とは異なる可能性があることを理解しておく必要があります。
シミュレーションは、「我が家の土地の評価額って、だいたいこのくらいの範囲なんだな」という最初のステップとして、上手に活用するのが良いでしょう。
相続財産 評価額 計算方法についてよくあるご質問FAQ


ここでは、相続財産の評価額計算に関するよくある質問にお答えしますね!



お疲れ様です!土地の評価額、いかがでしたか?専門用語が多くて大変だったかもしれませんが、基本的な流れは掴んでいただけたかと思います。
一番大事なのは、「正確な資料をもとに、決められたルールで計算する」ということです。
そして、少しでも「これはどうなんだろう?」と迷ったら、一人で抱え込まずに専門家の力を借りるのが、結果的に一番の近道になりますからね。
まとめ:正しい相続財産評価額の計算方法
- 相続税評価額は相続税計算専用の価額
- 基準は国税庁の財産評価基本通達で定められている
- 建物の評価額は固定資産税評価額と同じ
- 土地の評価額は路線価方式か倍率方式で計算する
- 路線価方式は市街地などで用いられる評価方法
- 倍率方式は郊外などで用いられる評価方法
- どちらの方式かは国税庁のHPで確認できる
- 路線価は道路に面した土地1㎡あたりの価額
- 倍率方式は固定資産税評価額に一定の倍率を掛ける
- 土地の形状が複雑な場合は補正計算が必要になる
- 補正計算は専門的な知識が求められる
- 自分で評価するメリットは費用の節約
- 自分で評価するデメリットは計算ミスのリスク
- シミュレーションサイトはあくまで目安として活用する
- 不動産以外の財産にもそれぞれ評価方法がある
今日からできるアクションプラン
- 固定資産税の納税通知書を探してみる:まずは財産の基礎情報が詰まったこの書類を確認しましょう。引き出しの奥に眠っていませんか?
- 国税庁のHPで自宅前の路線価を調べてみる:ゲーム感覚でOK!自分の土地の価値の目安を知ることは、資産管理の第一歩です。
- 相続する可能性のある財産をリストアップしてみる:預貯金、不動産、株、保険、自動車など、どんな財産があるかノートに書き出すだけで頭がスッキリ整理されます。
さあ、まずは最初の一歩から!未来の安心のために、今日から準備を始めましょう!
▼あわせて読みたい関連記事▼