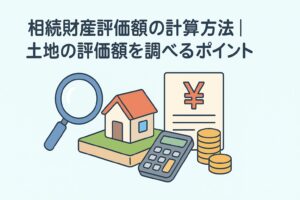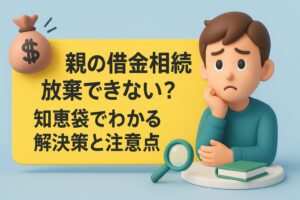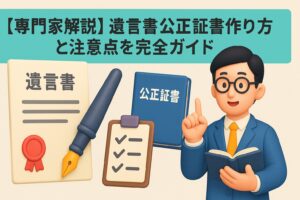「相続税って、うちには関係ないと思ってたけど…もしかして払うことになるの?」「相続税の節税方法を知りたいけど、初心者で何から手をつけていいか分からない!」なんて、不安に思っていませんか?僕、終活・相続の専門家カズも、これまでたくさんのご家族から同じような悩みを聞いてきました。
結論から言うと、相続税の節税方法は、初心者の方でもポイントさえ押さえればしっかり対策できます。相続税対策の基本は、生前から計画的に進めることです。
ただし、相続税対策として年間110万円の贈与だけを考えていたり、死後に相続税を減らす方法は?と慌てたりするケースでは注意が必要です。相続税対策が必要な人を見極め、現金や不動産、土地といった財産の種類に応じた最適な節税対策を考えることが重要になります。
中には相続税対策として会社設立といった選択肢や、あまり知られていない相続税の裏ワザも存在します。相続税を0円にするにはどうすればいいですか?という疑問にも、この記事でしっかりお答えしますね。
この記事では、相続税の節税は死後でも可能なのかといった疑問から、具体的な対策まで、専門家の視点から分かりやすく解説します。
- 相続税対策が必要になる人の具体的な基準
- 初心者でも始めやすい基本的な相続税の節税方法
- 不動産や生命保険などを活用した応用的な節税テクニック
- 相続発生後でも間に合う節税対策と注意点
 コンサルタント @KAZU
コンサルタント @KAZU相続税対策って聞くと、すごく難しくてお金持ちだけの話って思いがちですよね。でも、実はそんなことないんです。大切なのは「我が家の場合はどうかな?」と具体的に考えてみること。この記事をガイドブック代わりに、まずは終活とは何かを理解し、第一歩を踏み出してみましょう!
相続税の節税方法【初心者向け】の基本


相続税対策はどんな人が必要な人か
「そもそも、うちに相続税対策って必要なの?」これは、僕がお客様から一番よく聞かれる質問であり、すべてのスタート地点となる最も重要な問いです。
結論として、遺産の総額が「基礎控除額」を超える可能性がある人は、相続税対策を検討する必要があります。基礎控除額とは、いわば「ここまでなら税金はかかりませんよ」という国が定めた非課税のボーダーラインのことです。
この金額を1円でも超えた部分に対して、相続税が課税される仕組みになっています。
この大切な基礎控除額の計算方法は、「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」という式で求められます。例えば、ご家族が配偶者(奥様)と子供2人の合計3人だった場合、基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円」となります。
このケースでは、遺産の総額が4,800万円を超えなければ、相続税の申告も納税も一切必要ない、ということになりますね。
法定相続人とは誰のこと?
法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続する権利を持つ人のことです。誰が法定相続人になるかには、明確な優先順位があります。
- 常に相続人:配偶者(夫または妻)
- 第1順位:子供(亡くなっている場合は孫)
- 第2順位:親(亡くなっている場合は祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)
上の順位の人が一人でもいる場合、下の順位の人は相続人にはなれません。例えば、子供がいる場合は、親や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。
「うちはそんなに財産ないから大丈夫」と安心している方も、一度立ち止まって考えてみてください。ご自宅の不動産(土地・家)、預貯金、株式や投資信託、生命保険金、自動車、ゴルフ会員権などをすべて合計すると、予想外に大きな金額になることがあります。
特に、長年都市部にお住まいの方は、ご自身が思っている以上に土地の評価額が高くなっており、それだけで基礎控除額を超えてしまうケースも決して珍しくありません。まずはご自身の財産をリストアップし、おおよその総額を把握することが、全ての相続税対策の第一歩ですよ。
【約10人に1人が相続税の課税対象に】
国税庁の発表によると、令和4年中に亡くなった方(被相続人数)約157万人のうち、相続税の課税対象となった被相続人数は約15万人で、その割合は約9.6%にのぼります。
これは、およそ10人に1人が相続税の対象となっている計算です。特に都市部では地価が高いため、課税対象となる方の割合はさらに高くなる傾向にあります。
まずは知りたい相続税対策の基本


相続税対策と聞くと、複雑で難しそうに感じるかもしれませんが、その基本は3つのシンプルな柱で成り立っています。この3つを頭に入れておくだけで、専門家の話もぐっと理解しやすくなりますし、ご自身でやるべきことの方向性が見えてきます。
1つ目の柱は、「相続財産そのものを減らす(生前贈与など)」ことです。これは最も直感的で分かりやすい方法です。
将来、相続税の課税対象となる財産を、元気なうちから計画的に子供や孫に贈与していくことで、課税対象となる財産の山を少しずつ小さくしていくイメージですね。年間110万円の非課税枠を使った「暦年贈与」がその代表例です。
2つ目の柱は、「財産の評価額を下げる(資産の組み換え)」という考え方です。同じ1,000万円の価値を持つ財産でも、現金で持っている場合と、不動産で持っている場合とでは、相続税を計算する際の評価額(値段)が異なります。
一般的に不動産の評価額は時価よりも低くなるため、現金を不動産に換えておくことで、財産の価値を維持しつつ、税金の計算上の評価額だけを圧縮できる可能性があります。これを資産の組み換えと呼びます。
そして3つ目の柱が、「納税資金を準備しておく(生命保険など)」ことです。相続税は、原則として相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、現金で一括納付しなければなりません。
遺産のほとんどが不動産だった場合、「納税するためにお父さんが遺してくれた家を売却しなくては…」という悲しい事態に陥りかねません。
そうならないよう、生命保険などを活用して、いざという時にスムーズに納税できる現金を準備しておくことも、家族の生活を守るための立派な対策の一つなのです。
注意点:相続税対策というと、どうしても「節税」ばかりに目が行きがちです。しかし、それと同じくらい重要なのが、家族が財産の分け方で揉めてしまう、いわゆる「争族」を防ぐための対策です。
せっかく節税対策をしても、家族の仲が悪くなってしまっては元も子もありません。遺言書を作成するなど、家族が円満に相続を終えられるための準備も、決して忘れないようにしましょう。
相続税を0円にするにはどうすればいいですか?
「できることなら、大切な財産は1円でも多く家族に遺したい。相続税を0円にすることはできないの?」そのお気持ち、専門家として痛いほどよく分かります。
結論からお伝えすると、相続税を0円にするための最も確実な方法は、遺産の総額を前述した「基礎控除額」以下に抑えることです。
生前贈与などを計画的に活用し、将来の相続財産が非課税枠内に収まるようにコントロールできれば、相続税の心配はなくなります。
しかし、「うちの財産は、どう頑張っても基礎控除額を超えてしまいそう…」という方もいらっしゃるでしょう。ご安心ください。
そのような場合でも、税金の特例制度をうまく活用することで、結果的に納税額が0円になるケースはたくさんあります。特に強力なのが、次の2つの制度です。
| 特例制度の名前 | 内容 | 初心者向けポイント |
|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者が相続した遺産が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のどちらか多い金額まで相続税がかからなくなる制度。 | 多くのケースで配偶者の相続税が0円になりますが、次にその配偶者が亡くなった時(二次相続)の税負担が重くなる可能性も考慮が必要です。 |
| 小規模宅地等の特例 | 亡くなった方が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件を満たせば、その土地の評価額を最大80%も減額できる制度。 | 非常に節税効果が高い反面、「誰が相続するか」「相続後どうするか」などの適用要件が非常に複雑です。専門家への相談が必須の特例と言えます。 |
これらの特例は、いわば相続税の切り札です。適用できるかどうかで、納税額が数千万円単位で変わることもあります。
豆知識:これらの特例を適用して計算上の納税額が0円になったとしても、「うちは税金ゼロだから何もしなくていいや」とはなりません。
税務署に対して「私たちは、この特例を使って計算した結果、納税額が0円になりました」という意思表示、つまり相続税の申告手続きそのものは必ず必要になります。
この申告を忘れると、特例の適用が受けられなくなり、後から多額の追徴課税やペナルティが発生する可能性があるので、くれぐれも注意してくださいね。
ご自身のケースでこれらの特例が使えるかどうか、少しでも気になったら、迷わず専門家に相談してみるのが安心への一番の近道ですよ。
相続税対策の基本、年間110万円の贈与


相続税対策と聞いて、多くの方が真っ先に思い浮かべるのが「年間110万円までの生前贈与」ではないでしょうか。これは「暦年贈与(れきねんぞうよ)」と呼ばれる方法で、数ある節税対策の中でも、最もポピュラーで誰でも始めやすい、基本中の基本と言えるでしょう。
この制度の仕組みは非常にシンプルです。1人の人が1年間(その年の1月1日から12月31日まで)に他人からもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税は一切かからない、というものです。この便利な非課税枠は、財産を「あげた人」ではなく「もらった人」を基準に計算されます。これが大きなポイントです。
例えば、お子様2人とお孫さん2人の合計4人に、それぞれ毎年110万円ずつ贈与するとしましょう。すると、1年間で「110万円 × 4人 = 440万円」もの財産を、完全に非課税で次の世代に移転できることになります。
これを10年間続ければ、なんと4,400万円もの財産を、将来の相続財産の山から取り除くことができるわけですね。こうした生前贈与の成功例は数多くあります。
このように、時間を味方につけることで絶大な効果を発揮するのが暦年贈与の魅力ですが、正しく行わないと思わぬ落とし穴にはまることもあります。
暦年贈与で絶対に押さえておきたい注意点
- 贈与の証拠をしっかり残す:後日、税務署から「それは贈与ではなく、故人が家族の名義を借りていただけの預金(名義預金)ですよね?」と指摘されないよう、対策が不可欠です。
面倒でも毎年「贈与契約書」を作成したり、手渡しではなく銀行振込を利用したりして、贈与の事実が客観的に誰の目にも明らかな形で証拠を残すようにしましょう。 - 相続開始前の贈与は加算されるルール:「亡くなる直前に慌てて贈与すればいいや」という考えは通用しません。
2024年からの税制改正により、亡くなった日(相続開始日)から遡って7年以内に行われた贈与は、原則として相続財産に持ち戻して相続税の計算対象となります(この期間は段階的に3年から7年へと延長されています)。対策を始めるなら、一日でも早いうちから計画的に行うことが何よりも重要です。
また、毎年同じ日に同じ金額を贈与していると、「最初からまとまった金額を分割で贈与する約束だった(定期贈与)」とみなされ、初年に一括で多額の贈与税が課税されるリスクもゼロではありません。
これを避けるためにも、贈与の都度、契約書を交わすなどの一手間が、後々の安心につながります。手軽に始められるからこそ、正しいやり方をきっちり理解しておくことが大切ですね。
相続税の節税は死後でも間に合うか
「親が元気なうちに対策の話なんてできなかった…」「突然のことで、何も準備しないまま相続が起きてしまった…」そんな時、もう節税は諦めるしかないのでしょうか?いいえ、そんなことはありません。
結論から言うと、相続が発生した後(死後)からでも打てる手はあります。もちろん、生前から計画的に対策するのに比べると使える技の数は減ってしまいますが、それでも納税額を大きく左右する重要なポイントがいくつか残されています。
相続発生後にできる最も影響の大きい対策、それは「遺産分割のやり方を工夫する」ことです。遺産分割とは、残された相続人全員で「誰が、どの財産を、どれだけ受け継ぐか」を話し合って決める手続きです。
この分け方一つで、使える特例が変わってくるため、相続税の総額も大きく変動するのです。例えば、先ほどご紹介した「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」は、まさに誰が何を相続するかによって適用できるかどうかが決まる、遺産分割の最たる例と言えます。
また、「相続財産の評価方法を最適化する」ことも非常に重要なポイントです。特に土地(不動産)の評価は一筋縄ではいきません。土地の形や立地、周辺環境など、評価額を下げるための様々な減額要因が存在します。
こうした要素を一つひとつ丁寧に拾い上げ、財産の評価額を適正に下げることができれば、それは直接的な節税につながります。これは専門家である税理士の腕の見せ所でもありますね。
他にも、故人の葬儀にかかった費用を遺産総額から控除したり、生命保険金の非課税枠をきちんと適用したりと、申告手続きの中でできることは意外とたくさんあるのです。
生前の対策が十分でなかったとしても、決して悲観する必要はありません。相続税の申告期限である「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」までが、最後の勝負期間です。
できるだけ早い段階で相続に強い専門家に相談し、残された選択肢の中で、ご家族にとって最善の方法を見つけ出すことが何よりも重要になります。
死後に相続税を減らす方法は?


前述の通り、相続が始まってからでも相続税を減らす方法は残されています。ここでは、特に効果が大きく、実務でも頻繁に検討される代表的な方法を、もう少し具体的に掘り下げて見ていきましょう。
一つ目は、「配偶者の税額軽減を最大限活用する」ことです。この特例を使えば、配偶者は最低でも1億6,000万円までは相続税がかかりませんから、一次相続(例えばお父様が亡くなった時)の税負担を劇的に減らすことができます。
ただし、ここで注意したいのが二次相続(次にお母様が亡くなった時)です。一次相続で配偶者が財産を相続しすぎると、その財産が二次相続の課税対象となり、結果的に子供たちの税負担が重くなってしまう可能性があります。家族全体のトータルの納税額を見据えたバランス感覚が求められます。
二つ目は、「小規模宅地等の特例を漏れなく適用する」ことです。これは、亡くなった方が住んでいたご自宅の土地などを相続した場合に、その土地の評価額を最大80%も減額できるという、相続税対策の中でも屈指の強力な特例です。
適用できるかできないかで、納税額が数百万、場合によっては数千万円単位で変わることも珍しくありません。誰が相続するか、相続後も住み続けるか、といった適用要件が非常に複雑なため、専門家と入念な打ち合わせの上で、誰が相続するのが最も有利かを判断する必要があります。
三つ目は、「相続財産を専門家の目で正しく評価する」ことです。特に土地は、一つとして同じものはなく、評価が非常に難しい財産です。
例えば、土地の形状がいびつな「不整形地」であったり、公道に直接面していない土地であったりする場合など、様々な要因で評価額を下げることができます。こうした減額要因を見逃さず、財産の価値を適正に評価し直すことができれば、大きな節税につながります。
その他にも、生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)の適用や、10年以内に相次いで相続があった場合に税額を控除できる「相次相続控除」といった制度もあります。
相続税申告は、単なる数字の計算作業ではありません。税金の法律や特例の知識を総動員して、納税額を適正化する最後のチャンスだと考えることが大切です。



どうでしょう?相続税対策って、本当に色々な角度からのアプローチがあるんです。
まるでパズルみたいですよね。一つ一つのピース(対策)を理解して、ご自身の家族という絵にどう当てはめていくか。
それを一緒に考えるのが僕たち専門家の役目なんです。
相続税の節税方法【初心者向け】具体策


【相続財産の約7割は「不動産」と「現金・預貯金」】
国税庁の統計によれば、相続税の対象となった財産の内訳で最も大きな割合を占めるのは「現金・預貯金等」で35.2%、次いで「土地」が32.5%となっています。
この2つを合わせると67.7%となり、相続財産のおよそ7割に達します。このことから、いかに現金・預貯金と不動産に対する相続税対策が重要であるかが分かります。
相続税対策における現金の扱い方
相続財産の中で、現金や預貯金は最もシンプルであると同時に、対策が難しい財産の一つです。なぜなら、不動産などと違って評価額を下げるという概念がなく、1円は1円、1億円は1億円として、額面通りに評価されてしまうからです。
そのため、現金や預貯金が潤沢にある場合の相続税対策の基本戦略は、「評価額の低い他の財産に組み替える」か「生前に計画的に贈与してしまう」かの2つが中心になります。
前者(資産の組み換え)の代表例が、現金を不動産、特に賃貸アパートなどの購入資金に充てる方法です。これは、不動産の相続税評価額が時価(実勢価格)よりも低く計算される仕組みを利用したもので、財産の価値を保ちながら課税対象額を圧縮する効果が期待できます。
また、生命保険に加入して、現金を「死亡保険金」という形で家族に遺す方法も非常に有効です。死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という強力な非課税枠があるため、同額の現金を預貯金としてそのまま遺すよりも、税負担を軽減できるのです。
豆知識:タンス預金は税務署になぜバレる?
「税務署に分からないように、金融機関を通さず現金で自宅に保管(タンス預金)しておけば大丈夫」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、これは極めて危険な考え方です。
税務署は、相続が発生すると、亡くなった方やそのご家族の過去の預金口座の動きを、数年分(時には10年近く)遡って徹底的に調査する権限(税務調査)を持っています。
その過程で、使途が不明な大きな出金があれば、「そのお金はタンス預金としてご自宅にありませんか?」と、ほぼ確実に指摘されると考えておいた方が良いでしょう。正直な申告が一番の近道です。
【税務調査で最も多く見つかるのは「現金・預貯金」】
国税庁が公表した相続税の調査結果によると、税務調査で申告漏れが指摘された財産の中で、金額ベースで最も多かったのは「現金・預貯金等」で、全体の約31.6%を占めています。
税務署は金融機関への照会権限を持っており、過去の入出金履歴を詳細に調査できるため、「タンス預金」も高確率で把握されるのが実情です。
もちろん、後者(生前贈与)として、これまでにご紹介した年間110万円の暦年贈与や、お孫さんへの教育資金贈与(最大1,500万円非課税)などの特例を活用して、計画的に現金を次の世代に移していくことも、王道かつ非常に有効な手段です。
手元に現金が多い方ほど、早めにこれらの対策を組み合わせ、検討を始めることを強くお勧めします。
相続税対策で不動産を活用するコツ


不動産は、相続税対策において「攻め」の切り札となりうる、非常に重要な役割を果たします。その最大の理由は、不動産の相続税評価額が、実際に市場で売買される価格(時価)よりも低く設定されているという、税制上の大きな特徴にあります。
一般的に、土地は時価の80%程度とされる「路線価」で、建物は建築費の50%~70%程度とされる「固定資産税評価額」で評価されます。
つまり、仮に1億円の現金を持っているよりも、1億円で不動産を購入して所有している方が、相続税を計算する上では有利になるわけです。この時価と評価額の差(ギャップ)を戦略的に活用するのが、不動産を使った節税の基本となります。
では、具体的にどのようなコツがあるのでしょうか。初心者の方がまず押さえておきたいのは、以下の2点です。
- 賃貸物件として活用する:ご自宅のようにご自身で使用している不動産よりも、アパートやマンションとして他人に貸している不動産の方が、評価額はさらに低くなります。これは、入居者がいることで所有者の自由な使用が制限されるため、「貸家建付地(かしやつけたてち)」や「貸家(かしや)」の評価減が適用されるからです。
- 小規模宅地等の特例を最大限活用する:前述の通り、ご自宅や事業用の土地に適用できるこの特例は、不動産節税のまさに切り札です。例えば、親との同居を始めることでこの特例の適用要件を満たすなど、生前から計画的に準備を進めることも有効な対策の一つとなります。将来的に不動産の名義変更も視野に入れる必要があります。
注意点:節税効果が高いからといって、安易に不動産投資に手を出すのは危険です。アパート経営には、空室リスクや家賃下落リスク、老朽化に伴う修繕費用の発生など、当然ながら事業としてのリスクが伴います。
また、2024年1月以降、タワーマンションの高層階などを利用した過度な節税には国税庁が歯止めをかける新しい評価ルールが導入されています。目先の節税効果だけに囚われず、長期的な収益性や資産価値まで含めて総合的に判断することが、成功の秘訣です。(出典:国税庁「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」)
相続税対策で土地の評価を下げるには
土地の評価額を1円でも下げることができれば、その分、相続税額を直接的に減らすことにつながります。土地の評価は非常に専門的で、税理士によって評価額が異なることも珍しくありませんが、初心者の方でも「こんな土地は評価が下がる可能性があるんだ」という基本的な考え方を知っておくことは非常に有益です。
まず、土地の相続税評価は、国税庁が道路一本一本に設定した価格である「路線価」を基に計算するのが基本です(路線価が定められていない地域では固定資産税評価額に一定の倍率を掛ける倍率方式が使われます)。
この路線価に土地の面積を掛けて基本的な評価額を算出しますが、土地の個性に応じて、ここから様々な補正(減額)を行うことができるのです。より詳しくは「相続不動産評価額の調べ方」の記事も参考にしてください。
例えば、一般的に「使い勝手が悪い」とされる、以下のような土地は評価額が下がる代表例です。
- 形のいびつな土地(不整形地):きれいな正方形や長方形ではなく、三角形であったり、一部が欠けていたりする使いにくい形の土地は評価が下がります。
- 間口が狭い土地・奥行きが長すぎる土地:道路に接している部分(間口)が極端に狭かったり、逆に細長すぎて有効活用しにくい土地も減額の対象です。
- 私道にしか面していない土地:不特定多数の人が通行できる公道ではなく、特定の個人や法人が所有する私道にしか出入り口がない土地も、利便性が低いとされ評価が下がります。
- 広すぎる土地(地積規模の大きな宅地):都市部で500㎡以上など、一定以上の面積を持つ広大な土地は、個人で利用するには大きすぎるため、市場性が低いと判断され評価額が下がります。
また、応用的なテクニックとして、一つの土地を複数に法的に分ける「分筆(ぶんぴつ)」を行うことで、分筆後のそれぞれの土地の評価額の合計が、分筆前の評価額よりも低くなるケースもあります。
ただし、明らかに節税目的だけと判断されるような不合理な分筆は、税務署に否認されるリスクがあるため、実行には専門家による慎重な判断が不可欠です。
これらの評価減の規定を漏れなく適用するには、法律の知識だけでなく、現地の状況を正確に把握する実務経験が求められます。
相続財産に土地が含まれる場合は、相続税に強い税理士に評価を依頼することが、適正な納税と節税への最も確実な道と言えるでしょう。
相続税対策としての会社設立のメリット


「相続税対策のために、会社を設立する?」と聞くと、多くの方が「自分には関係ない、大資産家の話だろう」と思われるかもしれませんね。
確かに、これは特に賃貸不動産を多く所有している方や、ご自身で事業を営んでいる方が検討する、少し応用的な節税方法です。
具体的には、個人が所有している賃貸アパートや駐車場などを管理するための「資産管理会社」を設立し、その会社に財産を移転(売却など)する手法です。この方法には、相続税対策上、主に2つの大きなメリットが期待できます。
一つ目のメリットは、所得の分散による、将来の相続財産の増加抑制効果です。個人で家賃収入などを受け取ると、税金を引かれた後の利益はすべて個人の財産として蓄積され、将来の相続財産は雪だるま式に増え続けてしまいます。
一方、法人(会社)で収入を受け取り、ご家族を役員にして役員報酬を支払う形にすれば、所得をご家族に分散できます。これにより、ご自身の財産が急激に増えるのを防ぎ、結果的に将来の相続税を抑えることにつながるのです。
二つ目のメリットは、相続時の財産評価額の引き下げ効果です。資産管理会社へ財産を移転した後、相続の対象となるのは不動産そのものではなく、その会社の「株式」になります。
この会社の株式の価値(株価)を計算する際、一定の条件下では、個人で不動産を直接相続するよりも、株式として相続する方が低く評価されることがあります。この評価額の差を利用して、相続税の負担を軽減できる可能性があるわけです。
注意点:もちろん、良いことばかりではありません。会社を設立するには、登録免許税などの設立費用がかかりますし、運営していく上でも税理士への顧問料などの維持コストが発生します。
また、税務上の手続きも個人に比べて格段に複雑になります。ある程度の資産規模や収益がないと、コスト倒れになってしまう可能性も否定できません。
メリットとデメリットを天秤にかけ、慎重に検討する必要がある、まさに上級者向けの対策と言えるでしょう。
知っておきたい相続税の節税対策と裏ワザ
これまで解説してきた王道の節税対策に加えて、知っておくと役立つ、あるいは状況によっては「裏ワザ」的に活用できる方法もいくつかご紹介しておきましょう。
一つは、「養子縁組」です。法定相続人の数が1人増えれば、基礎控除額が600万円、生命保険金の非課税枠が500万円増えるため、直接的な節税につながります。
例えば、お子様の配偶者(お嫁さんなど)やお孫さんを養子に迎えるケースが考えられます。ただし、相続税法上、法定相続人の数に含められる養子の数には制限(実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで)がある点には注意が必要です。
また、何よりも家族関係や身分関係に大きな影響を与える行為ですから、節税目的だけで安易に行うべきではないことを肝に銘じておきましょう。
二つ目は、「墓地や仏壇などの生前購入」です。お墓や仏壇、仏具といった、ご先祖様を祀るための財産は「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれ、その性質から相続税が非課税とされています。
そのため、生前に現金で購入しておくことで、その分の現金を非課税財産に換えることができ、課税対象となる相続財産を減らす効果があります。最近では墓じまいを考える方も増えていますが、新たにお墓を持つことも一つの選択肢です。
ただし、投資目的とみなされるような、過度に高価な純金製の仏具などは、課税対象となる可能性があるので常識の範囲内で行うことが大切です。
最後の裏ワザとして、「二次相続まで見据えた総合的なシミュレーション」が挙げられます。これは節税対策の総仕上げとも言える考え方です。
例えば、一次相続(お父様の相続)の際に、配偶者の税額軽減をフル活用して相続税を0円にしたとします。一見、大成功に見えますが、その結果、お母様の財産が過大になってしまい、二次相続(お母様の相続)の際に、子供たちが一次相続の時以上に多額の税金を支払うことになる、というケースは少なくありません。
一次相続と二次相続という2つのステージを一つの物語として捉え、家族全体のトータルの納税額が最も少なくなるような遺産分割の黄金比を見つけ出すこと。これが本当の意味でのプロの節税対策と言えるでしょう。
相続税の節税方法についてよくあるご質問FAQ


まとめ:相続税の節税方法を初心者が学ぶ重要性



お疲れ様でした!ここまで読み進めてくださったあなたは、もう相続税対策の初心者卒業です!
大切なのは、得た知識をもとに「我が家だったらどうだろう?」と、ご家族で話してみること。それが、最高の相続対策への第一歩になりますからね。
- 相続税の節税方法は初心者でもポイントを押さえれば実践可能
- 対策の基本は「財産を減らす」「評価額を下げる」「納税資金の準備」
- 相続税がかかるかは遺産総額が基礎控除額を超えるかで決まる
- 基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算
- 年間110万円までの暦年贈与は手軽に始められる基本の対策
- 亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に加算されるので注意が必要
- 相続発生後でも遺産分割の工夫や特例適用で節税は可能
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は効果が大きい
- 現金は評価額が下がらないため他の資産への組み替えが有効
- 不動産は時価より評価額が低いため節税に活用しやすい
- 土地の評価は不整形地など様々な減額要因があるため専門家への相談が鍵
- 資産管理会社の設立は所得分散などで節税になる上級者向けの方法
- 養子縁組で法定相続人を増やすと基礎控除額が増える
- お墓や仏壇の生前購入は非課税財産への組み替えになる
- 一次相続だけでなく二次相続まで見据えた対策が重要
今日からできるアクションプラン
相続税対策の第一歩は、現状把握から始まります。まずは難しく考えず、以下の2つをノートに書き出してみませんか?
- おおまかな財産リストの作成:ご自宅の土地・建物、預貯金、生命保険など、どんな財産がどれくらいあるかザックリと書き出してみましょう。
- 法定相続人の確認:ご自身の家族の場合、誰が法定相続人になるのかを図に書いてみましょう。
この2つをやるだけでも、「うちは基礎控除額を超えそうかな?」という目安がつき、次の一手を考えるきっかけになりますよ!
▼あわせて読みたい関連記事▼