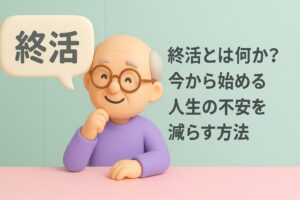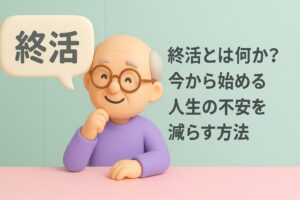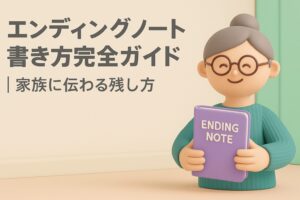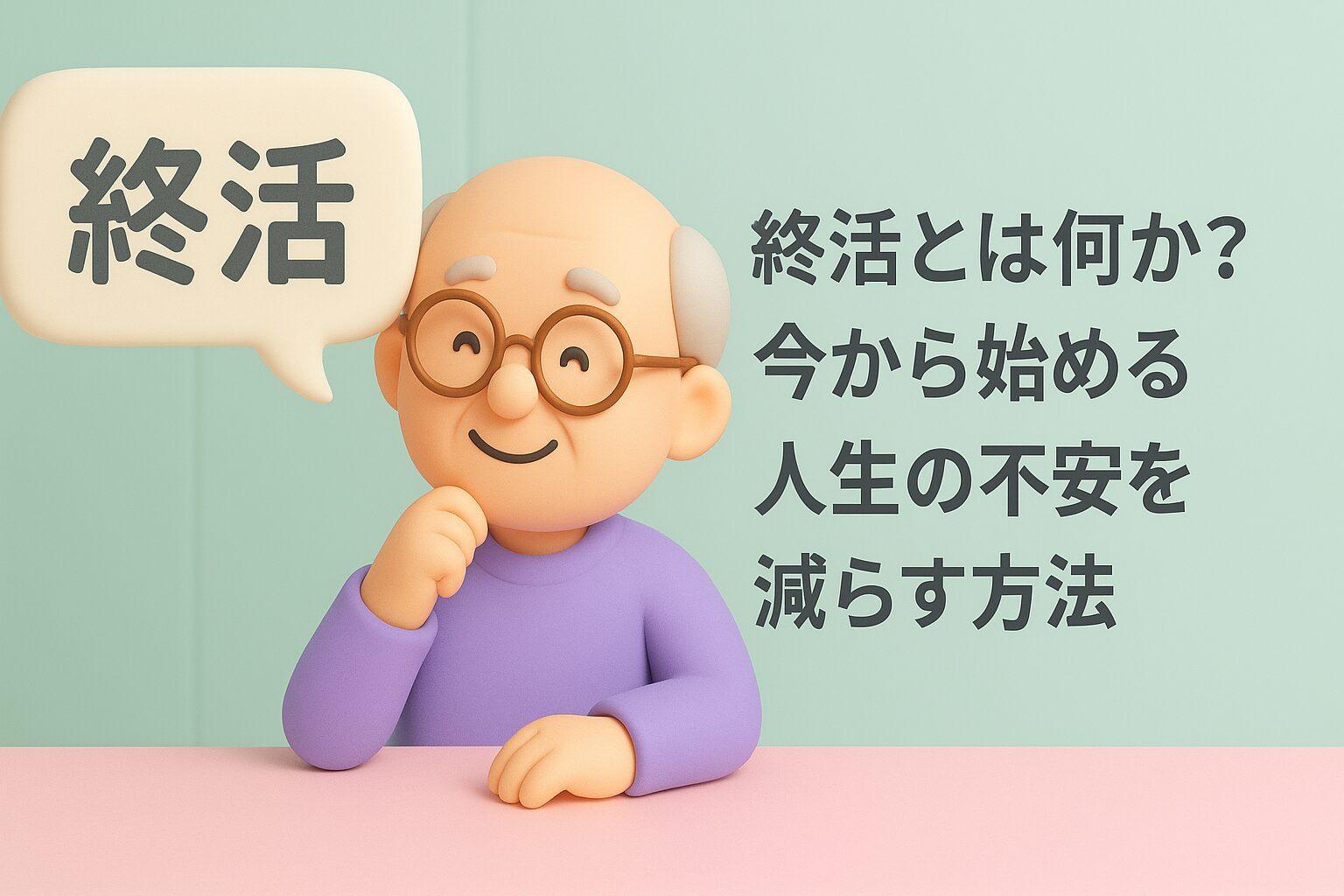
「最近よく聞く『終活』って、ぶっちゃけ何なの?」「何から手をつけていいかサっぱり…」なんて思っていませんか?僕もこの仕事に就く前は、終活って聞くと、なんだか縁起でもないし、面倒くさそうだなって感じていました。
でもですね、何もしないでいると、いざという時に大切な家族に大きな負担をかけてしまったり、ご自身の財産や想いが正しく伝わらないデメリットも実はあるんです。この記事では、終活なんの略?という基本的な疑問から、終活で大切な10ことは何ですか?という核心まで、しっかり解説します。
終活は何から始めるべきか、40代や50代、または20代の考え方、おひとりさまの場合のポイント、そして終活ノートや身辺整理の具体的な進め方まで、専門家の僕カズがユーモアを交えてお話ししますので、リラックスして読んでみてくださいね!
- 終活の基本的な意味と目的
- 年代別(20代〜50代)の終活の始め方
- 具体的な終活のやることリストと手順
- 家族に迷惑をかけないための注意点
 コンサルタント @KAZU
コンサルタント @KAZUこんにちは、終活・相続専門家のカズです!「終活」と聞くと、身構えてしまう方が多いのですが、実は「これからの人生を、もっと自分らしく、いきいきと過ごすための準備」なんですよ。この記事では、そんな前向きな活動としての終活の魅力を、僕の経験も交えながらお伝えしていきますね。
終活とは何か?その目的と意味を解説


そもそも終活なんの略か知っていますか
まず、基本的なところからお話ししますね。「終活」という言葉、これは「人生の終わりのための活動」の略です。よく就職活動の「就活」と間違えられますが、全然違いますよ(笑)。
多くの方が「死ぬ準備」という少しネガティブなイメージを持っているかもしれません。しかし、僕たち専門家の間では、「残りの人生をより良く生きるための活動」と捉えています。
自分の人生を一度ここで振り返り、医療や介護、財産、そしてお葬式といったことを整理しておく。そうすることで、漠然とした将来への不安が解消され、これからの時間を安心して、前向きに過ごせるようになるんです。



僕のお客様でも、「終活を始めたら、やりたいことがたくさん見つかって毎日が楽しくなった!」なんておっしゃる方が結構多いんですよ。まさに人生の棚卸しですね。
終活の言い換えでポジティブな側面に注目


「終活」という言葉がどうも…という方は、ポジティブな言葉に置き換えて考えてみるのがおすすめです。これも立派な終活の第一歩ですよ。
例えば、こんな言い換えはいかがでしょうか。
終活のポジティブな言い換え例
- ライフエンディング・デザイン:自分の人生の締めくくり方を自らデザインする、という前向きな考え方です。
- セカンドライフプラン:定年後など、これからの人生をどう楽しむか計画すること。これも終活の一部です。
- 未来への引き継ぎ準備:大切な家族へ、迷惑ではなく「想い」と「安心」を引き継ぐための準備。



このように言うと、なんだかワクワクしてきませんか?言ってしまえば、終活は未来の自分と家族へのプレゼント準備みたいなものなんです。どんなプレゼントを用意するか、考えるだけで少し楽しくなりますよね。
終活のデメリットと注意点を先に確認
ただ、もちろん良いことばかりではありません。進め方を間違えると、かえってトラブルの原因になる可能性もゼロではないので、先にデメリットや注意点も正直にお伝えしておきますね。
終活を進める上での注意点
- 家族とのコミュニケーション不足:自分一人で勝手に進めてしまうと、後から家族が内容を知って「そんなつもりじゃなかったのに」と揉める原因になります。特に葬儀やお墓のことは、事前に相談が大切です。
- ネガティブな気持ちになる可能性:死と向き合う活動なので、人によっては気分が落ち込んでしまうことがあります。無理せず、自分のペースで、楽しい計画(旅行など)も一緒に立てるのがコツです。
- 情報管理のリスク:エンディングノートなどに個人情報をたくさん書くので、保管場所は厳重に管理しましょう。特にパスワードなどのデジタル情報は注意が必要です。



僕の失敗談ですが、駆け出しの頃、あるお客様に良かれと思ってどんどん終活プランを提案したら、「そんなに急かされると、早く死ねって言われてるみたいだ」と少しお叱りを受けた経験があります。それ以来、本人の気持ちとペースに寄り添うこと、そしてご家族との対話を促すことを何よりも大切にしています。
終活は何歳から始めるべきか解説します


「で、結局のところ終活は何歳から始めるべきなの?」これは本当によく聞かれる質問No.1です。
結論から言うと、「終活を始めたいと思ったその時が、あなたの始めどき」です。年齢に決まりは一切ありません。なぜなら、終活は元気で、判断力がしっかりしているうちに進めるのが一番スムーズだからです。
▼あわせて読みたい
終活いつから始めるメリット満載!専門家が年代別に解説
病気になってから、あるいは判断能力が衰えてからだと、できることが限られてしまいます。それに、不慮の事故は年齢に関係なく起こり得ますよね。だからこそ、この記事を読んで「ちょっとやってみようかな」と思った今が、最高のタイミングなんです。
20代から考える終活の意外なメリット
「20代で終活なんて早すぎでしょ!」と思いますよね。わかります。でも、20代だからこそやっておくとメチャクチャ良いことがあるんです。
20代の終活は、いわば「人生のコンパス作り」。主な目的は以下の通りです。
- デジタル資産の整理:SNSアカウントやサブスク、ネット銀行の口座など、今や財産はデジタルが中心。IDやパスワードを整理しておくだけでも、万が一の時に家族は本当に助かります。
- 生命保険の見直し:社会人になったタイミングで、自分に必要な保障は何かを考える良いきっかけになります。
- 人生設計の明確化:エンディングを意識することで、「20代のうちにこれをやりたい」「こんな人生を送りたい」という目標がクリアになります。



僕が担当した20代のお客様は、「終活をきっかけに自分の価値観がハッキリして、転職に踏み切れた」と話していました。死を考えることは、どう生きるかを考えることと直結しているんですね。
親のことも考える40代の終活のポイント


40代になると、自分のことだけでなく、親の健康や将来も気になり始めますよね。いわゆる「サンドイッチ世代」で、子育てと親の介護の板挟み…なんて方も多いかもしれません。
40代の終活は、「自分の準備」と「親との対話のきっかけ作り」という2つの側面があります。
▼あわせて読みたい
終活しない親との向き合い方|専門家がその理由と対策を解説
親にいきなり「終活して!」と言うと、ほぼ100%「縁起でもない!」と怒られます(笑)。まずは自分の話から入るのが、円滑なコミュニケーションのコツです。「実は僕(私)、自分の終活始めたんだよね」と切り出すことで、親も話しやすくなります。「実家を将来どうするか」といった不動産相続の話も、このタイミングで少しずつ始めるのがおすすめです。
本格的に準備する50代の終活でやること
50代は、多くの方が定年を意識し始める時期。子育ても一段落し、自分の人生を本格的に見つめ直す絶好の機会です。この年代の終活は、より具体的で実践的な内容になってきます。
「体力」と「判断力」が充実している50代のうちに、少し手間のかかる準備を進めておくのが理想的です。
- 財産目録の作成:預貯金、不動産、有価証券、保険、借金など、全ての財産をリストアップします。これが相続の基本情報になります。
- エンディングノートの作成:医療や介護の希望、葬儀の形式、大切な人へのメッセージなどを具体的に書き記しましょう。法的効力はありませんが、家族への道しるべになります。エンディングノートの書き方については、別の記事で詳しく解説しています。
- 遺言書の検討:財産の分け方で揉めそうな場合や、特定の誰かに財産を遺したい場合は、法的に有効な遺言書の作成を検討しましょう。特に不動産など分けにくい財産がある場合は重要です。
- 身辺整理の開始:長年溜め込んだ物を少しずつ整理(断捨離)し始めましょう。これは体力が必要なので、早めの着手が吉です。
日本の遺産相続、約3割が「争族」経験
大手信託銀行が実施した調査によると、遺産相続を経験した人のうち、約3人に1人が何らかのトラブルを経験したと回答しています。また、最高裁判所の司法統計によれば、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割に関する事件は、年間1万件を超えて推移しており、相続が家族間の争い(争族)に発展するケースは決して少なくないのが現状です。
(出典:最高裁判所 司法統計年報)
50代はまさに終活のゴールデンエイジ。この時期にしっかり準備しておけば、安心してセカンドライフを楽しめますよ。



ここまでで、終活が単なる「死の準備」ではなく、年代ごとに目的や内容が異なる「未来設計」であることがお分かりいただけたかと思います。特に40代、50代の方は、親のことと自分のことを同時に考える重要な時期。焦らず、まずは情報収集から始めてみてくださいね。
実践編!終活とは何かを具体的に知る


終活は何から始める?最初のステップ
さて、ここからはいよいよ実践編です。「やるべきなのはわかったけど、で、何から?」と思いますよね。僕がいつも最初におすすめしているのは、「エンディングノートを1冊買ってみる」ことです。
なぜなら、エンディングノートには終活で考えるべき項目が網羅されているからです。パラパラとページをめくるだけで、「あ、こんなことも考えておく必要があるんだ」と、やるべきことの全体像が見えてきます。
いきなり全部埋めようとしなくて大丈夫。「自分のプロフィール」とか「好きな食べ物」とか、書けるところから遊び感覚で書いてみるのが長続きのコツです。
最初のステップまとめ
- 本屋さんや文房具店で、ピンと来たエンディングノートを1冊選ぶ。
- まずは書けるところ、書きたいところから気軽に埋めてみる。
- 全体像を把握し、次に取り組むべきこと(財産整理、医療の希望など)を見つける。
この「とりあえず書いてみる」という具体的な活動が、漠然とした不安を解消する第一歩になりますよ。
終活で大切な10ことは何ですか?解説


エンディングノートで全体像を掴んだら、次は具体的な項目に取り組んでいきましょう。ここでは、特に「終活で大切な10こと」をリストアップして解説します。全部を一度にやる必要はありません。できそうなものから一つずつクリアしていきましょう。
| 項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 1. 医療・介護の希望 | 延命治療は希望するか、介護が必要になったらどこで過ごしたいか(自宅、施設など) |
| 2. 財産の整理・把握 | 預貯金、不動産、株、保険、ローンなどのプラスとマイナスの財産を一覧にする |
| 3. 相続の準備 | 誰に何を遺したいか考え、必要であれば遺言書を作成する。相続税が心配な方は相続税の基礎知識もチェック。 |
| 4. 身辺整理(断捨離) | 不要な物を処分する。思い出の品の整理。 |
| 5. デジタル遺品の整理 | PC・スマホのデータ、SNSアカウント、ネットバンクのID・パスワードの情報をまとめる(デジタル遺品管理の詳細はこちら) |
| 6. 葬儀・お墓の希望 | 葬儀の形式(一般葬、家族葬など)や規模、お墓をどうするか(継承、墓じまいなど) |
| 7. 連絡先リストの作成 | 自分の死後、連絡してほしい親戚や友人のリストを作成する |
| 8. ペットの世話 | 自分が飼えなくなった場合に、誰に託すか決めておく |
| 9. 大切な人へのメッセージ | 家族や友人への感謝の気持ちを書き残す |
| 10. これからの人生プラン | 残りの人生でやりたいこと、行きたい場所などをリストアップする |
こうして見ると、やることは結構多いですよね。だからこそ、元気なうちから少しずつ進めるのが大切なんです。
まずは簡単な終活の身辺整理から
リストを見て「うわっ、大変そう…」と思ったあなた。わかります。そんな時は、一番手軽に始められて、かつ効果を実感しやすい「身辺整理(断捨離)」から始めてみましょう。
部屋がスッキリすると、不思議と頭の中や心も整理されます。遺品整理は、遺された家族にとって時間的にも精神的にもかなりの負担になる作業です。これを生前のうちに自分でやっておくことは、最高の思いやりと言えるでしょう。



僕の経験上、一番処分に困るのが「趣味のコレクション」と「大量の写真」です。同じ趣味を持つ友人に譲ったり、写真はデータ化して整理したりと、元気なうちなら色々な選択肢がありますよ。「1年間使わなかった物は処分する」というマイルールを作るのもおすすめです。遺影に使う写真だけは、お気に入りを先に選んでおくと良いですね!
終活ノートに書き留めておくべき内容


前述の通り、終活の相棒とも言えるのが終活ノート(エンディングノート)です。これは、家族への「引き継ぎマニュアル」だと考えてください。ここに情報を一元化しておくことで、家族は手続きで迷うことが格段に減ります。
最低限、以下の項目は書き留めておきましょう。
エンディングノートの必須項目
- 自分の基本情報:本籍地、マイナンバー、保険証の保管場所など
- 資産について:銀行口座一覧(支店名まで)、保険会社、不動産の権利書など
- デジタル情報:スマホのロック解除方法、主要なサイトのID/パスワード
- 医療・介護の希望:かかりつけ医、延命治療の意思、アレルギー情報など
- 葬儀・お墓の希望:連絡してほしい葬儀社、遺影に使ってほしい写真など
- 連絡先リスト:訃報を伝えてほしい友人・知人の連絡先
ここで一つ注意点です。エンディングノートには法的な効力はありません。財産の分配などを法的に有効にしたい場合は、別途「遺言書」が必要です。エンディングノートはあくまで「お願い」や「情報共有」のツールだと理解しておきましょう。
法務局も推奨する「自筆証書遺言書保管制度」
エンディングノートに法的な効力はありませんが、財産について法的な意思を残したい場合、法務局が遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」の利用が推奨されています。
この制度を利用すると、遺言書の紛失・改ざんを防ぎ、家庭裁判所での検認も不要になるメリットがあります。終活の一環としてエンディングノートで想いを整理し、財産に関する部分は遺言書として法的に担保するという使い分けが、円満な相続への鍵となります。
(出典:法務省「自筆証書遺言書保管制度」)
終活でおひとりさまが準備すべきこと
2050年、日本の全世帯の44.3%が「おひとりさま」に
日本の国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、2050年には日本の総世帯数に占める単独世帯(一人暮らし)の割合は44.3%に達すると予測されています。
これは、約2.2世帯に1世帯が「おひとりさま」となる計算です。この社会的背景から、家族を頼ることが難しいケースが増え、元気なうちに自らの意思で準備を進める「おひとりさまの終活」の重要性が一層高まっています。
(出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」)
ご家族がいない、あるいは遠方にしかいない「おひとりさま」の場合、終活の重要性はさらに高まります。頼れる人がいないからこそ、元気なうちに公的な制度や専門家との繋がりを作っておくことが、安心して老後を過ごすための鍵になります。
特に考えておきたいのが、以下の3つの契約です。
- 身元保証契約:入院や施設入居の際に必要となる身元保証人を、NPO法人などに依頼する契約です。
- 任意後見契約:判断能力が低下した時に備え、財産管理や身上監護を任せる人をあらかじめ自分で選んでおく契約です。信頼できる友人や専門家と結びます。認知症対策として有効な家族信託も選択肢の一つです。
- 死後事務委任契約:亡くなった後の諸手続き(役所への届け出、葬儀、納骨、遺品整理など)を第三者に委任する契約です。これがなければ、役所が手続きを進めることになり、自分の希望は一切反映されません。
▼詳しくはこちら
死後事務委任とは?費用や手続きの流れをわかりやすく解説
おひとりさまの終活は、不安を解消するための「お守り」作りです。少し費用はかかりますが、将来の安心を手に入れるための投資だと考えて、ぜひ専門家への相談を検討してみてください。
参考情報サイト: 法務省「任意後見契約」
URL: https://www.moj.go.jp/MINJI/a03.html
終活に関するよくあるご質問FAQ
まとめ:より良い人生のための終活とは何か


ここまで、終活とは何か、その目的から具体的な進め方までお話ししてきました。色々な情報があって大変だったかもしれませんが、一番大切なのは「終活は未来の自分と大切な人のために行う、前向きでクリエイティブな活動である」ということです。この記事の要点を最後にまとめますね。
- 終活とは人生の終わりを考え、今をより良く生きるための活動
- 始める年齢に決まりはなく「思いたったが吉日」
- まずはエンディングノートを手に取り全体像を掴むのがおすすめ
- 医療や介護、財産、葬儀など10個の大切な項目を整理する
- 身辺整理は手軽に始められ効果も大きい第一歩
- 20代は人生設計、40代は親との対話、50代は具体的準備がテーマ
- おひとりさまは任意後見や死後事務委任契約の準備が重要
- 終活は一人で抱え込まず家族とコミュニケーションを取りながら進める
- ネガティブになりすぎず、楽しい計画も一緒に立てるのがコツ
- 終活の言い換えとしてライフエンディング・デザインという考え方もある
- 終活ノートには法的効力はなく遺言書とは別物
- デジタル遺品の整理は現代の終活に不可欠な要素
- 不安な点や専門的なことは専門家に相談する勇気も大切
- 終活を通じて自分の人生を振り返り価値観を再発見できる
- 最終的な目的は遺された家族の負担軽減と自分の人生の充実



最後までお読みいただき、ありがとうございます!終活は、決して一人で完璧にやる必要はありません。この記事をきっかけに、ご家族と話してみたり、エンディングノートを眺めてみたり、そんな小さな一歩を踏み出していただけたら、専門家としてこれほど嬉しいことはありません。あなたのこれからの人生が、より豊かで安心なものになるよう、心から応援しています!
▼あわせて読みたい関連記事▼