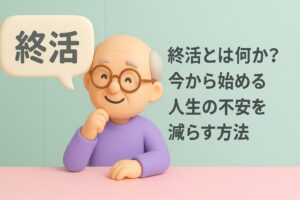こんにちは!終活・相続・不動産の専門家、カズです!僕がこの仕事を15年以上やってきて、最近とみに増えたご相談が「自分が死んだあと、誰がアレコレやってくれるの?」という切実な悩みです。
いやー、分かります!僕も考えますもん(笑)。この漠然とした不安を解消する一つの答えが、今回お話しする死後事務委任契約なんです。
でも、この契約、言葉は聞いたことあっても、具体的に遺言執行との違いや任意後見契約との違いが分からなかったり、死後事務委任契約の費用ってどうなの?トラブルはないの?なんて疑問も湧いてきますよね。
死後事務委任契約でできないことまで含めて、どこに頼むか、はたまた友人に頼めるのか、自治体は?預託金って何?手続きの流れは?など、気になる点は山積みだと思います。もしかしたら死後事務委任契約でお金がない、なんてケースもあるかもしれません。
大丈夫です!この記事を読めば、そんなモヤモヤが全部スッキリ晴れ渡りますよ。あなたの希望を叶えるための、最高の一歩を一緒に踏み出しましょう!
- 死後事務委任で「できること」と「できないこと」
- 遺言や任意後見契約との明確な違い
- 契約にかかる費用や注意すべきトラブル
- 自分に合った依頼先の選び方
 コンサルタント @KAZU
コンサルタント @KAZU最近「おひとりさま」という言葉も定着しましたが、ご自身の死後の手続きに不安を感じる方は本当に多いです。死後事務委任契約は、そんな不安を希望に変えるための、いわば「未来の自分への最高の贈り物」です。まずは基本をしっかり押さえることから始めましょう!
死後事務委任とは?基本と関連制度との違い


さて、まずはこの死後事務委任契約が「一体何者なのか?」という基本のキから見ていきましょう。これを押さえるだけで、他の制度との違いもスッと頭に入ってきますよ。
死後事務委任契約でできないこと
「よーし、これで死後のことは全部お任せだ!」と思いたいところですが、ちょっと待ってください!実は、死後事務委任契約にも守備範囲、つまり「できないこと」があるんです。これを理解しておくのが、トラブル回避の第一歩ですよ。
結論から言うと、財産の相続に関する手続きと、生きている間のサポートはできません。
【死後事務委任契約の守備範囲外】
- 預貯金の解約・払い戻し
- 不動産や自動車の名義変更
- 株式などの有価証券の売却・名義変更
- 生前の財産管理や見守り
- 医療行為への同意
僕が担当したお客様で、こんな方がいらっしゃいました。Aさんは「死後事務の契約をしたから、私が亡くなったら自宅マンションも売却してくれるはず」と思い込んでいたんです。しかし、これは完全に遺言や相続人の役割。危うくAさんの希望が叶えられないところでした。
あわせて読みたい
このように、財産に関わることは、別途遺言書の作成が必要になるんです。あくまでこの委任契約は、亡くなった後の「事務」を委任するもの、と覚えておいてくださいね。
遺言執行との違いをわかりやすく解説


「あれ?財産のことは遺言執行者がやるんじゃないの?」と思ったあなた、鋭いですね!そうなんです。ここで死後事務の受任者と遺言執行者の違いをはっきりさせておきましょう。一言で言うと、役割が「お金・財産」か「それ以外のお手続き」か、という違いです。
百聞は一見にしかず、ということで表にまとめてみました。
| 死後事務の受任者 | 遺言執行者 | |
|---|---|---|
| 主な役割 | 葬儀・納骨、役所手続き、遺品整理など | 遺言書の内容に沿った財産の分配・名義変更 |
| 得意分野 | 財産以外のあらゆる死後の事務手続き | 相続財産の管理と承継 |
| 根拠になるもの | 死後事務委任契約書 | 遺言書 |
| 具体例 | ・病院への支払い ・ペットの引継ぎ ・SNSの解約 | ・預貯金の解約 ・不動産の名義変更 ・株式の売却 |
僕の経験上、完璧な終活をされている方は、信頼できる専門家に死後事務と遺言執行の両方を依頼しています。こうすることで、財産とお手続きの両輪がガッチリ噛み合って、あなたの最後の希望がスムーズに実現するわけです。
あわせて読みたい
この二つの契約は、まさに終活界の最強タッグですね!
任意後見契約との違いも知っておこう
もう一つ、よく似た制度に「任意後見契約」があります。これは、将来、認知症などで判断能力が衰えてしまった場合に備える制度です。
一番の違いは、効力が発生するタイミングです。
- 任意後見契約 → 生きている間に判断能力が不十分になった時にスタート
- 死後事務委任契約 → 亡くなった後にスタート
つまり、任意後見契約はご本人の死亡によってその役割を終えるんですね。バトンタッチのように、生前は任意後見人が、死後は死後事務の受任者が、あなたをサポートするイメージです。
例えば、認知症対策として家族信託とあわせて任意後見契約を結び、さらに万が一に備えて死後事務委任契約も作成しておく。ここまでできれば、生きている間の財産管理から亡くなった後の事務まで、切れ目のないサポート体制が完成します。僕もお客様には、この「生前から死後までのフルサポートプラン」をよくご提案します。まさに盤石の布陣です!
参考情報サイト: 法務省「任意後見契約」
URL: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
死後事務委任契約の法的根拠は民法の「委任契約」
死後事務委任契約は、特定の法律で定められた制度ではありませんが、民法第643条に定められている「委任契約」の一種として法的に有効と解釈されています。
委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約です。
最高裁判所の判例でも、委任者の死亡によって委任契約は原則として終了するものの、契約の性質上、委任者の死亡後も存続させるべき特段の事情がある場合には、契約は終了しないと示されています。これにより、死後の事務手続きを委任する契約の有効性が認められています。
(出典:e-Gov法令検索 民法)
死後事務委任契約の手続きの流れ


「よし、契約の重要性は分かった!じゃあ、どうやって進めるの?」という方のために、手続きの流れを簡単にご紹介します。そんなに難しくないので安心してくださいね。
死後事務委任契約の簡単4ステップ
- 相談と内容の決定
まずは専門家などに相談し、どんな事務を、誰に、どこまで頼みたいのか希望を伝えます。葬儀の形式からSNSの扱いまで、わがままなくらい具体的に伝えるのがコツです! - 見積もりの確認
依頼内容に基づいて、費用や預託金の見積もりを出してもらいます。ここでしっかり内容と金額を確認しましょう。 - 契約書の作成
内容に納得できたら、契約書を作成します。後々のトラブルを避けるためにも、絶対に公正証書で作成することを僕カズは強くおすすめします。公証役場という場所で、公証人が作成してくれる信頼度MAXの書類です。 - 契約締結・保管
公正証書が完成したら、契約締結です。契約書の正本や謄本は、あなたと受任者がそれぞれ大切に保管します。これで、あなたの希望を託す準備は万端です!
死後事務委任契約はどこに頼むべきか
この契約、誰に頼むかが一番の悩みどころかもしれませんね。依頼先にはいくつかの選択肢があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
| 依頼先の候補 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 友人・知人 | 費用を抑えられる、気心が知れている | 専門知識がない、負担が大きい、相続人とトラブルになる可能性 |
| 弁護士・司法書士など | 法律知識が豊富、相続手続きも一任できる | 費用が比較的高額になる傾向 |
| 行政書士 | 書類作成のプロ、比較的費用を抑えられる | 紛争になった場合の代理はできない |
| NPO法人・一般社団法人 | 死後事務を専門に扱い経験豊富、比較的安価な場合も | 団体によってサービスや質が様々、信頼性の見極めが必要 |
僕カズの意見としては、「何を一番重視するか?」で選ぶのが良いと思います。費用を抑えたいなら信頼できる行政書士やNPO法人、相続まで含めて丸っとお任せしたいなら弁護士や司法書士、といった具合ですね。いくつかの候補に相談してみて、一番「この人なら信頼できる!」と思える担当者を見つけるのが成功の秘訣です。



ここまでで、死後事務委任契約の基本と、他の制度との違いがお分かりいただけたかと思います。大切なのは「自分に必要なのは何か」を見極めること。財産のことなら遺言、生前のことなら任意後見、そして死後の手続きなら死後事務。役割分担が大事です!
死後事務委任とは別に知るべき費用と注意点


さて、契約の全体像が見えてきたところで、後半戦はもっとディープな話、ズバリ「お金」と「注意点」についてです!ここをしっかり押さえておかないと、後で「こんなはずじゃなかった…」なんてことになりかねませんからね。
死後事務委任契約の費用と預託金について
気になる費用ですが、大きく分けて3つの要素で構成されています。
【費用の内訳】
- 契約書作成費用:専門家に契約書の作成を依頼する費用です。公正証書にする場合は、別途公証役場の手数料もかかります。(目安:10万円~30万円程度)
- 受任者への報酬:実際に死後、事務を行ってもらうための報酬です。依頼する事務の内容によって変動します。(目安:30万円~100万円以上)
- 実費:葬儀費用、納骨費用、医療費の精算、遺品整理費用など、手続きに実際にかかるお金です。
そして、これらの費用を支払うために重要になるのが「預託金」です。これは、死後事務に必要な費用を、あらかじめ受任者に預けておくお金のこと。
なぜなら、あなたが亡くなった直後、あなたの銀行口座は凍結されてしまい、誰もお金を引き出せなくなってしまうからです。預託金があれば、受任者が立て替えることなく、スムーズに葬儀や支払いの手続きを進められるというわけです。
あわせて読みたい
死後事務委任契約のデメリットは?


高まる死後事務の必要性:単独世帯の増加という事実
日本の国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、2020年に全世帯の38.1%だった「一人暮らし(単独世帯)」の割合は、2050年には44.3%にまで上昇すると予測されています。
特に65歳以上の一人暮らしは、2020年の約737万人から2050年には約1,084万人へと大幅に増加する見込みです。このように、頼れる親族がいない、あるいは親族に迷惑をかけたくないと考える方が増える社会背景が、死後事務委任契約への関心を高める大きな要因となっています。
どんな制度にも光と影があるもの。死後事務委任契約のデメリット、つまり注意点もしっかりお伝えしておきますね。
【知っておくべきデメリット】
- 費用がかかる:当然ですが、専門家に依頼すれば報酬が発生します。安心のための必要経費と考えるか、負担と考えるかは人それぞれです。
- 親族とのトラブルの可能性:ご自身の死後、何も知らされていない親族が突然現れた受任者を見て「誰だお前は!」となるケースは少なくありません。葬儀の形式などで意見が対立することも。
- 信頼できる受任者を見つける必要がある:大切な死後の希望を託すわけですから、万が一にも不誠実な相手に依頼しては大変です。事業者選びは慎重に行う必要があります。
特に親族とのトラブルは避けたいですよね。僕がいつもお客様にお願いしているのは、「契約を結んだら、必ずご親族(特に相続人になる方)に一言伝えておいてくださいね」ということです。一言あるだけで、死後のスムーズさが全く違ってきますから。
死後事務委任契約のトラブルを避けるには
デメリットを聞いて不安になったかもしれませんが、ご安心を。これらのトラブルは、事前の対策でほとんど防ぐことができます!
僕カズが伝授するトラブル回避の3か条!
- 契約内容は「これでもか!」というくらい具体的に!
「葬儀は〇〇葬儀社の家族葬プランで」「遺品はすべて処分。ただしアルバムだけは妹の〇〇へ」というように、誰が読んでも分かるように具体的に記しましょう。公正証書にするのは大前提です! - 親族への「根回し」を忘れずに!
契約の存在と内容を事前に伝えておきましょう。「こういう希望で、この人に頼んだから、よろしくね」と伝えておくだけでOKです。 - 受任者は複数の視点で厳しくチェック!
費用だけでなく、実績や担当者の人柄、契約内容の透明性など、総合的に判断して選びましょう。無料相談などを活用して、しっかり話を聞くのがおすすめです。
あわせて読みたい
死後事務委任契約は友人に頼める?


「仲の良い友人に頼めば、安く済むし安心かも」と考える気持ち、よく分かります。法律上、友人に依頼すること自体は全く問題ありません。
しかし、僕カズ個人の意見としては、あまりおすすめできません。
なぜなら、あなたが思っている以上に、死後の手続きは時間的にも精神的にも、そして時には金銭的にも大きな負担を強いるからです。役所を何度も往復したり、慣れない手続きに戸惑ったり、他の親族から問い合わせが来たり…。大切な友人に、そんな重荷を背負わせてしまっても良いものでしょうか?
もし、それでも友人に頼みたいのであれば、せめて負担が少ない最低限の事務に絞り、報酬や実費の精算方法を明確にした契約書(できれば公正証書)を作成することが、友情を壊さないための最低限のマナーだと僕は思います。
死後事務委任契約は自治体でも可能か
「公的な機関である自治体に頼めたら一番安心なのに」と思いますよね。残念ながら、現状、ほとんどの自治体で死後事務委任契約を直接結ぶことはできません。自治体はあくまで行政サービスを行う場所であり、個人の私的な契約の当事者にはなりにくいのです。
ただし、完全に無関係というわけではありません。多くの自治体では、高齢者支援の窓口や地域包括支援センターなどで、死後事務に関する相談に乗ってくれます。
そして、必要に応じて地域の社会福祉協議会や、信頼できる専門事業者を紹介してくれることもあります。まずは、お住まいの市区町村の窓口で「死後の手続きについて相談したい」と伝えてみるのが良いでしょう。
参考情報サイト: 厚生労働省「地域包括支援センター」
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/
死後事務委任契約でお金がない時の選択肢


「契約の必要性は分かった。でも、正直まとまったお金がない…」という切実な悩みも、僕がよくお受けする相談の一つです。
諦めるのはまだ早いです!いくつか方法はあります。
費用を抑えるための3つのアイデア
- 委任する事務を限定する
全ての事務を盛り込むのではなく、「遺体の引き取りと火葬、納骨」など、絶対に誰かにやってもらわなければならない最低限の事務に絞って契約することで、費用を大幅に抑えられます。 - NPO法人などを検討する
営利を目的としないNPO法人などの中には、比較的安価な料金プランを用意している団体もあります。いくつかの団体を比較検討してみる価値はあります。 - 遺言書の付言事項を活用する
これは契約ではありませんが、遺言書には「付言事項」として、法的な効力はないものの、家族へのメッセージや希望を書き残すことができます。ここに「葬儀は質素にお願いします」などと書いておくことで、間接的に希望を伝える方法です。
よくある質問(FAQ)死後事務委任とは
まとめ:自分に合った死後事務委任とは
最後に、この記事の要点をリスト形式でまとめました。これさえ押さえておけば、あなたに合った死後事務委任の形が見えてくるはずです!
- 死後事務委任契約は死後の手続きを生前に託すための契約
- おひとりさまや親族に負担をかけたくない人に特におすすめ
- 財産の相続や生前のサポートは範囲外なので注意が必要
- 遺言は財産、任意後見は生前、死後事務は死後の手続きと役割分担する
- 手続きは専門家と相談し公正証書で作成するのが鉄則
- 依頼先は友人、専門家、NPOなどがあり特徴を理解して選ぶ
- 友人への依頼は可能だが大きな負担をかける覚悟が必要
- 費用は契約作成料、報酬、実費の合計で預託金で準備するのが一般的
- デメリットは費用と親族トラブルの可能性
- トラブルは契約内容の具体化と親族への事前連絡で防げる
- 自治体は直接の依頼先ではないが相談窓口にはなる
- お金がない場合は委任内容を絞るなどの工夫で費用を抑えられる
- 自分の希望と状況に合わせて最適な契約内容と依頼先を見つけることが重要
- 不安があればまずは無料相談などを活用して専門家の話を聞いてみること
- 死後事務委任は未来の自分と大切な人への最高の思いやり



死後事務委任契約は、決してネガティブなものではなく、残りの人生を安心して、自分らしく輝かせるためのポジティブな「終活」です。この記事が、あなたの不安を少しでも軽くし、次の一歩を踏み出すきっかけになれば、専門家としてこれほど嬉しいことはありません!
▼あわせて読みたい関連記事▼