
「うちの親、何度言っても終活をしてくれない…」と頭を抱えていませんか?僕、終活・相続の専門家カズのもとにも、そんなお悩みが本当に多く寄せられます。親が元気なうちに準備してほしいのに、話をすると終活を嫌い、しまいには怒る始末。
特に80代の親や、頼れる家族が少ないおひとりさまの親だと、心配は尽きないですよね。親の終活がつらいと感じる20代の方も増えています。そもそも終活とは何か、終活をやらないとどうなるのか。
エンディングノートや終活ノートをどう活用し、終活で親に聞いておくべきことは何か。この、こじれがちな問題には、実は親が終活しない理由に寄り添うことで見える、解決の糸口があるんです。
- 親が終活を嫌がる本当の心理
- 親子関係を壊さずに終活の話を切り出すコツ
- 子が主導で進められる具体的な準備リスト
- もしもの時に備えて絶対に確認すべき重要事項
 コンサルタント @KAZU
コンサルタント @KAZU「親に終活の話をしたいけど、どうすれば…」そのお気持ち、痛いほどわかります。多くの方が、親を想うからこそ悩んでいます。大切なのは、一方的に「やって」と求めるのではなく、まず親の気持ちを理解しようとすること。この記事では、僕が15年以上の実務で見てきた実例を交え、具体的な一歩を踏み出すためのヒントをお伝えしますね。
終活しない親が抱える心理と向き合い方


そもそも「終活とは」何かを理解する
「終活」という言葉を聞くと、どんなイメージが浮かびますか?おそらく、お葬式やお墓の準備、遺言書といった、少し重たいテーマを想像される方が多いかもしれませんね。もちろんそれらも終活の一部ですが、本来はもっと広くてポジティブな活動なんです。
結論から言うと、終活とは「これからの人生をより良く生きるための準備」です。自分が亡くなった後のことだけを考えるのではなく、元気なうちに医療や介護の希望をまとめたり、財産を整理して老後の生活設計を立てたり、やりたいことリストを作って人生を楽しんだりすることも、立派な終活なんですよ。
▼もっと詳しく知りたい方へ▼
「終活」の基本から具体的な進め方までを網羅したこちらの記事も、ぜひあわせてお読みください。
>>終活とは何か?今から始める人生の不安を減らす方法
僕のお客様の中にも、「終活を始めたら、気持ちがスッキリして、やりたいことが明確になった!」とおっしゃる方がたくさんいます。つまり、終活は「死への準備」ではなく、「未来への希望の準備」と捉えることができるんです。この視点を持つだけで、親御さんへの伝え方も少し変わってくるかもしれませんね。
親が断固として終活しない理由とは


【事実】データで見る「終活」への意識と実態
大手生命保険会社であるメットライフ生命が2023年に実施した調査によると、「終活に関心がある」と答えた人は全体の約7割にのぼります。しかし、その一方で「まだ何も取り組めていない」という人も約半数を占めています。
特に、終活に取り組んでいない理由として、「何から始めればよいかわからない」「まだ早いと思っている」「時間や気持ちの余裕がない」が上位に挙げられています。このデータは、多くの人が終活の必要性を感じつつも、具体的な一歩を踏み出せずにいる現状を示しており、「うちの親だけではない」という客観的な事実を浮き彫りにしています。
(出典:メットライフ生命「老後に関する調査」)
「ウチの親に限って、どうしてこんなに頑ななんだろう…」と感じますよね。でも、実は終活をしたがらない親御さんには、いくつかの共通した心理的な理由があるんです。僕がこれまで見てきた中で、特に多い3つの理由をお話しします。
親が終活をしない主な3つの理由
- 自分の「死」と向き合いたくない
- 「子どもが何とかしてくれる」という期待
- 何から手をつけていいか分からない
まず一つ目は、シンプルに「自分の死と向き合うのが怖い、縁起でもない」という気持ちです。特にご高齢になると、友人や知人の訃報に接する機会が増え、死がよりリアルなものとして感じられます。だからこそ、あえて考えないようにしている、というケースは非常に多いです。
二つ目は、少し意外かもしれませんが、「子どもへの信頼」からくるものです。「いざとなったら、うちの子がしっかりやってくれるだろう」と、ある意味で安心してしまっているんですね。これは子としては嬉しいような、困るような、複雑な心境ですよね。
そして三つ目が、「やらなきゃいけないとは思うけど、何から始めればいいか分からない」という状態です。終活はやるべきことが多岐にわたるため、全体像が見えず、考えるだけで億劫になってしまうのです。この場合は、子どもが少し手伝ってあげるだけで、スムーズに進む可能性があります。
このように、ただ「面倒くさい」で片付けてしまうのではなく、親がどの理由でためらっているのかを想像してみることが、対話の第一歩になります。
体力や気力が課題となる80代の終活
特に親御さんが80代になると、終活には特有の難しさが出てきます。これは単なる気持ちの問題だけではなく、体力や気力、そして判断力の低下という現実的な課題が大きく関わってきます。
僕が担当したお客様で、85歳のお父様の遺品整理をされた方がいました。お父様は生前「片付けないと」と口では言っていましたが、結局手つかずのまま。残されたご家族が整理を始めると、一部屋片付けるだけで数日かかり、心身ともに疲れ果ててしまったそうです。
80代になると、若い頃のように一日中動き回ることはできません。書類を一枚一枚確認したり、重いものを運んだりする作業は、想像以上に体にこたえます。また、物を大切にする「もったいない精神」が根付いている世代なので、「捨てる」という行為自体に強い抵抗を感じる方も少なくありません。思い出の品であれば、なおさらです。
80代の終活で注意すべきこと
ご本人の体力や気力だけで進めるのは非常に困難です。無理強いはせず、まずは「大事な物の場所を教えてもらう」「一緒に少しだけ片付けてみる」など、ごく小さなステップから始めるのが成功の秘訣です。
「元気なうちに」と焦る気持ちは分かりますが、80代の親御さんに対しては、完璧を求めすぎないこと。「全部やらなくてもいいんだよ」という姿勢で、子の側がサポートしてあげる意識が何より大切になります。
なぜ親は終活を嫌い、感情的になるのか


終活の話をした途端、親の機嫌が悪くなったり、「縁起でもない!」と怒られたりした経験はありませんか?親が終活という言葉自体を「嫌い」と感じ、感情的になってしまうのには、実はちゃんとした背景があります。
最大の理由は、「終活=死ぬ準備」と直結させてしまうからです。子ども側は「もしもの時のために」と考えていますが、親の立場からすると、「お前は私がもうすぐ死ぬと思っているのか」と、突きつけられたように感じてしまうのです。これは、親のことが心配だからこその行動が、裏目に出てしまう典型的なパターンですね。
以前、あるご家庭で「お父さんの財産、どうなってるの?」とストレートに聞いた息子さんが、お父様を激怒させてしまったことがありました。「俺の金を当てにしてるのか!」と。息子さんにそんなつもりは全くなくても、聞き方一つで親子関係にヒビが入ってしまうこともあるんです。
また、「戦後の何もない時代を生き抜いてきた」という自負が強い世代は、自分のことは自分で決めてきたというプライドがあります。その方々にとって、子どもから「あれをしろ、これをしろ」と指示されるような形になるのは、面白くないと感じるのも無理はありません。
親が終活を嫌い、怒るのは、あなたへの不信感からではありません。自身の老いや死への不安、プライドが複雑に絡み合った結果なのです。その気持ちを理解した上で、言葉を選ぶ必要があります。
話を切り出して終活に怒る親への対処法
では、実際に終活の話を切り出して親を怒らせてしまった場合、どうすれば良いのでしょうか。ここで関係がこじれてしまうと、その後の協力が一切得られなくなる可能性もあるため、慎重な対応が求められます。
まず、一度引いて、冷却期間を置くことが重要です。感情的になっているときに、いくら正論をぶつけても火に油を注ぐだけ。「ごめん、急にこんな話しちゃって。嫌な気持ちにさせたね」と、まずは相手の感情を害したことについて謝り、その場は話を切り上げましょう。
そして、次にアプローチする際は、作戦を変えます。僕がよくアドバイスするのは、「主語を『親』から『私(子)』に変える」という方法です。
伝え方の変換例
- NG例:「お父さん、そろそろ終活しないとダメだよ」
- OK例:「もしお父さんに何かあった時、僕が手続きで困らないように、保険証券の場所だけ教えてくれると助かるんだけどな」
「あなたのため」ではなく、「私が助かるから」という伝え方をすると、親は「子どものために、それくらいならやってやるか」という気持ちになりやすいのです。これは驚くほど効果がありますよ。
他にも、「友人の親が亡くなった時に、通帳の場所が分からなくて大変だったらしい」といった第三者の話を持ち出したり、「自分自身の終活を始めたんだ」と自分の話から入るのも有効なテクニックです。決して焦らず、外堀から埋めていくようなイメージで、少しずつ距離を縮めていきましょう。
子の立場で感じる親の終活はつらい気持ち


ここまで親御さんの気持ちを中心に解説してきましたが、忘れてはならないのが、事を進めようとしている「お子さん自身の気持ち」です。親の終活と向き合うのは、実のところ、とてもつらい作業です。
親の老いを直視し、いつか来る「別れ」を具体的に考えなければなりません。思い出の品を整理すれば、楽しかった頃を思い出して手が止まってしまう。財産の話をすれば、どこか事務的で、お金の話ばかりしている自分に嫌気がさすこともあるでしょう。
僕自身も、父の終活を手伝ったときは、元気だった頃の父を思い出して、何度も感傷的な気持ちになりました。「なんでこんなことしなきゃいけないんだ」と、やり場のない怒りを感じたことも一度や二度ではありません。
この「つらい」という気持ちは、親を大切に想っているからこそ生まれる、ごく自然な感情です。決してあなたが冷たい人間だからではありません。むしろ、その気持ちがあるからこそ、親御さんも最終的には心を開いてくれるのだと思います。
一人で抱え込まず、兄弟姉妹や配偶者、あるいは僕のような専門家に話してみるだけでも、気持ちは軽くなります。つらいと感じている自分を、まずは自分で認めてあげてくださいね。



ここまで、親御さんが終活を嫌がる心理的な背景を中心に見てきました。大切なのは「なぜ?」を理解しようとする姿勢です。死への恐怖、プライド、子どもへの信頼、何をすべきか分からない戸惑い。これらの気持ちが複雑に絡み合っています。この点を踏まえ、次の章では具体的なアクションプランを見ていきましょう。
終活しない親のために子が知っておくべき事


結局、終活をやらないとどうなるのか
「まあ、なんとかなるだろう」と思っている方もいるかもしれませんが、親が何の準備もしないまま倒れたり亡くなったりすると、残された家族には想像以上の負担がかかります。具体的にどんなことが起こるのか、知っておくだけでも親御さんへの伝え方が変わるはずです。
終活準備がない場合の三大リスク
1. 手続き上のリスク:
預金通帳や印鑑、保険証券などが見つからず、口座の凍結解除や保険金の請求に膨大な時間がかかります。最悪の場合、存在するはずの資産に気づかず、権利を失うことも。僕のお客様の例では、貸金庫の存在を知らず、中身を確認するだけで半年以上かかったケースもありました。
2. 経済的なリスク:
葬儀費用や入院費の支払いがすぐにできない、遺品整理に高額な費用がかかる、といった問題が発生します。特に実家の片付けは数十万円から、場合によっては100万円以上かかることも珍しくありません。これらの費用を、一旦子どもが立て替えなければならなくなります。
3. 家族関係のリスク:
これが最も深刻かもしれません。親の希望が分からないため、葬儀の形式や不動産の相続などで兄弟姉妹の意見が対立し、揉めてしまうケースです。「争族」という言葉があるように、親が亡くなった後に家族の絆が壊れてしまうことは、本当に悲しいことです。
【事実】相続トラブルは他人事ではない?司法統計データ
最高裁判所が公表している司法統計によると、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割に関する事件(調停および審判)の件数は、年間1万件以上で推移しており、決して他人事ではありません。
特に注目すべきは、争いになる遺産総額です。最も多いのは「1,000万円超5,000万円以下」のケースで、全体の約43%を占めています。
これは、いわゆる「普通のご家庭」でも、相続をきっかけに深刻なトラブルに発展する可能性が十分にあることを示しています。「うちは財産が多くないから大丈夫」という思い込みが、最も危険なリスクとなり得るのです。
(出典:最高裁判所 司法統計年報(令和4年度))
これらのリスクは、決して大げさな話ではありません。「親に穏やかな老後を送ってほしいし、自分たち家族も揉めたくない」そのために準備が必要なんだ、という視点で伝えることが大切です。特に相続で揉めないためには、法的な効力を持つ遺言書が非常に有効です。
▼遺言書の準備はこちら▼
遺言書があれば防げるトラブルはたくさんあります。正しい書き方をこちらの記事で確認しておきましょう。
>>初心者でも安心!遺言書書き方の完全手順
終活で親に聞いておくべきことは何か


親御さんが終活に協力的ではない場合、全てを網羅しようとせず、「これだけは絶対に聞いておきたい」という重要事項に絞って確認するのが現実的です。完璧を目指さないことが、成功のコツですよ。
僕が「最低限これだけは!」とアドバイスしているのは、大きく分けて「お金・財産のこと」と「もしもの時の希望」の2つです。
最低限聞いておくべきことリスト
【お金・財産に関すること】
- 銀行口座と証券口座:どの金融機関に口座があるか。ネット銀行も忘れずに。
- 保険:生命保険や医療保険に加入しているか。会社名だけでもOK。
- 不動産:自宅や土地など、所有している不動産の一覧。
- 年金:年金手帳や証書の保管場所。
- ローンや借金:プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も重要。
【もしもの時の希望に関すること】
- 医療・介護:延命治療を望むか、どんな介護を受けたいか。
- 葬儀・お墓:呼びたい友人、希望の形式、お墓の場所と管理について。特にお墓は、近年墓じまいを検討するご家庭も増えています。
- 連絡先:緊急時に連絡してほしい親戚や友人のリスト。
暗証番号や具体的な金額まで聞こうとすると、警戒されてしまいます。まずは「何が」「どこにあるか」を把握することを目標にしましょう。「書類を一か所にまとめておいてくれるだけで、すごく助かるんだ」とお願いするのが効果的です。
終活ノートとエンディングノートの活用法
親に聞いておくべきことを確認するツールとして、非常に役立つのが「終活ノート」や「エンディングノート」です。これらは似ていますが、少しニュアンスが異なります。
| 終活ノート | エンディングノート | |
|---|---|---|
| 主な目的 | 自分自身の人生の棚卸しや、これからの生活設計など、より広い意味での活動記録。 | 家族に残す情報(資産、医療、葬儀など)を整理し、伝えることに特化。 |
| 特徴 | 自由度が高く、日記や備忘録のような使い方ができる。 | 項目が決まっており、それに沿って書けば必要な情報が網羅できる。 |
| 法的効力 | なし | なし(遺言書とは異なる) |
親御さんが書くことに抵抗があるなら、前述の通り、子どもがインタビュアーになって代わりに書き留めてあげるのがおすすめです。「僕が代わりに書くから、教えてくれる?」と提案してみましょう。
この時のポイントは、一度に全てを完成させようとしないこと。「今日は銀行のことだけ教えて」「今度、お友達のこと聞かせて」というように、テーマを分けて少しずつ進めるのが長続きの秘訣です。完成したノートは、親の希望をまとめた「家族のお守り」のような存在になりますよ。
エンディングノートの具体的な項目や、親子で楽しく書くためのコツは、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください!
>>エンディングノート書き方完全ガイド|家族に伝わる残し方
終活はおひとりさまの親にこそ必要
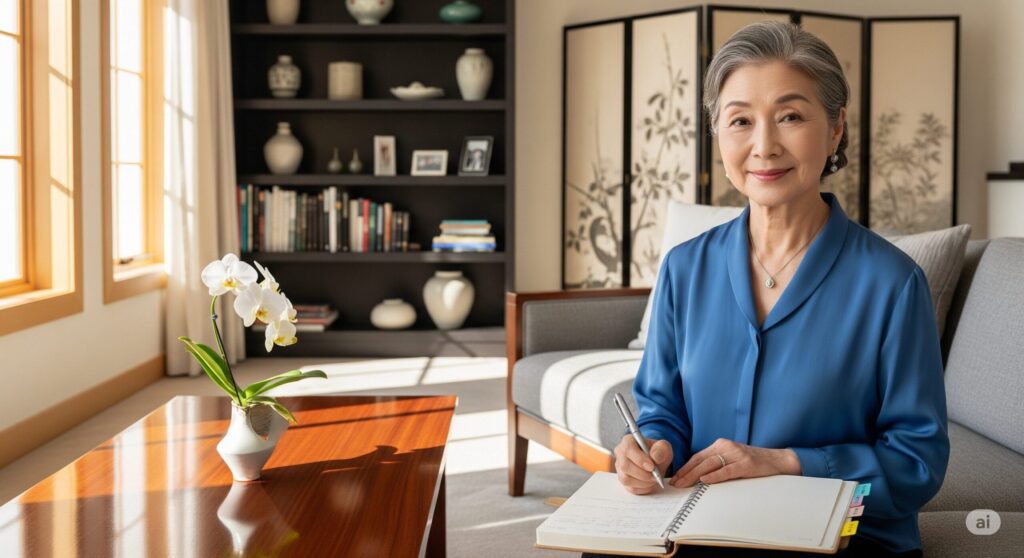
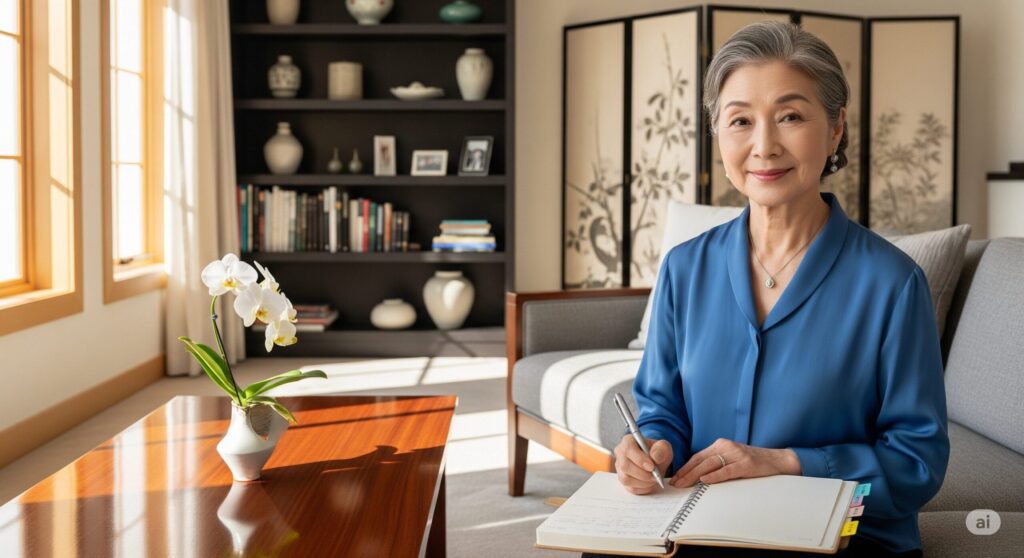
【事実】高齢者の判断能力と認知症の現状
内閣府が公表している「令和5年版高齢社会白書」によると、2020年時点で65歳以上の高齢者の認知症有病率は16.7%、つまり約6人に1人が認知症であると推計されています。さらに、2025年にはこの割合が約5人に1人に増加すると見込まれています。
一度認知症と診断されると、ご本人の意思で預金口座を解約したり、不動産を売却したり、遺言書を作成したりといった法律行為が原則としてできなくなります。これは、終活の準備が「元気で判断能力があるうち」にしかできないという厳しい現実を示しています。
(出典:内閣府「令和5年版高齢社会白書」)
配偶者に先立たれたり、お子さんがいなかったり、あるいは遠方に住んでいるなど、いわゆる「おひとりさま」の親御さんの場合、終活の重要性はさらに高まります。
頼れる人が身近にいないため、いざという時に様々な手続きや判断をしてくれる人がいません。例えば、急な入院で保証人が必要になったり、認知症などで判断能力が低下した際の財産管理が大きな問題となります。
僕が担当した例では、おひとりで暮らしていた80代の女性が認知症になり、悪質な訪問販売で高額な商品を次々と契約させられていた、というケースがありました。甥御さんが気づいた時には、預金の多くが失われていました。
おひとりさまの終活で考えておきたいこと
- 財産管理:判断能力が低下した場合に備え、信頼できる人に財産管理を託す「家族信託」や「任意後見制度」の利用を検討する。
- 死後事務委任契約:亡くなった後の葬儀、役所への届け出、遺品整理などを生前に依頼しておく死後事務委任契約も有効です。
- 見守りサービス:緊急時に駆けつけてくれるサービスや、定期的に連絡をくれるサービス。
これらの準備は、ご本人が元気で判断能力があるうちしかできません。「あなたが心配だから」と、子の立場から正直な気持ちを伝え、一緒に情報収集から始めてみることが大切です。おひとりさまだからこそ、早めの準備が将来の安心に直結します。
終活を20代から考えることの重要性
「終活なんて、まだまだ先の話」と思っている20代の方も多いかもしれません。しかし、実は若いうちから終活を意識することには、大きなメリットがあるんです。
これは「死の準備」というより、「人生をデザインする」という視点です。20代のうちから終活を考えると、以下の2つの良いことがあります。
一つは、「親世代の終活をスムーズに進められる」こと。若いうちから終活に関する知識を持っていれば、いざ親の終活が必要になった時に、慌てず的確なサポートができます。今回解説してきたような親の気持ちも理解しやすく、冷静な対話ができるはずです。
そしてもう一つは、「自分自身の人生設計に役立つ」ことです。エンディングノートを書くつもりで、「自分の大切なものは何か」「どんな人生を送りたいか」「どんな人と関わっていきたいか」を考えてみてください。それは、キャリアプランやライフプランを考える上で、強力な指針になります。自分がどう生きたいかが見えれば、日々の選択も変わってきます。
僕自身、この仕事を始めた20代の頃に自分のエンディングノートを書いたことが、その後の人生設計に大きな影響を与えました。若いうちの終活は、いわば「人生の羅針盤」を手に入れるようなもの。ぜひ、軽い気持ちで始めてみてはいかがでしょうか。
よくある質問 (FAQ)
根気よく進める終活しない親との準備


- 終活しない親との向き合いは長期戦と心得る
- 親が終活を嫌がる心理的な背景をまず理解する
- 「死の準備」ではなく「より良く生きる準備」と捉え直す
- 80代の親には体力や気力の面で配慮が必要不可欠
- 終活の話で親が怒るのは不安やプライドの裏返し
- 子のつらい気持ちも自然な感情だと受け止める
- 準備がないと手続き・経済・家族関係の三大リスクがある
- 全てを聞き出そうとせず重要事項に絞って確認する
- 「何が」「どこにあるか」の把握を最初の目標にする
- 親子でエンディングノートを少しずつ埋めていく
- おひとりさまの親には認知症対策や死後事務の準備が特に重要
- 20代から終活を意識すると自分と親、双方の人生に役立つ
- 完璧を目指さず小さな一歩を褒める姿勢が大切
- 子の「助かるから」という伝え方が親の心を動かす鍵
- 困った時は一人で抱えず専門家に相談する選択肢も持つ



ここまでお読みいただき、ありがとうございます。終活しない親との関係は、本当に根気がいります。でも、この記事で紹介したように、親の気持ちを理解し、伝え方を少し変えるだけで、状況は好転する可能性があります。大切なのは、焦らず、諦めず、そして何よりあなた自身が一人で抱え込まないこと。今日の情報が、あなたの次の一歩に繋がれば、これほど嬉しいことはありません。
▼あわせて読みたい関連記事▼












