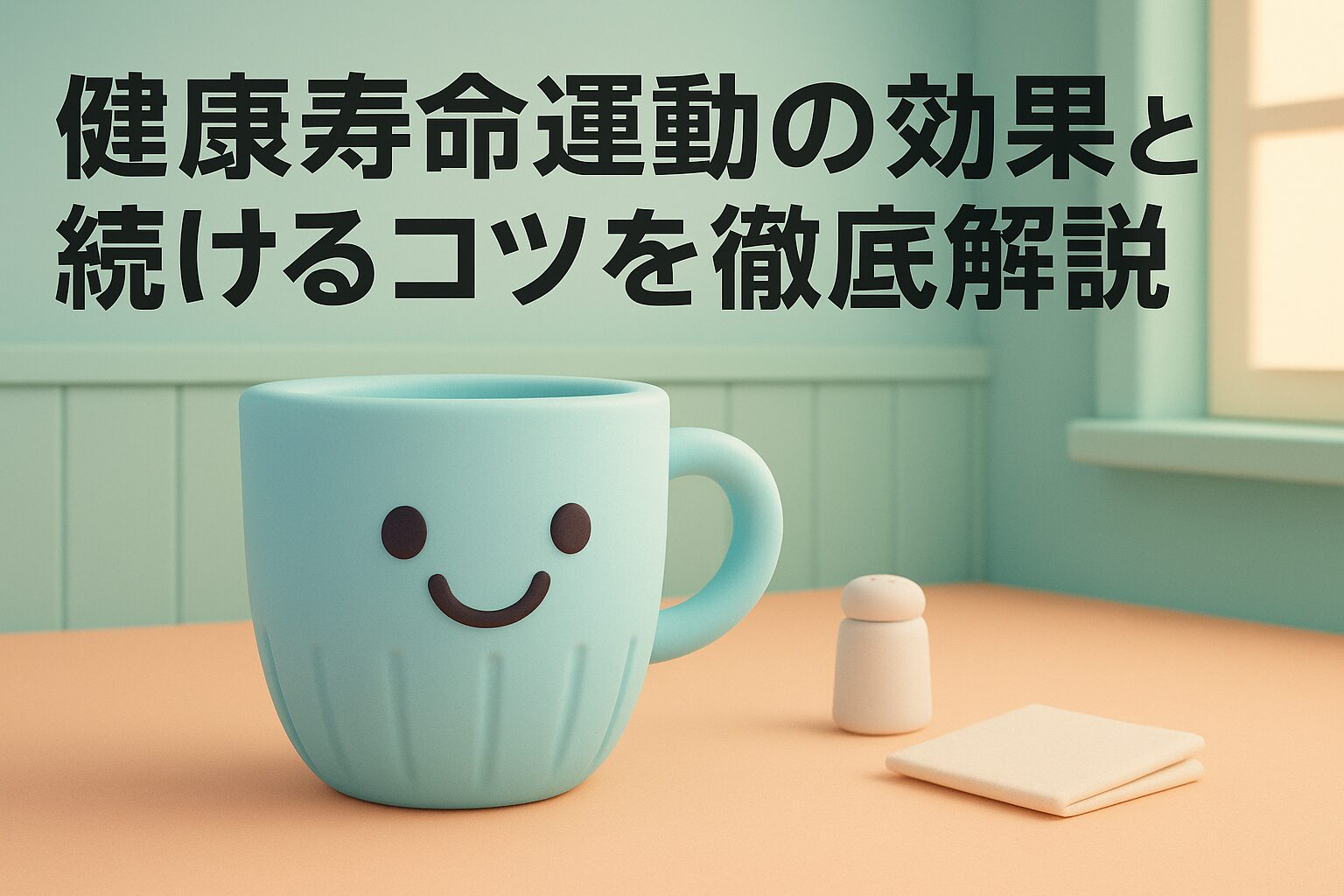
こんにちは!終活・相続の専門家カズです。最近、「老後のために資産準備を…」というご相談を受ける中で、つくづく思うことがあるんです。「お金も大事だけど、それ以上に元気な体が一番の財産だな」って。
そこで今回は、健康寿命と運動の関係について、最新研究や科学的根拠を交えつつ、僕のお客様の事例なんかも思い出しながら、誰にでも分かりやすくお話ししますね。
高齢者の方が運動しないとどうなるかのリスク解説から、自宅でできる運動や初心者向けの筋トレメニュー、食事との組み合わせまで、データやグラフ付きでご紹介します。
長生きする運動トップ3や寿命が1番伸びるスポーツの種目別比較、自治体の取り組み事例集まで網羅しているので、この記事を読めば、きっと「今日からやってみよう!」と思えるはずですよ!
- 科学的データに基づいた健康寿命と運動の重要性
- 初心者でも自宅で簡単に始められる運動メニュー
- 運動効果を最大化する食事との組み合わせ方
- いつまでも元気でいるための具体的なアクションプラン
💡 まずは将来のお金の不安から解消しませんか?
元気な体とお金の準備は、いわば車の両輪です。老後に必要なお金の計算方法や、今からできる準備について詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。老後までに必要なお金はいくら?不安を解消する徹底ガイド
 コンサルタント @KAZU
コンサルタント @KAZU終活のご相談では、ご自身の希望を叶えるために「元気でいること」がいかに大切かを痛感します。この記事では、ただ長生きするだけでなく、人生の終わりまで自分らしく活動的に過ごすための「健康寿命運動」に焦点を当てました。未来の自分のために、今日からできる小さな一歩を一緒に見つけていきましょう!
健康寿命運動の重要性とは?科学的根拠を


高齢者が運動しないとどうなる?リスクを解説
「年を取ったら、家でゆっくりしているのが一番」なんて思っていませんか?実はそれ、ちょっと危険なサインかもしれません。僕が担当したお客様で、数年前までは旅行が趣味だった方がいらっしゃいました。しかし、定年退職を機にパッタリと外出の機会が減ってしまったんです。
すると、わずか1年ほどで足腰が弱り、今では近所の買い物も億劫になってしまった、と寂しそうに話していました。
このように、高齢者の方が運動しない生活を続けると、様々なリスクが高まる可能性があります。専門的には「フレイル」や「サルコペニア」と呼ばれる状態に陥りやすくなると言われています。
運動不足が招く可能性のある主なリスク
- 筋力・身体機能の低下(サルコペニア):筋肉量が減少し、転倒や骨折のリスクが高まります。一度転んでしまうと、それがきっかけで寝たきりになるケースも少なくありません。
- 生活習慣病のリスク増大:肥満、高血圧、糖尿病などのリスクが高まるという調査結果があります。健康診断の結果が年々悪化している方は要注意です。
- 認知機能の低下:体を動かさないことは、脳への刺激を減らすことにも繋がります。認知症予防の観点からも、適度な運動習慣は必要と考えられています。
- 精神的な落ち込み:活動量が減ると、人との交流も少なくなりがちです。社会的な孤立や気分の落ち込みに繋がり、生活の質(QOL)そのものが低下してしまいます。
言ってしまえば、運動をやめることは、元気で自立した生活を自ら手放してしまうようなもの。終活をいつから始めるかを考える上でも、ご自身の希望を伝えたり、必要な手続きを進めたりするには、まず心身の健康が土台になりますからね。
健康寿命と運動の関係を示す最新研究


「運動が大事なのは分かったけど、本当にそんなに効果があるの?」と思いますよね。もちろんです!近年、健康寿命と運動の関係については、世界中で様々な調査や研究が進んでおり、その重要性を示すデータが次々と報告されています。
例えば、厚生労働省も「健康づくりのための身体活動基準2013」の中で、高齢者の身体活動を推奨しています。これは、多くの研究データを基に、運動習慣が健康寿命の延伸に寄与するという結論に至っているからです。
最新研究から見えてきたポイント
最近の研究では、単に運動の「量」だけでなく、「質」や「種類」も注目されています。例えば、有酸素運動だけでなく、筋力トレーニングを組み合わせることで、より効果的に身体機能の低下を防げるという報告が多くあります。
また、「座りっぱなしの時間」が長いこと自体が独立した健康リスクであることも分かってきました。30分に一度は立ち上がって少し歩くだけでも、健康への意識は大きく変わるかもしれませんね。
僕のお客様でも、80代で実家の不動産相続の相談に来られた方がいらっしゃいましたが、週に2回ジムに通っていると話していて、本当にお元気でした。その方は、「将来子供に迷惑をかけないためにも、自分の足でしっかり歩けることが一番の終活」とおっしゃっていて、まさにその通りだと感銘を受けた経験があります。
参考情報サイト: 厚生労働省「e-ヘルスネット」
URL: https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/
健康寿命と運動のデータをグラフ付きで解説
健康寿命の最新データ(令和元年)
厚生労働省が公表した令和元年のデータによると、日本人の平均寿命と健康寿命は以下の通りです。
- 男性:平均寿命 81.41歳 / 健康寿命 72.68歳 (その差 8.73年)
- 女性:平均寿命 87.45歳 / 健康寿命 75.38歳 (その差 12.06年)
この「差」の期間は、日常生活に何らかの制限を要する、つまり介護などが必要になる可能性がある期間を示しています。運動習慣は、この差を縮めるための最も有効な手段の一つです。
言葉で説明するよりも、データを見ると一目瞭然かもしれません。ここでは、運動習慣と健康寿命の関係を示す一般的なデータについてお話しします。
厚生労働省の調査によると、平均寿命と健康寿命の間には、男性で約9年、女性で約12年もの差があります。この差の期間は、何かしらの介護や支援を必要とする可能性がある時間ということになります



この「9年」や「12年」という時間を、いかに短くして、ピンピンコロリを目指すか。これが健康寿命を考える上での大きなテーマなんですよね。
そして、様々な調査データを分析すると、運動習慣がある人とない人では、この健康寿命に明確な差が出ることが示唆されています。例えば、1日に歩く歩数と要介護認定のリスクを比較したグラフを見ると、歩数が多い人ほど要介護リスクが低い傾向がはっきりと見て取れます。
データから読み解くポイント
横軸に「1日の平均歩数」、縦軸に「要介護になるリスク」をとったグラフをイメージしてみてください。グラフの線は、歩数が増えるにつれて右肩下がりに下がっていきます。つまり、身体を動かす活動量が増えれば増えるほど、将来介護が必要になる可能性を下げられる、というわけです。
もちろん、ただやみくもに歩けば良いというわけではありません。しかし、データは「身体を動かす習慣」が、将来の健康な生活のための非常に有効な「投資」であることを示してくれています。
科学的根拠に基づく健康寿命への運動効果


運動が健康寿命に良い影響を与える背景には、しっかりとした科学的な根拠(エビデンス)があります。気分的なものだけでなく、身体の中で実際にポジティブな変化が起きているんです。
主に、運動による効果は以下の3つに大別できます。
1.身体的な機能の維持・向上
これは最もイメージしやすい効果ですね。運動をすると、まず筋肉量の減少(サルコペニア)を防ぎ、筋力を維持できます。特に下半身の筋肉は、歩行能力やバランス能力に直結するため非常に重要です。また、心肺機能も向上し、疲れにくい体になります。骨に適度な刺激が加わることで、骨密度の低下、つまり骨粗しょう症の予防にも繋がるとされています。
2.生活習慣病の予防・改善
ウォーキングなどの有酸素運動は、血中の糖や脂肪をエネルギーとして消費します。そのため、血糖値や血圧、中性脂肪の数値を安定させる効果が期待できるのです。これにより、糖尿病や高血圧、脂質異常症といった生活習慣病の予防・改善に繋がります。これらの病気は、がんや心疾患、脳卒中といった、より深刻な病気の引き金になることもあるため、運動による予防は非常に重要です。
3.認知機能・精神面の安定
運動をすると、脳の血流が良くなり、神経細胞の活動が活発になります。これは、認知機能の維持・向上に良い影響を与えると多くの研究で報告されています。また、運動は「セロトニン」といった、気分を安定させる脳内物質の分泌を促すとも言われています。外に出て体を動かすこと自体が気分転換になり、ストレス解消やうつ病の予防にも効果的です。相続の準備など、少し頭を使う作業をする前にも、軽い散歩はおすすめですよ。頭がスッキリして、良いアイデアが浮かぶかもしれません。
✍️ 体も頭もスッキリしたら、想いをノートに綴ってみませんか?
元気なうちに自分の考えや希望をまとめておくことは、残される家族への最高の贈り物になります。エンディングノートの書き方やポイントを解説した記事もご用意しています。エンディングノート書き方完全ガイド|家族に伝わる残し方
健康寿命を延ばす本当の要因ランキング
「健康寿命を延ばすには、結局何が一番大事なの?」という疑問にお答えするために、様々な研究で重要だとされている要因を、僕なりにランキング形式でまとめてみました。終活・相続の専門家として多くの方の人生に触れてきた経験も踏まえています。
| 順位 | 要因 | 重要性のポイント |
|---|---|---|
| 第1位 | 運動習慣 | 身体機能の維持、生活習慣病予防、認知機能維持など、心身両面に直接的な効果があるため、最も基本的かつ重要な要因と言えます。 |
| 第2位 | バランスの取れた食事 | 体を作る資本であり、運動の効果を最大限に引き出すためにも不可欠です。特に高齢期は、筋肉の材料となるタンパク質の摂取が重要になります。 |
| 第3位 | 社会とのつながり(社会参加) | 友人との交流、趣味のサークル、ボランティア活動など、社会的な役割を持つことは、精神的なハリや生きがいに繋がり、認知症予防にも効果的です。(シニアの習い事も人気です) |
| 第4位 | 知的活動の習慣 | 読書、囲碁や将棋、新しいことへの挑戦など、脳を積極的に使う習慣は、認知機能の維持に役立ちます。 |
| 第5位 | 適切な休養と睡眠 | 活動と休養のバランスが大切です。質の良い睡眠は、心身の疲労を回復させ、翌日の活動の質を高めます。 |
このように見ると、やはり運動習慣が土台となっていることが分かります。いくら社会とのつながりを持とうとしても、外に出るための体力がなければ難しいですよね。食事も、活動してお腹が空かなければ美味しく食べられません。全ての健康要因は、互いに密接に関係しているのです。
健康寿命を伸ばす食事と運動の組み合わせ


運動の効果を最大限に引き出すためには、食事がめちゃくちゃ重要です。車で言えば、運動が「エンジン」で、食事が「ガソリン」のようなもの。どちらが欠けても、元気に走り続けることはできません。
特に意識してほしいのが、運動とタンパク質の組み合わせです。
ゴールデンコンビ:運動 × タンパク質
運動をすると、筋肉は少しだけ傷つきます。それが回復する過程で、以前よりも強い筋肉が作られるのですが、この回復に必要不可欠な材料がタンパク質です。せっかく筋トレをしても、材料が不足していては、筋肉は効率よく作られません。
- 摂取のタイミング:運動後30分~1時間以内が、タンパク質摂取のゴールデンタイムと言われています。
- おすすめの食品:肉、魚、卵、大豆製品(豆腐、納豆)、乳製品(牛乳、ヨーグルト)など。手軽に摂れるプロテインドリンクやサラダチキンも便利です。
僕のお客様で、毎日1時間のウォーキングを日課にしている方がいるのですが、始めた当初はあまり効果を実感できなかったそうです。そこで僕が「運動の後に、牛乳かヨーグルトを摂ってみてはどうですか?」とアドバイスしたところ、数ヶ月後には「前より疲れにくくなったし、歩くのが楽になった!」と嬉しい報告をくれました。
もちろん、タンパク質だけでなく、エネルギー源となる炭水化物や、体の調子を整えるビタミン・ミネラルもバランス良く摂ることが大前提です。一日三食、様々な食材を彩り豊かに食べることを心がけるのが、健康な体作りの基本ですね。
高齢者のフレイル予防に必要なたんぱく質量
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、65歳以上の高齢者のフレイル予防を目的として、摂取すべきたんぱく質の目標量が示されています。
- 目標量:1日に摂取する総エネルギーのうち15~20%をたんぱく質から摂ること。
- 体重あたりの推奨量:少なくとも体重1kgあたり1.0g以上の摂取が推奨されています。 (例: 体重60kgなら60g以上)
運動で筋肉に刺激を与えた後、その材料となるたんぱく質をしっかり補給することが、筋力を維持し、健康寿命を延ばす上で科学的に重要であるとされています。



ここまで、なぜ運動が大切なのか、その科学的な理由をお話ししてきました。データや理屈が分かると、やる気も湧いてきますよね。大切なのは「知っている」だけでなく「やってみる」こと。次のセクションでは、今日からすぐに始められる具体的な運動メニューをご紹介しますので、ぜひ一緒に体を動かしてみましょう!
今日から始める!具体的な健康寿命運動メニュー


長生きする運動トップ3を種目別に比較
「運動って言っても、何をすればいいの?」という方のために、手軽に始められて効果が高いとされる運動をトップ3形式でご紹介します。それぞれの特徴を比較してみましょう。
| 第1位:ウォーキング | 第2位:ラジオ体操 | 第3位:水中運動 | |
|---|---|---|---|
| 手軽さ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
| 安全性 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 効果 | 全身の持久力、心肺機能向上 | 全身の筋肉、関節を万遍なく動かす | 膝や腰への負担が少ない、心肺機能向上 |
| ポイント | 少し息が弾む程度の速さで、腕を振って歩く | 一つ一つの動きを大きく、正確に行う | 水の抵抗を利用してゆっくり動く |
第1位は、やはり「ウォーキング」です。特別な道具も場所も必要なく、思い立ったらすぐに始められるのが最大の魅力。日常生活の中に組み込みやすいのもポイントです。「一駅手前で降りて歩く」「買い物は少し遠回りする」といった工夫で、無理なく運動時間を確保できます。
第2位の「ラジオ体操」も侮れません。約3分という短い時間の中に、有酸素運動、筋トレ、ストレッチの要素が凝縮されており、非常に効率の良い運動です。
第3位の「水中運動」は、膝や腰に痛みがある方に特におすすめ。浮力のおかげで関節への負担が少なく、水の抵抗が適度な負荷になるため、効率的に筋力アップが図れます。お近くに市民プールなどがあれば、ぜひ試してみてください。
自宅でできる高齢者向け初心者運動メニュー


「外に出るのはちょっと…」という方でも大丈夫。自宅のリビングで、テレビを見ながらでもできる簡単な初心者向け運動メニューをご紹介します。大切なのは、無理せず、毎日少しずつでも続けることです。



僕もデスクワークが多いので、意識してやっていますよ!特にスクワットは、下半身全体の筋肉に効くのでおすすめです。
1.イスを使ったスクワット(5回~10回)
下半身の筋力を総合的に鍛える「キング・オブ・トレーニング」です。
- 安定したイスの前に、足を肩幅に開いて立ちます。
- お尻を後ろに引くように、ゆっくりと腰を下ろします。イスにお尻が軽く触れるくらいまで。
- ゆっくりと元の姿勢に戻ります。膝がつま先より前に出ないように注意しましょう。
2.かかと上げ(10回~20回)
ふくらはぎの筋肉を鍛え、歩行の安定や血行促進に繋がります。
- イスの背もたれなどに手を添えて、まっすぐ立ちます。
- かかとをゆっくりと持ち上げ、つま先立ちになります。
- ゆっくりとかかとを下ろします。
3.片足立ち(左右 各1分)
バランス能力を高め、転倒予防に非常に効果的です。
- 転倒しないように、必ず壁や机の近くで行います。
- 片足を床から少し浮かせ、1分間キープします。
- 反対の足も同様に行います。ふらつく場合は、無理せず短い時間から始めましょう。
運動を行う際の注意点
痛みを感じたらすぐに中止してください。また、持病がある方は、事前にかかりつけ医に相談してから始めるようにしましょう。
健康寿命を伸ばすための簡単筋トレメニュー
前述の初心者向けメニューに慣れてきたら、もう少しだけ負荷をかけた筋トレにも挑戦してみましょう。筋肉は、年齢に関係なく、鍛えれば必ず応えてくれます。
ここで紹介する筋トレは、特に「抗重力筋」と呼ばれる、地球の重力に対して姿勢を保つために働く筋肉をターゲットにしています。この筋肉が衰えると、猫背になったり、つまずきやすくなったりします。
1.太もも上げ(左右交互に10回ずつ)
お腹の奥にある「腸腰筋」という、足を前に持ち上げる筋肉を鍛えます。
- イスに深く腰掛け、背筋を伸ばします。
- 片方の膝を、胸に近づけるようにゆっくりと持ち上げます。
- 限界まで上げたら、ゆっくりと下ろします。反対の足も同様に行います。
2.ブリッジ(10回)
お尻の「大殿筋」や背中の「脊柱起立筋」など、体の裏側全体を鍛えます。
- 仰向けに寝て、両膝を90度くらいに立てます。足は腰幅に開きます。
- お尻をゆっくりと持ち上げ、肩から膝までが一直線になるようにします。
- その状態で数秒キープし、ゆっくりとお尻を下ろします。
これらの筋トレを日々の生活に取り入れることで、階段の上り下りが楽になったり、姿勢が良くなったりといった効果が期待できます。遺言書の作成など、集中力が必要な相続準備も、良い姿勢で行うとはかどりますよ。
自治体も推進!健康寿命を延ばす取り組み事例集


「一人で運動を続けるのは自信がない…」という方もご安心ください。今、全国の多くの自治体が、住民の健康寿命を延ばすための様々な取り組みに力を入れています。
自治体の取り組み事例
- 介護予防体操教室:地域の公民館やコミュニティセンターで、専門の指導員による体操教室が定期的に開催されています。同じ目的を持つ仲間と一緒に楽しく運動できます。
- ウォーキングイベント:地域のウォーキングマップを作成・配布したり、スタンプラリー形式のイベントを開催したりして、住民が楽しく歩くきっかけを提供しています。
- 健康ポイント制度:運動教室への参加や健康診断の受診などでポイントが貯まり、商品券などと交換できる制度です。モチベーション維持に繋がりますね。
これらの情報は、お住まいの市町村の広報誌やホームページで確認できます。「(お住まいの市町村名) 介護予防教室」や「(お住まいの市町村名) 健康づくり」といったキーワードで検索してみてください。
専門家として様々なご家庭の家族信託や相続のご相談を受けていると、親御さんがこうした地域の活動に参加しているご家庭は、家族関係も良好なケースが多いように感じます。社会とのつながりを持つことは、心身の健康だけでなく、家族全体の安心にも繋がるのかもしれませんね。
健康寿命運動のよくあるご質問(FAQ)
まとめ:今日から始める健康寿命運動のすすめ
今回は、健康寿命を延ばすための運動について、様々な角度からお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。最後に、この記事の要点をリスト形式でまとめます。
- 健康寿命とは心身ともに自立して生活できる期間のこと
- 平均寿命との差は男性約9年、女性約12年ある
- 運動不足は筋力低下や生活習慣病のリスクを高める
- 運動習慣は健康寿命を延ばすという科学的根拠がある
- 健康寿命を延ばす要因の第1位は運動習慣
- 運動効果を高めるには食事、特にタンパク質が重要
- 運動後のタンパク質摂取が筋肉の回復を助ける
- 初心者にはウォーキングやラジオ体操がおすすめ
- 膝や腰が不安な方には水中運動が効果的
- 自宅でできる簡単な運動でも継続することが大切
- イスを使ったスクワットは下半身強化に最適
- 片足立ちは転倒予防に繋がるバランストレーニング
- 筋トレは姿勢を保つ「抗重力筋」を意識する
- 多くの自治体が住民向けの健康増進プログラムを実施している
- 今日からプラス10分多く体を動かす意識を持つことから始めよう



最後までお読みいただき、ありがとうございました。健康寿命を延ばすことは、最高の「終活」であり、未来のご自身とご家族への最高のプレゼントです。今日ご紹介した運動は、どれも簡単なものばかり。まずは一つでも良いので、試してみてください。その小さな一歩が、10年後、20年後の元気なあなたを作ります!
▼あわせて読みたい関連記事▼












