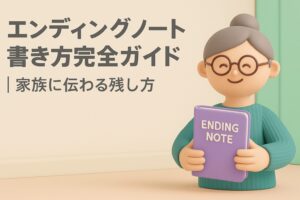こんにちは!終活・相続の専門家、カズです。いやあ、突然「遺影写真、どうしよう…」ってなると、本当に焦りますよね。
「どんな写真がいいの?」「そもそもマナーとかあるの?」って、頭の中がクエスチョンマークでいっぱいになる気持ち、僕も数々のお客様から伺ってきました。遺影の選び方一つで、故人様の印象も、残された家族の気持ちも大きく変わることがあります。
遺影写真のサイズや服装、故人が笑顔の写真でもいいのか、遺影タブーはあるのか、など悩みは尽きません。特に、いざという時に良い写真がない人は本当に困ってしまいます。
今回は、遺影の生前準備から遺影写真の加工、若すぎる写真の問題、フレームの選び方、葬儀後の遺影の処分方法、そして飾るのがよくない場所まで、皆さんの不安を解消し、最高の1枚を選ぶお手伝いをさせてください!
- 故人らしさを最大限に引き出す遺影写真の選び方
- サイズや服装など遺影写真の基本的なルールとマナー
- 写真がない場合や生前に準備するための具体的な方法
- 葬儀後の遺影の飾り方から処分までの知識
▼そもそも終活って何から始めるの?という方は、まずはこちらの記事からどうぞ!
終活とは何か?今から始める人生の不安を減らす方法
 コンサルタント @KAZU
コンサルタント @KAZU遺影写真は、ただの記録ではありません。故人様の人柄を伝え、残された人々が在りし日を偲ぶための大切な架け橋です。だからこそ、形式ばったルールよりも「その人らしさ」を大切にする視点が重要になります。この記事で、後悔のない写真選びの第一歩を踏み出しましょう。
後悔しない遺影写真の準備と選び方の基本


故人らしい遺影 選び方のポイント
遺影写真を選ぶとき、一番大切にしてほしいのが「故人らしさが伝わるか」という点です。昔は真面目な顔で、きっちり正装した写真が「遺影の定番」でしたが、今は時代が大きく変わりました。むしろ、その人柄がにじみ出るような、自然な表情の写真を選ぶ方が増えています。
僕が担当したお客様で、お父様を亡くされた方がいらっしゃいました。お父様は釣りが趣味で、いつも日焼けして楽しそうに笑っていたそうです。
アルバムを探すと、立派なスーツ姿の写真もあったのですが、ご家族が満場一致で選んだのは、大きな魚を掲げて満面の笑みで写っている一枚でした。
「父さんらしいのは、やっぱりこっちだよね」と。参列された方々も、その写真を見て「〇〇さんらしいなあ」と、思い出話に花を咲かせていました。
▼故人様の趣味や生きがいが伝わる写真選びは素敵ですね。シニア世代の趣味探しについてはこちらの記事も参考にしてみてください。
シニア習い事人気ランキング|60代から始める趣味特集
「故人らしさ」を判断する3つの視点
- 表情:穏やかな微笑みや、楽しそうな表情など、その人柄を表すものか。
- 趣味や好きなこと:趣味に打ち込んでいる姿や、旅行先でのリラックスした一枚も素敵です。
- ご家族の想い:「この写真を見ると、お父さん(お母さん)を思い出す」と感じる一枚が一番です。
もちろん、ピントが合っていて、お顔がはっきり写っていることは大前提です。ですが、技術的なこと以上に、ご家族が愛情を感じられる写真を選ぶことが、何よりの後悔しないための選び方と言えるでしょう。
適切な遺影写真 サイズはどれくらい?


遺影写真と一言で言っても、実は葬儀で使うサイズは主に2種類あるんです。これを知らないと、いざという時に「あれ?小さいのしかない!」なんてことにもなりかねません。葬儀社さんで準備してくれることがほとんどですが、知識として知っておくと安心ですよ。
主に祭壇に飾るための大きなサイズと、焼香台などに置かれる小さなサイズの2つを準備します。
| 用途 | 一般的なサイズ | 特徴 |
|---|---|---|
| 祭壇用 | 四つ切り(約30.5cm×25.4cm)やA4サイズ | 参列者席からでもお顔がはっきり見えるように、大きめのサイズが選ばれます。 |
| 焼香台・仏壇用 | L判(約12.7cm×8.9cm)や2Lサイズ | 葬儀後に自宅の仏壇のそばに飾ることを想定したサイズ。手元に残す写真ですね。 |
元の写真が小さすぎると、祭壇用に大きく引き伸ばしたときに画像が荒れてしまう可能性があります。目安として、元の写真のお顔の大きさが10円玉以上あると、キレイに仕上げやすいと言われています。最近のスマートフォンのカメラは性能が良いので、しっかり撮れていればあまり心配はいりません。
僕の経験上、集合写真から切り抜く場合は特に注意が必要です。ご本人は素敵に写っていても、引き伸ばしたらぼやけてしまった…という失敗談も。できるだけご本人が大きく写っている写真を探すのが成功の秘訣ですね。
遺影写真 服装は普段着でも大丈夫?
「遺影写真の服装は、絶対にスーツや着物じゃないとダメですか?」これ、本当によく聞かれる質問です。結論から言うと、全くそんなことはありません!
前述の通り、今の遺影選びで重視されるのは「故人らしさ」です。もし故人様が普段から愛用していたお気に入りのセーターや、趣味の活動で着ていたユニフォームがあるなら、そちらの方がよりその人柄を偲ぶことができるでしょう。
とはいえ、「さすがにパジャマ姿は…」「背景に他の人が写り込んでいる」といったケースもありますよね。ご安心ください。最近の写真加工技術は本当にすごいんです。
遺影写真の加工でできること
専門の業者や葬儀社に依頼すれば、以下のような加工が可能です。
- 服装の着せ替え:普段着からスーツや着物へ自然に合成できます。
- 背景の変更:散かった部屋や他の人物が写っていても、無地の背景や思い出の風景などに変更できます。
- 色あせや傷の修正:古い写真でも、鮮明さを取り戻すことが可能です。
【事実】生前の遺影撮影は「常識」へ
大手葬儀関連サービス企業「株式会社鎌倉新書」が2023年に行った調査によると、自身の葬儀について何らかの準備をしている人のうち、「遺影写真の準備」を終えている、あるいは検討している人は4割以上にのぼります。
この結果は、終活の一環として、元気なうちに自分らしい一枚を残したいと考える人が急増していることを示しており、生前の遺影準備が特別なことではなくなっている現状を反映しています。
ただし、ピントが合っていない写真を鮮明にすることは難しいので、元の写真選びは慎重に行いましょう。服装や背景は後から変えられる、と覚えておけば、写真選びの選択肢がぐっと広がりますよ。
遺影 笑顔の写真を選ぶ際の注意点


「故人が笑っている遺影」って、素敵ですよね。見ているこちらも、なんだか温かい気持ちになります。一昔前は「不謹慎だ」という風潮もありましたが、今では笑顔の遺影を選ぶ方は非常に多くなりました。
ただし、どんな笑顔でも良いかというと、少し注意点があります。例えば、大口を開けて大爆笑している写真などは、見る人によっては少し違和感を覚えるかもしれません。もちろん、それが「最高にその人らしい一枚」であれば問題ありませんが、一般的には穏やかに微笑んでいるくらいの表情が好まれる傾向にあります。
僕のお客様で、お母様の遺影に、お孫さんを見て目を細めて優しく微笑んでいる写真を選んだ方がいました。その方は「母はいつもこうやって僕たちを見てくれていたんです」と話してくれました。葬儀の場でも、その優しい表情が、ご家族の悲しみを少し和らげてくれたように感じました。
最終的にはご家族が「この表情が一番」と思えることが大切です。故人様との思い出を振り返りながら、一番しっくりくる表情の写真を選んであげてください。
遺影 若すぎる写真は避けるべきか
「元気だった頃の、若々しい写真を使ってあげたい」という気持ち、とてもよく分かります。特に、長く闘病されていた場合などは、亡くなる直前の写真を使うのに抵抗があるかもしれません。
遺影に使う写真の撮影時期に厳密なルールはありませんが、一般的には亡くなる前5年~10年以内の写真が目安とされています。あまりに若すぎる写真、例えば20代の頃の写真などを80歳で亡くなった方の遺影に使うと、参列者の方が「どなただろう?」と戸惑ってしまう可能性があります。
若すぎる写真を選ぶ際の注意点
故人様をよく知る親族は分かっても、会社関係者やご友人など、晩年の姿しか知らない方が戸惑うことがあります。葬儀は故人様とゆかりのある方々が集まる場であるため、多くの方が「〇〇さんだ」と分かる写真を選ぶ配慮も大切です。
もし、どうしても若い頃の写真を使いたい場合は、葬儀会場の受付やメモリアルコーナーに、晩年のスナップ写真と一緒に飾るという方法もあります。そうすれば、故人様の人生の歩みを感じてもらうことができ、とても素敵な演出になりますよ。
遺影 写真がない人のための対処法


「探しても、遺影に使えるような写真が全然ない…」というケース、実は少なくありません。特にご高齢の方で、写真を撮る習慣がなかったりすると、本当に見つからないことがあります。でも、諦めないでください。いくつか対処法があります。
考えられる対処法
- 集合写真から切り抜く:ご親族やご友人との集合写真に、鮮明に写っている部分があれば、そこから遺影を作成できる可能性があります。
- 証明写真を利用する:運転免許証やパスポートの写真は、真正面を向いていてピントも合っているため、遺影の元データとして使えることがあります。ただし、画質が粗い場合も多いため、最終手段と考えた方が良いかもしれません。
- スナップ写真を高度に加工する:少しピンボケしていたり、表情が硬かったりする写真でも、専門の業者に依頼すれば、目を少し開けたり、口角を上げたりといった修正を加えて、自然な遺影に仕上げてくれる場合があります。
Googleでよく検索される質問:遺影にしたくない写真とは?
一般的に、ピントが大きくずれていて顔が不鮮明な写真、顔が小さすぎて引き伸ばすと画像が著しく劣化する写真、故人様のイメージとかけ離れすぎている写真(例:コスプレなど)は避ける傾向にあります。ただし、最終的にはご遺族の判断が最も尊重されます。
写真がないからといって、遺影なしで葬儀を行うことももちろん可能です。しかし、遺影は故人様を偲ぶための大切なシンボル。まずは葬儀社に「良い写真がないのですが…」と正直に相談してみてください。プロの視点から、思わぬ解決策を提案してくれるはずです。



ここまで遺影写真の「選び方」に焦点を当ててきました。サイズや服装、表情など、考えることは多いですが、軸になるのは「故人への想い」です。次のセクションでは、生前準備や葬儀後のマナーなど、さらに一歩踏み込んだ知識について解説していきますね。
遺影写真の準備と選び方で知っておきたいこと


遺影 生前準備と写真加工のポイント
最近、「終活」という言葉が一般的になり、ご自身の遺影を生前に準備される方が増えてきました。残される家族の負担を減らせるだけでなく、自分自身が一番気に入った写真を使ってもらえるという大きなメリットがあります。
【事実】デジタル技術で写真はここまで蘇る
大手カメラ・フィルムメーカーである富士フイルムの先進的な画像修復技術では、AI(人工知能)を活用して、古く色褪せた写真や傷のある写真でも高精細に復元することが可能です。
AIが膨大な写真データを学習することで、失われた色彩やディテールを予測・再現し、まるで撮り直したかのような鮮明な画像に仕上げます。この技術により、昔の小さなスナップ写真からでも、自然で美しい遺影を作成することが現実的になっています。
(出典:富士フイルム「高精度な写真修復」)
▼終活を始めるタイミングに悩んだら、こちらの記事がおすすめです。
終活いつから始めるメリット満載!専門家が年代別に解説
生前準備の2つの方法
1. プロに撮影を依頼する 写真館や専門のカメラマンに撮影してもらう方法です。ヘアメイクを整え、プロのアドバイスを受けながら、最高の表情を写真に残すことができます。最近では、葬儀社が開催する終活イベントで、プロによる遺影撮影会が行われることもありますよ。
2. お気に入りの写真を加工しておく 旅行先で撮ったお気に入りの一枚などを、あらかじめ遺影用に加工しておく方法です。背景を整理したり、服装を少しフォーマルなものに修正したり、ご自身で納得のいく形に準備できます。
僕がおすすめしているのは、元気なうちにエンディングノートに「遺影に使ってほしい写真」のありかを記しておくことです。データで保存している場合は、そのフォルダ名やパスワードも一緒に。これだけで、いざという時のご家族の負担は劇的に減ります。まさに愛情のバトンですね。
写真加工を依頼する際は、信頼できる業者を選ぶことが大切です。不自然な仕上がりにならないよう、事前に作例などを確認させてもらうと良いでしょう。
▼写真データやSNSアカウントなど、デジタル遺品の管理も重要です。
デジタル遺品パスワード管理の全知識|トラブル回避術
遺影のフレームには決まりはあるの?


遺影というと、黒い漆塗りの重厚なフレーム(額縁)をイメージされる方が多いかもしれません。しかし、実はフレームの色やデザインに厳密な決まりはありません。
黒いフレームが主流だったのは事実ですが、最近では価値観も多様化し、様々な選択肢が登場しています。
- 木目調のフレーム:温かみがあり、ナチュラルな雰囲気になります。
- シルバーやゴールドのフレーム:モダンで洗練された印象を与えます。
故人様のイメージや、葬儀後に飾るお部屋のインテリアに合わせて選ぶ方も増えています。例えば、いつも明るく華やかな方だったなら、お花が似合うような明るいフレームを選んであげるのも素敵な供養になります。葬儀社でいくつか種類を用意している場合が多いので、ぜひ相談してみてください。
遺影タブーと飾る よくないと言われる理由
遺影の扱いに関して、「これはやってはいけない」というタブーや、古くからの習わしがいくつかあります。知らずにやってしまうと、ご親族から指摘されたり、後から気になってしまったりすることもあるので、ポイントを押さえておきましょう。
最もよく言われるタブーは、仏壇の中や真上に遺影を飾ることです。
なぜ仏壇の中や真上はNG?
仏壇は、ご本尊様(仏様)をお祀りするための神聖な場所です。その中に個人の写真を入れたり、仏様を見下ろす形になる真上に置いたりすることは、ご本尊様に対して失礼にあたると考えられているためです。遺影は、仏壇の近くや、少し離れた場所の壁、あるいは鴨居(かもい)などに飾るのが一般的です。
また、「遺影を飾るとよくない」という噂を聞くことがあるかもしれませんが、これは迷信の類です。故人を偲び、感謝の気持ちを伝えるために飾るものですから、何も問題はありません。むしろ、ご家族が故人様を身近に感じられる大切な習慣と言えるでしょう。方角についても特に決まりはありませんが、気になるようであれば、お部屋が明るくなる東向きや南向きに飾るのが良いとされています。
葬儀後の遺影 処分の方法について


四十九日法要が終わり、日常生活が戻ってくると、「この大きな遺影、ずっと飾っておくべき…?」と悩まれる方がいらっしゃいます。特に、お住まいのスペースの問題で、飾り続けるのが難しい場合もありますよね。遺影の処分は決して罰当たりなことではありません。いくつかの適切な方法があります。
葬儀後の遺影の主な対処法
- 小さいサイズにリサイズして飾る:祭壇用の大きな遺影は保管し、焼香台用に作ったL判などの小さいサイズの写真だけを飾る方法です。これなら場所を取りません。
- データ化して保管する:写真をスキャンしてデジタルデータとして保存します。デジタルフォトフレームに他の思い出の写真と一緒に表示させるのも現代的な方法です。
- お寺や神社で供養(お焚き上げ)してもらう:どうしても処分したい場合は、お寺などで「お焚き上げ」という形で供養してもらうのが最も丁寧な方法です。魂抜きの読経をしてもらった後、焼却します。
- 自治体のルールに従って処分する:遺影に宗教的な意味合いは必須ではないため、自治体のルールに沿って処分することも可能です。その際は、写真とフレームを分別し、他のごみと一緒にならないよう白い紙に包んで塩で清めるなど、感謝の気持ちを込めて行うと、気持ちの整理がつきやすいでしょう。
どの方法を選ぶにしても、ご家族やご親族とよく相談することが大切です。勝手に処分して後でトラブルになるケースも。後悔しないためにも、皆が納得できる方法を選びましょう。
▼遺影の処分と同様に、お墓の管理に悩む方も増えています。こちらの記事も参考にしてください。
墓じまいの流れと費用を完全解説|後悔しない手順ガイド
参考情報サイト:さいたま市「葬祭費・埋葬料(費)の支給」
URL:https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/017/003/p033302.html
遺影写真の選び方よくある質問(FAQ)
最高の遺影写真の準備と選び方まとめ


- 遺影選びで最も大切なのは「故人らしさ」が伝わること
- 写真は亡くなる前5年~10年以内のピントが合ったものを選ぶ
- 祭壇用(四つ切り等)と仏壇用(L判等)の2サイズを準備する
- 元の写真のお顔の大きさは10円玉以上が目安
- 服装は普段着でも問題なく、加工でスーツや着物に変更可能
- 背景に不要な物や人がいても加工で修正できる
- 笑顔の写真は素敵だが、穏やかな微笑みのものが好まれやすい
- 若すぎる写真は参列者が戸惑う可能性があるので配慮が必要
- 写真がない場合は集合写真や証明写真から作成できるか相談する
- 生前準備はプロに撮ってもらうか、お気に入りを加工しておく
- 生前準備の際はエンディングノートに写真の場所を記しておくと親切
- フレームの色やデザインに決まりはなく、自由に選べる
- 遺影を仏壇の中や真上に飾るのはタブーとされる
- 葬儀後の遺影はリサイズやデータ化、供養して処分も可能
- 処分する際は必ず家族や親族と相談して決める



遺影写真の準備と選び方、お疲れ様でした!たくさんのルールやポイントがありましたが、根底にあるのは「故人を大切に想う気持ち」です。この記事が、あなたとご家族が心から納得できる、温かい一枚を選ぶための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
【事実】遺影を含む「葬儀費用」の全国平均
一般財団法人日本消費者協会が2017年に行った「葬儀についてのアンケート調査」によると、葬儀にかかる費用の全国平均は約195.7万円でした。この費用には、飲食費や寺院への費用なども含まれますが、遺影写真の作成や祭壇の装飾といった基本的な項目も含まれています。
葬儀費用は地域によって差がありますが、遺影写真が葬儀全体の印象を左右する重要な要素の一つであることがわかります。
▼あわせて読みたい関連記事▼