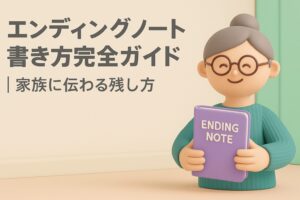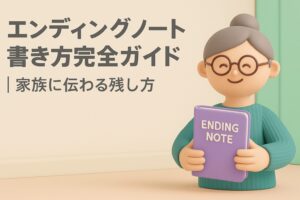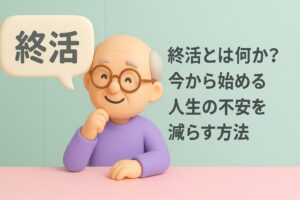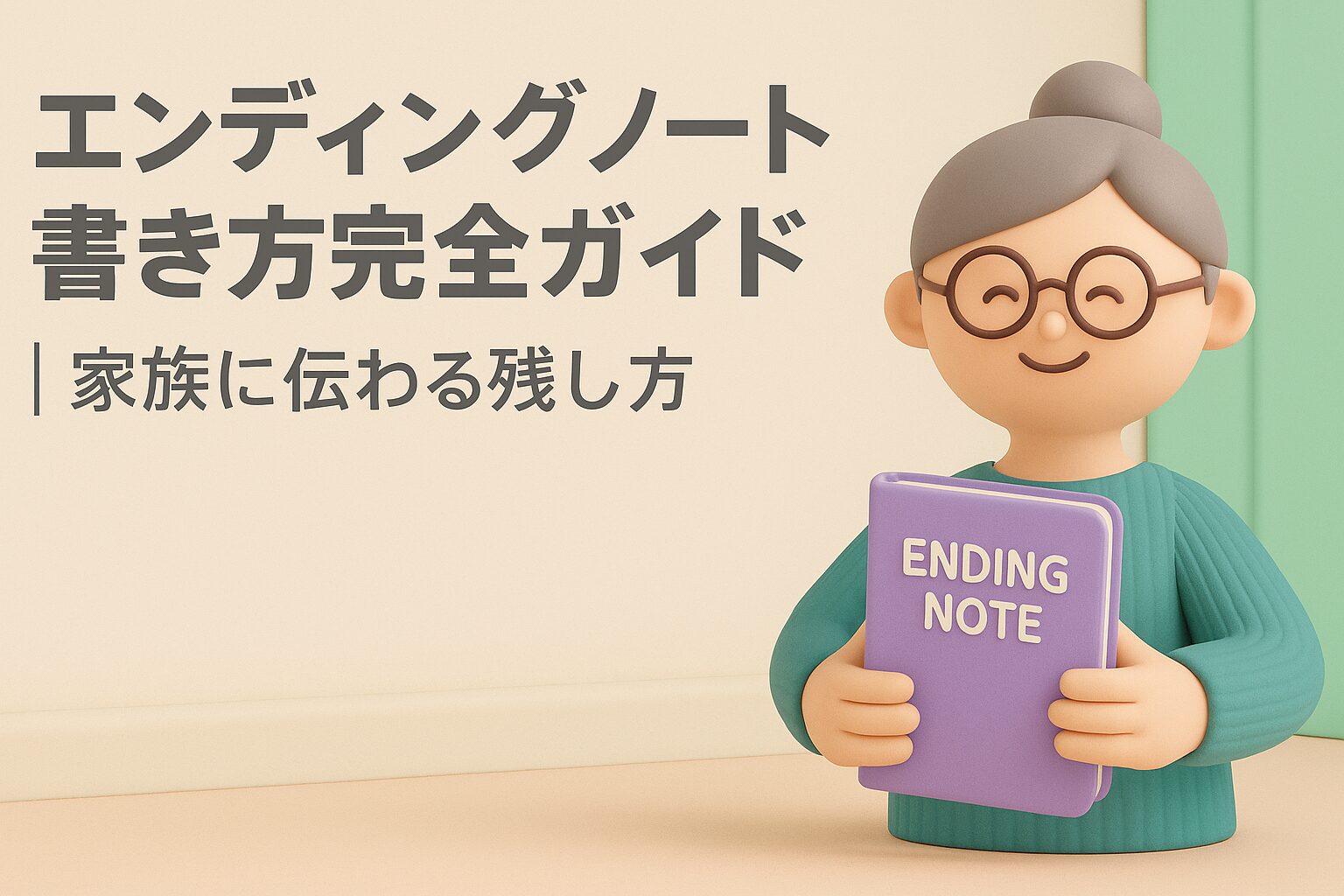
エンディングノートの書き方、気になってはいるけど「何から書けばいいの?」って立ち止まっていませんか?僕も専門家としてお話を聞いていると、エンディングノートに最低限書かなければならないことは何か、具体的な項目一覧や見本が知りたい、という声をよく聞きます。
特に50代くらいになると、親のことやご自身のことで考え始めますよね。それに、最近は若い人向けのものもあるんですよ。この記事では、ダイソーで買えるノートを使った手作りや無料テンプレートでの自作項目の記入例から、子供が助かるエンディングノートの書き方のコツまで、専門家カズがまるっと解説します。
エンディングノートの書き方ができる資格なんて必要ありませんから、安心してくださいね!
- エンディングノートに書くべき基本的な項目
- 世代や目的に合わせた書き方のポイント
- 無料でエンディングノートを始めるための具体的な方法
- 作成する上での注意点と家族への伝え方
 コンサルタント @KAZU
コンサルタント @KAZUエンディングノートって、いざ書こうとするとペンが止まりがちですよね。でも大丈夫!これは「未来の自分」と「大切な家族」への最高のプレゼントなんです。この記事をガイドブック代わりに、まずは書けるところから、楽しんで一歩を踏み出してみましょう。僕がしっかりサポートします!
基本的なエンディングノート書き方


エンディングノートに最低限書くことは?
エンディングノートをいざ書こう!と思っても、あまりに自由だと逆に「えっと…何から?」と固まってしまいますよね。僕が担当したお客様でも、真っ白なノートを前に1ヶ月悩んだ、なんて方もいらっしゃいました。
まずは、「これさえ書いておけば、残された家族が困らない」という最低限の情報から始めるのが鉄則です。難しく考えすぎる必要はありません。
具体的には、以下の3つの柱を意識するとスムーズに進みます。
最低限書いておきたい3つの柱
- 自分自身の基本情報:氏名、生年月日、本籍地、マイナンバーなど、各種手続きで必ず必要になる情報です。
- 資産に関する情報:預貯金口座、不動産、生命保険、ローンなどの一覧。家族が財産の全体像を把握できるようにします。
- 希望や想い:延命治療や介護の希望、葬儀やお墓の要望、そして何より家族や友人へのメッセージです。
特に、今の時代はネット銀行やSNSアカウントなど、デジタル資産も忘れてはいけないポイントです。IDやパスワードの保管場所を記しておくだけでも、家族の負担は大きく減ります。まずはこの3点を押さえること、それがエンディングノート作成の第一歩ですよ。
▼あわせて読みたい
終活とは何か?今から始める人生の不安を減らす方法
具体的なエンディングノート項目一覧


「最低限のことは分かったけど、もっと具体的にどんな項目があるの?」という声が聞こえてきそうですね。承知しました!一般的なエンディングノートで推奨されている項目を一覧にしてみました。もちろん、全てを埋める必要はありません。あなたにとって必要な項目、書きたい項目から手をつけてみてください。
| カテゴリ | 具体的な項目例 |
|---|---|
| 自分自身のこと | 氏名、生年月日、本籍地、血液型、学歴、職歴、家系図、大切な思い出など |
| 医療・介護のこと | かかりつけ医、持病、アレルギー、常用薬、延命治療の希望、介護してほしい場所や人など |
| 資産・財産のこと | 預貯金、不動産、有価証券、生命保険、年金、ローン・借入金、クレジットカード、各種ID・パスワードなど |
| 葬儀・お墓のこと | 希望する葬儀の形式・規模、遺影写真の指定、菩提寺、お墓の場所、納骨の希望など |
| 連絡先リスト | 家族、親戚、親しい友人、お世話になった人など、訃報を伝えてほしい人の連絡先 |
| 大切な人へのメッセージ | 配偶者、子ども、孫、友人など、それぞれに向けた感謝の言葉や伝えたい想い |
| ペットのこと | 名前、年齢、性格、かかりつけの動物病院、自分の死後にお世話をお願いしたい人など |
こうして見るとたくさんありますよね。でも、これはあくまで「見本」です。この中から自分だけのオリジナルなノートを作っていく、という感覚で取り組むのが長続きのコツです。
ちなみに、エンディングノートには法的効力はありません。財産分与など法的な効力を持たせたい内容は、別途遺言書として準備することをおすすめします。
エンディングノートと遺言書の法的な違い
エンディングノートには、ご自身の希望や想いを自由に書き残せますが、法的な拘束力はありません。一方、遺言書は民法で定められた形式で作成することで、財産の分配などについて法的な効力を持たせることができます。法務省も、自筆証書遺言書の作成を希望する方のために、様式や注意点を公開し、その重要性を案内しています。
(出典:法務省「自筆証書遺言書様式」)
参考になるエンディングノート記入例
項目が分かっても「どう書けばいいの?」となりますよね。ここでは、僕がお客様によくお見せする簡単な記入例をご紹介します。ポイントは、事務的な情報だけでなく、自分の「想い」も一言添えること。それだけで、家族が受け取ったときの温かみが全く違ってきます。
【記入例:預貯金について】
銀行名:〇〇銀行 △△支店
口座番号:普通 1234567
保管場所:リビングの棚、茶色い封筒の中
メモ:これは家族旅行のために、毎月コツコツ貯めていたお金です。もしもの時は、みんなで美味しいものでも食べに行ってください。
【記入例:延命治療について】
延命治療は希望しません。
ただし、痛みを和らげる治療は最大限お願いします。
メモ:最後まで自分らしく、穏やかに過ごしたいと思っています。家族には負担をかけたくないけど、わがままを聞いてくれたら嬉しいです。
どうでしょうか?ただ情報を羅列するだけでなく、一言添えるだけで、あなたの気持ちが伝わりやすくなります。これが、エンディングノートが単なる事務書類ではなく、「家族への手紙」にもなる理由なんですよ。
エンディングノート見本で全体像を掴む


文章だけだとイメージが湧きにくいかもしれませんね。そんな時は、実際に見本を見て全体像を掴むのが一番です。
最近では、多くの自治体や関連団体がエンディングノートのフォーマットをWebサイトで公開しています。これらは無料でダウンロードできるものが多く、非常に参考になりますよ。
例えば、市区町村の役所のホームページで「エンディングノート」と検索してみてください。「わたしの終活ノート」といった名前で、PDF形式の見本が見つかることがあります。
見本を探す際のポイント
- 自治体のサイト:お住まいの地域の役所のサイトはまずチェック。地域に特化した情報(地域の葬儀社リストなど)が含まれていることも。
- 法務省や司法書士会のサイト:法律の専門家が監修した、より実用的なフォーマットが見つかる場合があります。
参考情報サイト: 法務省「エンディングノート」
URL: https://www.moj.go.jp/content/001395858.pdf
これらの見本をいくつか見比べることで、「自分にはこの項目が必要だな」「この書き方は分かりやすいな」といった発見があります。最初から完璧を目指さず、まずは見本を参考にしながら、自分だけのノートの設計図を描いてみましょう。
ダイソーで買える?無料での入手方法
「エンディングノートって、立派なものを買わなきゃいけないの?」そんなことは全くありません!実は、もっと気軽に始める方法がたくさんあります。
まず、驚くかもしれませんが、ダイソーなどの100円ショップで売っている普通のノートで十分立派なエンディングノートが作れます。罫線だけのシンプルなノートなら、項目も内容も完全に自由。あなただけのオリジナルノートが作れるのが魅力です。
また、前述の通り、インターネット上には無料でダウンロードできるテンプレートがたくさんあります。自治体やNPO法人が提供しているものは、内容もしっかりしていて安心です。
エンディングノートの主な入手方法
- 市販のものを購入:書店などで数千円で販売。項目が整理されていて書きやすい。
- 100円ショップのノート:ダイソーなどで購入。自由度が高く、安価に始められる。
- 無料テンプレートを印刷:Webサイトからダウンロード。費用をかけずに始められる。
- PCやアプリで作成:Wordや専用アプリでデータとして管理。修正が簡単。
僕のお客様には、「まずはダイソーのノートと、Webの無料テンプレートを参考に始めてみましょう」とアドバイスすることが多いです。大切なのは、高価なノートを用意することではなく、まず一文字でも書き始めてみることですからね。
エンディングノート手作り・自作の項目


市販のノートではなく、手作りや自作でエンディングノートを作成する際の魅力は、なんといってもその自由度の高さです。しかし、自由だからこそ「どんな項目を入れればいいの?」と悩むこともありますよね。
ここでは、自作する際にぜひ入れておきたい、おすすめのオリジナル項目をいくつかご紹介します。
手作り・自作で加えたいオリジナル項目例
- わたしの好きなことリスト:好きな食べ物、音楽、映画、場所など。介護の場であなたの個性を理解してもらうヒントになります。
- 思い出のアルバムページ:特に心に残っている写真と、それにまつわる短いエピソードを書き添えます。家族が見返したときに、温かい気持ちになれるページです。
- 連絡してほしくない人リスト:人間関係は様々です。万が一の際に、家族が対応に困らないよう、配慮として記しておくことも優しさの一つです。
- デジタル遺品の整理:SNSアカウントの扱い(削除か継続か)、有料サブスクリプションサービスのリストと解約方法など。これは非常に実用的です。
僕の経験上、手作りのエンディングノートは、書いた人の人柄がにじみ出て、家族にとって何よりの宝物になることが多いです。市販のノートをベースにしつつ、自分らしいページを数ページ加えるだけでも、ぐっとパーソナルな一冊になりますよ。



ここまでで、エンディングノートの「基本のキ」はバッチリですね!何を書くか、どうやって手に入れるか、イメージが湧いてきたのではないでしょうか。大切なのは完璧を目指さないこと。まずは一項目、一言から。その小さな一歩が、未来の家族を大きく助けることになるんです。
世代別のエンディングノート書き方


若い人向けのエンディングノートとは?
「エンディングノートって、高齢者向けでしょ?」と思っている若い世代の方、実はそれ、少しもったいない考え方かもしれません。最近では、20代や30代といった若い人向けのエンディングノートも注目されているんです。
若い世代にとってのエンディングノートは、「終活」というよりは「これからの人生をどう生きるか」を考えるためのツール、いわば「ライフプランニングノート」としての側面が強いです。もちろん、万が一の備えも重要です。
若い人向けエンディングノートのポイント
- デジタル情報の管理:SNS、ブログ、ネット銀行、仮想通貨など、オンライン上の情報を整理。アカウントの扱いの希望を明記します。
- 夢や目標のリストアップ:「やりたいことリスト100」のように、これからの人生で挑戦したいことを書き出します。
- 自分史の記録:これまでの人生の棚卸し。自分の価値観や強みを再確認するきっかけになります。
- 大切な人へのメッセージ:万が一は、いつ誰に訪れるか分かりません。日頃伝えられない感謝の気持ちを記しておきます。
僕自身も30代ですが、自分のノートには仕事の目標や、子どもに伝えたい自分の考えなどを書き留めています。死を意識するというよりは、「今をより良く生きるため」のツールとして活用する。それが若い人向けのエンディングノートの新しい捉え方だと言えますね。
▼あわせて読みたい
終活いつから始めるメリット満載!専門家が年代別に解説
50代からのエンディングノート書き方


50代は、まさにエンディングノートを書き始めるのに最適な年代かもしれません。子育てが一段落し、親の介護や相続を身近に感じるようになり、ご自身のセンドライフや老後について具体的に考え始める時期だからです。
僕が50代のお客様にご提案する際に強調するのは、「今のうちに、現実的な問題を整理しておきましょう」ということです。特に、財産や医療に関する項目は、時間をかけてじっくりと書き進めることをお勧めします。
【50代からの書き方 3つの重要ポイント】
1. 財産の棚卸しを具体的に:
預貯金や保険だけでなく、実家などの不動産相続の問題や、退職金の運用計画なども含めて、資産と負債を正確に把握します。これが相続税対策の第一歩にもなります。
2. 介護の希望を明確に:
「子どもには迷惑をかけたくない」という想いは皆さん共通です。在宅介護か施設か、費用はどこから捻出するかなど、具体的な希望を記しておくことで、いざという時に家族が判断しやすくなります。認知症などが心配な場合は家族信託という制度も選択肢になります。
エンディングノートと遺言書の法的な違い
エンディングノートには、ご自身の希望や想いを自由に書き残せますが、法的な拘束力はありません。一方、遺言書は民法で定められた形式で作成することで、財産の分配などについて法的な効力を持たせることができます。
法務省も、自筆証書遺言書の作成を希望する方のために、様式や注意点を公開し、その重要性を案内しています。
(出典:法務省「自筆証書遺言書様式」)
3. 家族との情報共有:
書き進めたノートの内容について、少しずつ家族と話す機会を持つことを推奨します。特に、お墓の管理(墓じまいなど)や財産のことは、一方的な希望だけでなく、家族の意見も聞いておくと後のトラブルを防げます。
50代で書き始めることは、残りの人生を安心して、より豊かに過ごすための「お守り」を作ることだと僕は考えています。
子供が助かるエンディングノートの書き方
エンディングノートは、自分のためだけでなく、残される「子供たちのため」という視点が非常に重要です。僕がこれまで見てきた相続の現場で、「あの時、親がこれを書いてくれていたら…」という場面は数え切れないほどありました。
では、具体的に「子供が助かる」エンディングノートとはどんなものでしょうか。ポイントは「分かりやすさ」と「具体性」です。
深刻化する「デジタル遺品」の問題
一般社団法人デジタル遺品研究会ルクシーの調査によると、故人の死後にスマートフォンやパソコンのパスワードが分からず、ロックを解除できなかった経験を持つ遺族は4割以上にのぼります。
特にネット銀行やネット証券、サブスクリプションサービスなどは、遺族がその存在に気づかないまま放置され、トラブルに発展するケースも少なくありません。IDやパスワードの保管場所をエンディングノートに記しておくことは、現代の終活において不可欠な対策となっています。
(出典:一般社団法人デジタル遺品研究会ルクシー)
子供の負担を減らす書き方のコツ
- とにかく保管場所を明確に!:保険証券、年金手帳、不動産の権利証、銀行の通帳など、重要書類の保管場所を一覧にしておきましょう。「リビングのタンスの上から3段目の右奥」のように、誰が見ても分かるように書くのがコツです。
- 連絡先リストは「関係性」も一言:親戚や友人の連絡先リストには、「父の大学時代の親友、〇〇さん」「法事でいつもお世話になっている従兄弟の△△さん」のように、関係性を書き添えておくと、子供たちが連絡する際に非常に助かります。
- 葬儀の希望は「理由」も添えて:「葬儀は家族だけでささやかにお願いします。理由は、みんなに気を遣わせたくないからです」のように理由を添えることで、子供たちがあなたの意思を尊重しやすくなります。
- 感謝の言葉を忘れずに:手続きの情報も大切ですが、最後に「今までありがとう」という感謝の言葉があるだけで、子供たちの心の負担は大きく和らぎます。
エンディングノートは、子供たちへの最後の「引き継ぎ書」であり、最後の「ラブレター」です。事務的な情報と温かいメッセージ、その両方をバランス良く盛り込むことを意識してみてください。
▼あわせて読みたい
終活しない親との向き合い方|専門家がその理由と対策を解説
書き方が学べる資格はある?
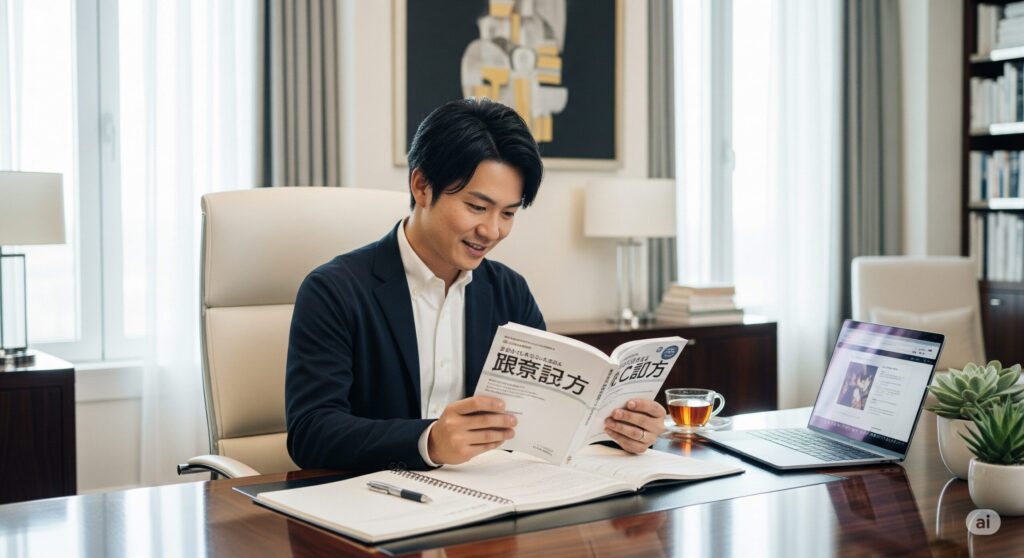
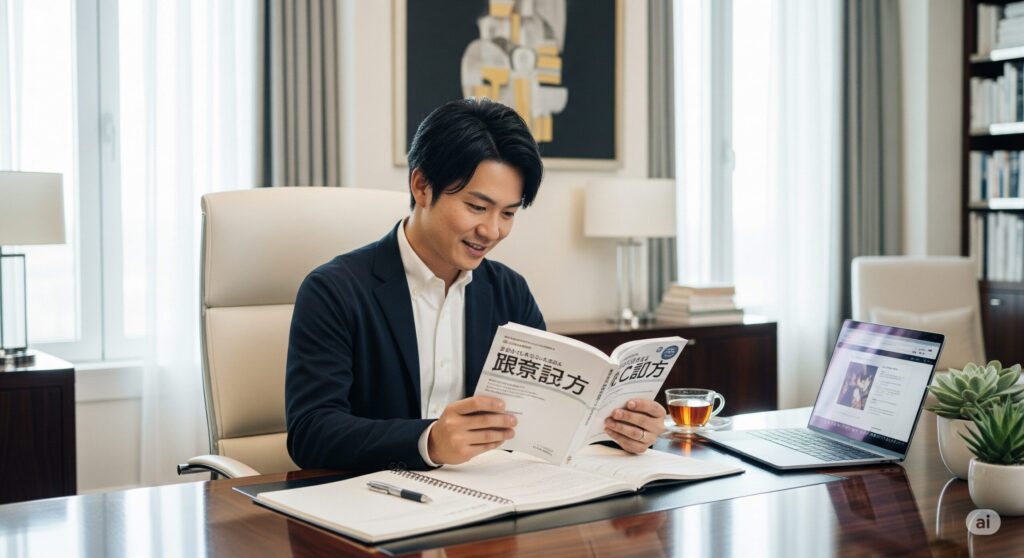
「エンディングノートの書き方を、もっと専門的に学びたい」「仕事に活かしたい」と考える方もいらっしゃるかもしれませんね。結論から言うと、エンディングノートの作成そのものに特定の資格は必要ありません。誰でも、いつでも自由に書くことができます。
ただ、関連する知識を深めるための資格は存在します。これらは、他の方の終活をサポートする際に役立つものです。
【エンディングノートに関連する資格の例】
- 終活ガイド:終活全般に関する幅広い知識を学び、アドバイスができるようになる資格です。
- ファイナンシャル・プランニング技能士(FP):相続や保険、年金といったお金の面から、人生設計をサポートする国家資格です。
- 行政書士:遺言書の作成支援など、法的な書類作成の専門家です。
僕自身もFPの資格を持っていますが、それはお客様に相続や資産について、より的確なアドバイスをするためです。ご自身やご家族のためにエンディングノートを書くのであれば、資格取得にこだわる必要は全くありません。この記事でご紹介したようなポイントを押さえて、まずはペンを取ってみること。それが何より大切ですよ。
エンディングノート書き方に関するFAQ
始めるエンディングノート書き方まとめ
ここまで、エンディングノートの書き方について様々な角度から解説してきました。最後に、この記事の要点をまとめて、皆さんが今日から一歩を踏み出すためのチェックリストにしたいと思います。
- エンディングノートは未来の自分と家族への贈り物
- まず最低限の情報(自分・資産・希望)から書く
- 項目一覧はあくまで見本、全部埋めなくてOK
- 記入例を参考に自分の言葉で想いを添える
- 見本は自治体サイトなどで無料で手に入る
- ダイソーのノートや手作りでも立派に作れる
- 若い人はライフプランニングノートとして活用
- 50代は財産や介護など現実的な問題を整理
- 子供のためには保管場所と連絡先を具体的に
- 作成に特別な資格は一切不要
- 大切なのはまず書き始めてみること
- 法的効力はないので遺言書は別途準備を検討
- 家族と内容を共有するとトラブル防止になる
- 定期的に見直して情報を最新に保つ
- 楽しんで書くことが長続きの秘訣



お疲れ様でした!エンディングノートは、一度書いたら終わりではありません。人生と共に変化し、成長していく「相棒」のようなものです。この記事が、あなたの素晴らしい人生を記録し、大切な人へ想いを繋ぐ、その第一歩となれば、これほど嬉しいことはありません。さあ、あなただけの一冊を始めましょう!
▼あわせて読みたい関連記事▼