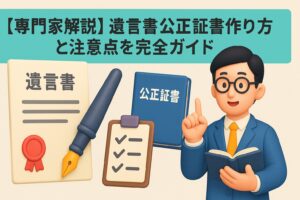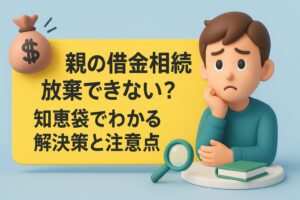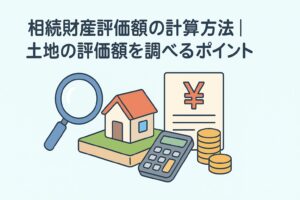「うわっ、親の遺産を調べたら借金の方が多いかも…どうしよう…。」突然のことで頭が真っ白になりますよね。相続放棄の手続きを自分で進めようと思っても、どこで手続きするのか、どんな必要書類がいるのか、兄弟でまとめてできるのか、費用はいくらかかるのか…分からないことだらけで不安じゃないですか?
特に、相続放棄の手続きには期限があって、もし3ヶ月過ぎるとどうなるのか、万が一認められない事例に当てはまったら…と考えると夜も眠れませんよね。
司法書士に頼む費用も気になるし、法テラスで費用の相談はできるのかな、なんてグルグル考えていませんか?ご安心ください!この記事で、そのモヤモヤ、僕カズが全部スッキリさせますよ!
- 相続放棄のタイムリミット(期限)と過ぎた場合のリスク
- 手続きにかかる費用の全貌(自分でやる場合・専門家に頼む場合)
- 手続きの流れと絶対に間違えてはいけない注意点
- 専門家に相談すべきかどうかの具体的な判断基準
 コンサルタント @KAZU
コンサルタント @KAZU相続放棄は、まさに「知らないと損をする」手続きの代表格です。僕も15年以上この仕事をしていますが、期限や費用の知識不足で後悔された方を何人も見てきました。この記事では、僕が現場で得たリアルな知識を基に、皆さんが安心して手続きを進められるよう、ポイントを分かりやすく解説していきますね!
相続放棄手続き期限と費用の基本知識


まずは基本から!ここでは、相続放棄のキホンとなる「いつまでに」「どこで」「何が必要か」といった点を、僕の経験談も交えながら解説します。
相続放棄・手続きの流れ(タイムライン)
【相続発生】 → 【3ヶ月以内】相続放棄を検討 → 【STEP1】必要書類の収集(戸籍謄本など) → 【STEP2】相続放棄申述書の作成 → 【STEP3】家庭裁判所へ申述 → 【STEP4】照会書への回答 → 【STEP5】相続放棄申述受理通知書が届き完了!
- 相続放棄の手続きには期限があります
- 相続放棄の期限を3ヶ月過ぎるとどうなる?
- 相続放棄の手続きはどこでするのか
- 相続放棄の申述に必要な書類
- 相続放棄が認められない事例とは
相続放棄の手続きには期限があります
こんにちは!終活・相続の専門家カズです。
さて、いきなりですが一番大事なことからお伝えしますね。相続放棄の手続きには、原則として「ご自身が相続人であることを知った時から3ヶ月以内」という厳格な期限があります。
この3ヶ月という期間は「熟慮期間」と呼ばれていて、この間に「相続するのか、それとも放棄するのか、よーく考えて決めてくださいね」というわけです。
多くの場合、このカウントが始まるのは「被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知った日」です。でも、ちょっと注意が必要なケースもあります。例えば、第一順位の相続人である子供が全員相続放棄をした結果、第二順位である親(亡くなった方から見ると祖父母)に相続権が移る場合があります。
この場合、祖父母の方々は「子供たちが相続放棄したことを知った日」から3ヶ月以内に手続きを判断する必要があるんです。
以前、ご相談に来られたAさんは、疎遠だったお兄様が亡くなったことを数ヶ月後に知り、慌てていました。さらに、お兄様のお子さん(Aさんから見れば甥姪)が相続放棄したことを人づてに聞いたのが、そのさらに1ヶ月後。
「もう手遅れかも…」と真っ青でしたが、「甥姪が放棄したことを知った日から」が起算日になるため、ギリギリ間に合った、なんていうハラハラする事例もありました。相続放棄手続き期限と費用を正しく理解していないと、本当に大変なことになります。
このように、いつから3ヶ月なのかは状況によって変わるため、期限の管理は本当に重要です。
相続放棄の期限を3ヶ月過ぎるとどうなる?


「もし、うっかり3ヶ月の期限を過ぎてしまったら…?」
考えただけでも恐ろしいですが、この場合、原則として財産も借金もすべて丸ごと受け継ぐ「単純承認」をしたと見なされてしまいます。
つまり、後から「やっぱり借金が多いから放棄したい!」と思っても、もう相続放棄はできなくなるのがルールです。
単純承認とは?
亡くなった方の権利や義務(プラスの財産もマイナスの財産も)を無条件・無制限にすべて承継することです。熟慮期間内に相続放棄や限定承認の手続きをしないと、自動的に単純承認したことになります。
ただし、これには一応、救済措置があります。
例えば、「被相続人に借金があるなんて夢にも思わず、そう信じるのに相当な理由があった」という特別な事情がある場合です。
僕が担当したお客様で、亡くなったお父様は真面目な公務員で、借金とは無縁だと思い込んでいたBさんがいました。ところが、お父様が亡くなって半年ほど経ったある日、消費者金融から分厚い督促状が届き、初めて多額の借金があったことを知ったのです。
このケースでは、「借金の存在を知った時から3ヶ月以内」に事情を詳しく説明して申述することで、無事に相続放棄が認められました。
期限を過ぎてからの手続きは非常に難易度が高く、家庭裁判所に事情を詳しく説明する「上申書」などの追加書類も必要になります。もし期限を過ぎてしまった場合は、すぐに相続税の計算方法なども含めて相談できる専門家を頼ることを強くおすすめします。
【事実】年間26万件以上が利用する相続放棄
最高裁判所が公表している「司法統計」によると、全国の家庭裁判所で受理された相続放棄の申述件数は、近年増加傾向にあり、2022年(令和4年)には過去最多の260,498件に達しました。
- 2020年(令和2年):234,741件
- 2021年(令和3年):249,766件
- 2022年(令和4年):260,498件
このデータは、相続放棄が決して珍しい手続きではなく、借金などの問題から自身や家族の生活を守るために、広く活用されている法的な権利であることを示しています。
(出典:最高裁判所 司法統計年報(令和4年度))
相続放棄の手続きはどこでするのか
相続放棄の手続きをする場所は、意外と間違えやすいポイントです。
正解は、亡くなった方(被相続人)の「最後の住所地」を管轄する家庭裁判所です。
今ご自身が住んでいる場所の最寄りの裁判所や、本籍地の裁判所ではないので、注意してくださいね。
例えば、ご自身は東京在住でも、亡くなったご両親が福岡に住んでいたなら、手続きは福岡の家庭裁判所で行う必要があります。
「え、遠方だと大変じゃない?」と思われるかもしれませんが、ご安心ください。手続きは、必要書類を家庭裁判所の窓口へ直接持っていく方法のほかに、郵送で提出することも可能です。
管轄の家庭裁判所がどこになるかは、裁判所のウェブサイトで簡単に調べることができます。
参考情報サイト: 裁判所「裁判所の管轄区域」
URL: https://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/index.html
相続放棄手続き期限と費用も大切ですが、まずは正しい場所で手続きを始めることが第一歩です。
相続放棄の申述に必要な書類


手続きをスムーズに進めるには、事前の書類準備がカギになります。基本となる必要書類は以下の通りです。
| 書類名 | 取得場所 | 簡単な説明 |
|---|---|---|
| 相続放棄の申述書 | 裁判所のウェブサイト | 手続きのメインとなる書類。裁判所のサイトから書式をダウンロードできます。 |
| 被相続人の住民票除票(または戸籍附票) | 被相続人の最後の住所地の市区町村役場 | 亡くなった方の最後の住所を証明する書類です。 |
| 申述人(ご自身)の戸籍謄本 | ご自身の本籍地の市区町村役場 | ご自身が相続人であることを証明します。 |
| 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 | 亡くなった事実と、その方との関係を証明します。 |
これらはあくまで基本セットです。
申述する方と亡くなった方の関係によっては、追加で別の書類が必要になることがあります。
例えば、亡くなった方の「子供」ではなく「兄弟姉妹」が相続放棄をする場合は、「亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本」や「亡くなった方の親の死亡が記載された戸籍謄本」など、より多くの戸籍を集めて、ご自身が相続人であることを証明する必要が出てきます。
これが結構大変で、「戸籍を遡るってどうやるの?」とパニックになる方も多いんです。昔の戸籍は手書きで読みにくかったり、本籍地を転々とされていると、全国の役所に請求が必要になったり…。書類集めだけで心が折れそうになったら、無理せず専門家を頼ってくださいね。
相続放棄が認められない事例とは
「よし、書類も揃ったし、これで安心!」…と、その前に。実は、ある行動をとってしまうと、相続放棄が認められなくなることがあるので要注意です。
最も代表的なのが、相続財産を一部でも処分してしまう行為です。
これは法律で「単純承認」と見なされる行為で、「財産を受け継ぐ意思があるんですね」と判断されてしまうんです。
具体的には、以下のような行為が該当します。
単純承認と見なされる可能性のある行為
- 亡くなった方の預貯金を引き出して、自分の生活費やローンの支払いに使ってしまった。
- 亡くなった方の所有していた不動産や自動車を売却してしまった。
- 形見分けのつもりで、高価な骨董品やブランド品を持って帰ってしまった。
「借金の返済に充てるためなら大丈夫でしょ?」と思うかもしれませんが、それもNGです。亡くなった方の財産から借金を返済する行為も「財産の処分」にあたります。
僕のお客様でも、お父様の葬儀費用が足りず、やむを得ずお父様の預金から少しだけ引き出して支払った方がいました。葬儀費用のような社会通念上相当な範囲での支払いは認められることが多いですが、それでも非常にデリケートな問題です。相続財産には一切手を付けないのが、相続放棄を考えている場合の鉄則です。そもそも相続財産をどう分けるか、どう残すかは、故人の意思が示された遺言書の書き方も大きく関わってきます。
【法律の根拠】「法定単純承認」とは?
記事で解説されている「相続財産を処分すると相続放棄ができなくなる」というルールは、民法第921条で「法定単純承認」として定められています。具体的には、以下の場合に単純承認したとみなされます。
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び短期の賃貸をすることは、この限りでない。
- 相続人が熟慮期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
- 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。(一部抜粋)
たとえ葬儀費用のためであっても、故人の預金を引き出す行為などがこの「処分」に該当すると判断されるリスクがあるため、相続財産には一切手を付けないことが最も安全な対応です。
(出典:e-Gov法令検索 民法)



ここまで基本知識を見てきました。特に「3ヶ月の期限」と「財産に手を付けない」という2点は、相続放棄の成否を分ける超重要ポイントです。この基本をしっかり押さえるだけでも、大きな失敗は防げます。もし少しでも不安な点があれば、迷わず専門家に相談してくださいね。それが一番の近道です!
状況別の相続放棄手続き期限と費用


基本が分かったところで、次は気になるお金の話。状況によって費用はどう変わるのか、具体的な金額の目安を見ていきましょう。
【保存版】相続放棄 やることチェックリスト
- □ 被相続人の最後の住所地を確認したか?
- □ 管轄の家庭裁判所を調べたか?
- □ 自分の戸籍謄本は取得したか?
- □ 被相続人の戸籍謄本類はすべて揃っているか?
- □ 収入印紙(800円分)と郵便切手は準備したか?
- □ 故人の預貯金や財産には一切手をつけていないか?
- 相続放棄の手続きにかかる費用について
- 相続放棄の手続きを自分で行う場合
- 私はどれ?30秒でわかる専門家選びの診断チャート
- 兄弟でまとめて相続放棄する際の費用
- 法テラスで相続放棄の費用相談は可能か
相続放棄の手続きにかかる費用について
相続放棄の手続きにかかる費用は、大きく分けると「実費」と「専門家への報酬」の2つに分類できます。
実費というのは、ご自身で手続きを行う場合でも、専門家に依頼する場合でも、必ず発生する基本的な費用のことです。
- 収入印紙代:申述書1通につき800円
- 連絡用の郵便切手代:数百円〜1,000円程度(裁判所によって異なります)
- 必要書類の取得費用:戸籍謄本1通450円、除籍・改製原戸籍謄本1通750円など。取得する通数によりますが、数千円程度かかることが多いです。
一方、専門家への報酬は、司法書士や弁護士に手続きの代行を依頼した場合に発生する費用です。これは事務所によって料金体系が異なるため、事前に確認が必要です。
相続放棄手続き期限と費用を考える際には、この「実費」と「報酬」の2つを念頭に置いて計画を立てることが大切になります。特に不動産が含まれる相続の場合、その不動産の名義変更や相続の評価額によって専門家の報酬が変わることもあるため、注意が必要です。
相続放棄の手続きを自分で行う場合


前述の通り、相続放棄の手続きをご自身で行う(DIYする)場合、費用を最も安く抑えられるという大きなメリットがあります。
かかる費用は基本的に「実費」のみ。
主な内訳は、収入印紙代800円、連絡用の郵便切手が数百円、そして戸籍謄本などの取得費用が数千円程度です。
合計しても、一般的には5,000円前後で手続きを完了させることが可能でしょう。
【自分で手続きする場合のメリット・デメリット】
メリット:なんと言っても費用が安い!
デメリット:書類の収集や作成に時間と手間がかかる。不備があると受理されないリスクがある。裁判所とのやり取りも全て自分で行う必要がある。
ご自身でやる場合は、時間に余裕があり、役所や裁判所とのやり取りが苦にならない方に向いていると言えます。ただ、少しでも不安があれば、費用はかかりますが専門家に任せた方が確実で安心です。相続放棄手続き期限と費用を天秤にかけ、ご自身の状況に合った方法を選びましょう。
私はどれ?30秒でわかる専門家選びの診断チャート
「自分で行うべきか、それとも専門家を頼るべきか…」と迷いますよね。そこで、あなたにピッタリの選択肢がわかる簡単な診断チャートを用意しました!
あなたはどのタイプ?専門家選びの簡単診断
この診断で、ご自身の状況に合った専門家が見えてきたでしょうか?さらに具体的に、費用と「どこまでやってくれるのか」を比較した表も見てみましょう。
| 項目 | 自分でやる | 司法書士 | 弁護士 |
|---|---|---|---|
| 費用目安 | 約5千円 | 3万~5万円 | 5万~10万円 |
| 書類収集 | △(自分) | ◎(代行) | ◎(代行) |
| 申述書作成 | △(自分) | ◎(代行) | ◎(代行) |
| 裁判所とのやり取り | △(自分) | △(自分) | ◎(代理) |
| 債権者対応 | △(自分) | ×(不可) | ◎(代理) |
このように、費用とサービス範囲はトレードオフの関係にあります。ご自身の「時間」「知識」「精神的な負担」を考慮して、最適な方法を選んでくださいね。より複雑な財産管理の方法として、家族信託の活用を検討する際も、司法書士は頼れる専門家の一人です。
兄弟でまとめて相続放棄する際の費用


「兄弟全員で放棄するなら、まとめて手続きした方が安上がりだよね?」
これは非常によくあるご質問ですが、実は少し認識が違います。
相続放棄は、あくまで相続人一人ひとりが個別に家庭裁判所へ申述する必要がある手続きです。そのため、「兄弟でまとめて一括申請」というような制度は存在しません。
費用についても、申述書に貼る収入印紙800円は、放棄する人数分が必要になります。兄弟3人で放棄するなら「800円×3人分=2,400円」の収入印紙が必要です。
ただ、少しだけ費用を抑えられるポイントもあります。
それは、被相続人の戸籍謄本など、兄弟間で共通して使える書類がある点です。これらの書類は1通取得すれば、兄弟それぞれの申述で使い回すことができます(コピーの提出が認められる場合が多いですが、裁判所にご確認ください)。
そのため、書類の取得費用は、一人ずつバラバラに申請するよりも少しだけ節約できる可能性があります。
FAQセクション
法テラスで相続放棄の費用相談は可能か
「専門家に頼みたいけど、正直、経済的に厳しい…」という方もいらっしゃると思います。
そんな時に頼りになるのが、法テラス(日本司法支援センター)です。
法テラスでは、収入や資産が一定の基準以下であるなどの条件を満たせば、以下のようなサポートを受けられる可能性があります。
- 無料の法律相談
- 弁護士・司法書士の費用の立替制度(民事法律扶助)
立替制度を利用すれば、ひとまず法テラスが専門家への費用を立て替えてくれ、ご自身は後から月々5,000円〜10,000円程度の分割で返済していくことができます。
利用には審査がありますが、費用面で相続放棄をためらっている方は、一度お近くの法テラスに相談してみることを強くおすすめします。これも、相続放棄手続き期限と費用に関する有益な情報の一つです。
参考情報サイト: 日本司法支援センター 法テラス
URL: https://www.houterasu.or.jp/
▼相続とお金についてもっと知りたい方はこちら!
老後までに必要なお金はいくら?不安を解消する徹底ガイド
総括:相続放棄手続き期限と費用の要点


最後に、この記事の重要ポイントをまとめます。これだけは覚えて帰ってくださいね!
- 相続放棄の期限は原則「相続を知ってから3ヶ月以内」
- 期限を過ぎると原則として全財産を相続することになる(単純承認)
- 例外的に期限後でも認められるケースはあるがハードルは高い
- 手続きは亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う
- 郵送での手続きも可能
- 必要書類は戸籍謄本など多岐にわたり、関係性によって増える
- 相続財産(預金など)に手を付けると放棄できなくなるので注意
- 自分で手続きすれば費用は数千円程度で済む
- 司法書士への依頼費用は3万円~5万円が相場
- 弁護士への依頼費用は5万円~10万円が相場だが債権者対応も任せられる
- 兄弟でまとめて放棄する場合も費用は人数分かかる
- 経済的に厳しい場合は法テラスの利用を検討する
- 手続きに少しでも不安があれば速やかに専門家へ相談することが重要
- 相続放棄手続き期限と費用はセットで考えるべき最重要項目
- 最終的な判断は慎重に行う必要がある



相続放棄は、精神的にも時間的にも負担の大きい手続きです。ですが、正しい知識さえあれば、決して怖いものではありません。この記事で、相続放棄手続き期限と費用についての不安が少しでも軽くなっていたら嬉しいです。一人で抱え込まず、適切なタイミングで専門家の力を借りることも、賢い選択の一つですよ!
▼あわせて読みたい関連記事▼