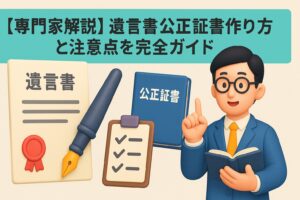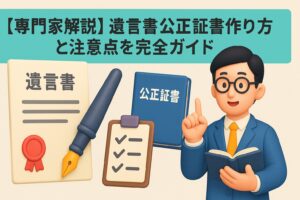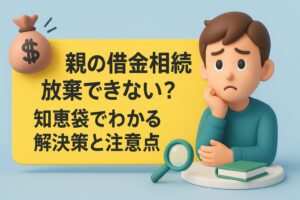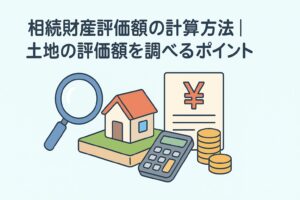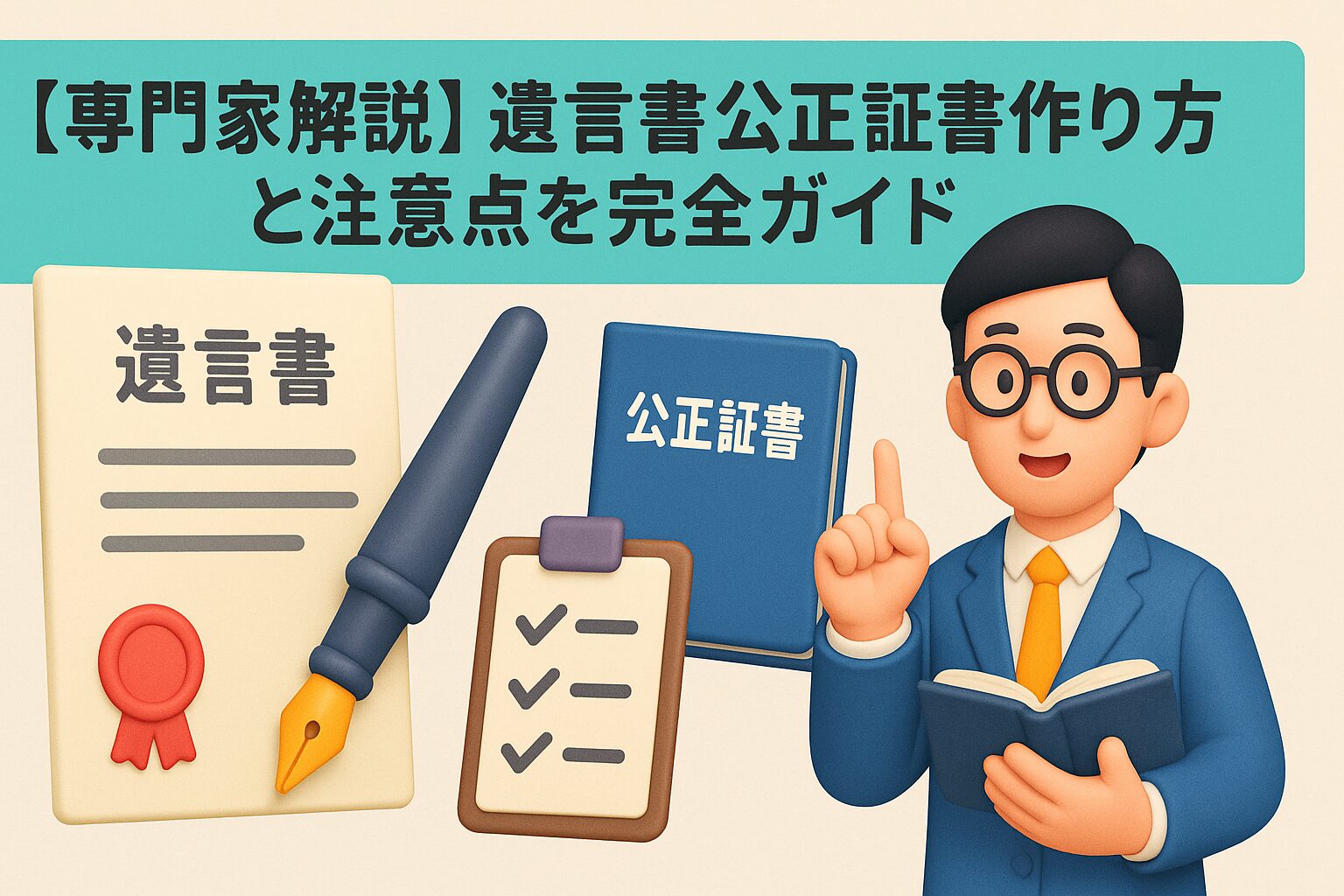
「相続でもめたくない…」そう思って遺言書の準備を考えているけれど、公正証書遺言なんて言葉を聞くだけで、なんだか難しそうに感じてしまいますよね。「一体何から手をつければいいの?」と、頭を抱えていませんか。
公正証書遺言の効力はどれくらい強力なのか、自分で作成することは可能なのか、気になる費用やその計算方法、さらには膨大な必要書類や証人は誰に頼めば良いのか。
考え出すとキリがありません。万が一、死亡したらその後の手続きや通知はどうなるのか、遺言内容は誰が見れるのか、そして何より、せっかく作っても家族がもめる原因になったり、無効になる場合があるのか…そんな不安や疑問が、あなたの第一歩をためらわせているのかもしれませんね。
ご安心ください、この記事でそのお悩み、まるっと解決しますよ!
- 公正証書遺言の基本的な知識とメリット・デメリット
- 作成手順と必要書類の集め方
- 具体的な費用とその計算方法
- 作成後の注意点や相続トラブルを避けるコツ
 コンサルタント @KAZU
コンサルタント @KAZUこんにちは!公正証-書遺言は「最強の遺言書」なんて言われることもありますが、作り方や内容一つで、ご家族の未来が大きく変わることもあるんです。多くの方が後悔しないために、私が現場で培ってきた実践的な知識を、この記事で余すことなくお伝えしますね。さあ、一緒に円満相続への第一歩を踏み出しましょう!
遺言書公正証書作り方と注意点【基本知識】


公正証書遺言が持つ法的な効力とは
公正証書遺言は、他の遺言書と比べて極めて高い証明力と法的な効力を持つとされています。なぜなら、法律の専門家である「公証人」が作成に関与するからです。
公証人は、元裁判官や検察官などが任命される公務員で、遺言の内容が法的に有効であるか、そして遺言者本人の意思に間違いがないかを厳格に確認しながら書類を作成します。このため、自筆で書く遺言書にありがちな「書き方を間違えて無効になってしまった…」というリスクがほとんどありません。
また、作成された遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されます。これにより、遺言書が紛失したり、誰かに隠されたり、内容を書き換えられたりする心配がないのです。相続が発生した後、家庭裁判所での「検認」という手続きも不要になるため、相続手続きをスムーズに進められるという大きなメリットもあります。
言ってしまえば、あなたの最後の意思を最も確実にご家族へ届けるための、強力な手段がこの公正証書遺言なのです。
公正証書遺言の効力のポイント
- 無効になりにくい:法律のプロ(公証人)が作成するため、形式不備のリスクが低い。
- 偽造・紛失の心配なし:原本が公証役場に保管されるため安全。
- 検認手続きが不要:相続開始後、速やかに遺産分割手続きに入れる。
【事実】データで見る遺言書の有効性
最高裁判所が公表する司法統計によると、家庭裁判所で遺言書の有効性が争われたケース(令和2年度)では、自筆証書遺言が「無効」と判断された割合は0.43%でした。
一方、公正証書遺言は作成段階で公証人が内容の適法性を確認するため、方式不備で無効になることは基本的にありません。また、家庭裁判所での検認手続きも不要なため、相続開始後の手続きがスムーズに進むという大きな利点があります。
公正証書遺言を自分で作成する手順


「公正証書遺言は専門家に依頼しないと作れない?」と思われがちですが、実はご自身で主導して作成を進めることも可能です。もちろん、公証人とのやり取りは必須ですが、専門家への依頼費用を抑えたい場合に選択肢となります。
ご自身で作成する場合の基本的な流れは以下の通りです。
- 遺言内容の検討:誰に、どの財産を、どれだけ渡すのか、財産の分け方を具体的に決め、メモに書き出します。
- 証人2名の選定:遺言の作成に立ち会ってもらう証人を2人決めます。信頼できる友人などにお願いすることも可能ですが、なれない人の条件(後述)があるので注意が必要です。
- 公証役場への連絡と相談予約:お近くの公証役場に電話をして、遺言書を作成したい旨を伝え、相談日時を予約します。
- 必要書類の収集:公証人から指示された戸籍謄本や財産に関する資料などを集めます。
- 公証人との打ち合わせ:予約した日時に公証役場へ行き、遺言内容や集めた書類について公証人と打ち合わせをします。この打ち合わせを元に、公証人が遺言書の文案を作成します。
- 遺言書作成日当日:指定された日時に、遺言者本人と証人2名が公証役場に集まります。公証人が遺言書の内容を読み上げ、全員で内容に間違いがないか確認した後、署名・押印をして完成です。
このように、手順自体は明確です。ただ、戸籍謄本などの書類収集や、法的に問題のない遺産分割内容の検討には、ある程度の知識と時間が必要になる点は理解しておきましょう。
公正証書遺言の作成で必要な書類一覧
公正証書遺言の作成には、誰が、何を、誰に遺すのかを公的に証明するために、いくつかの書類が必要になります。公証役場によって多少異なる場合もありますが、一般的に必要とされる主な書類は以下の通りです。
一般的に必要となる書類
事前に準備しておくと、公証人との打ち合わせがスムーズに進みます。
- 遺言者本人に関するもの
- 印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)と実印
- 戸籍謄本
- 財産を渡す相手との関係がわかるもの
- 相続人に渡す場合:遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
- 相続人以外に渡す場合:財産を受け取る人の住民票
- 財産に関するもの
- 不動産:登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
- 預貯金:通帳のコピーなど、銀行名・支店名・口座番号がわかるもの
- その他:有価証券の残高証明書など、財産を特定できる資料
- 証人に関するもの
- 証人の氏名、住所、生年月日、職業をまとめたメモ(住民票や運転免許証のコピーを求められることもあります)
これらの書類は、市区町村役場や法務局などで取得します。全ての財産を正確にリストアップし、必要な書類を漏れなく集めるのは少し大変な作業ですが、遺言の信頼性を担保するためにとても重要なプロセスです。
公正証書遺言の証人になれない人の条件


公正証書遺言を作成する際には、必ず2人以上の証人が立ち会う必要があります。この証人は、遺言が遺言者本人の自由な意思に基づいて作成されたことを証明する、とても重要な役割を担います。
しかし、誰でも証人になれるわけではありません。遺言の内容に利害関係があったり、中立な立場で判断できなかったりする可能性がある人は、民法で証人になることができないと定められています。これを「証人の欠格事由」と言います。
証人になれない人(欠格者)
以下の条件に当てはまる人は証人になることができません。もし欠格者が証人となった場合、その遺言自体が無効になってしまう可能性があります。
- 未成年者
- 推定相続人(将来、相続人になる予定の人)、およびその配偶者や直系血族
- 受遺者(遺言によって財産を受け取る人)、およびその配偶者や直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
つまり、ご自身の配偶者やお子さん、財産をあげる予定の知人などは証人にはなれない、ということです。もし身近に頼める人がいない場合は、公証役場で紹介してもらうこともできますし、作成を依頼した弁護士や司法書士などの専門家が証人になることも一般的です。
公正証書遺言の費用と詳しい計算方法
公正証書遺言の作成には、公証役場に支払う手数料がかかります。この手数料は、国が定めた「公証人手数料令」という法律に基づいており、遺言で渡す財産の価額に応じて変動します。決して、公証人が自由に決めているわけではないのですね。
手数料の計算は少し複雑ですが、基本的には「財産を受け取る人ごと」に、その人が受け取る財産の額を算出し、それぞれに対応する手数料を合計する、という流れになります。
手数料の基本料金テーブル
まずは、財産の価額に応じた基本手数料を確認してみましょう。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
(出典:日本公証人連合会「遺言」)
手数料の加算ルール
上記の基本手数料を合計したものに、さらにいくつかの加算があります。
- 遺言加算:全体の財産が1億円以下の場合は、上記で計算した合計額に11,000円が加算されます。
- 枚数による加算:遺言書の原本が4枚を超える場合、超える1枚ごとに250円が加算されます。
- 出張費用:もしご自宅や病院などに公証人に来てもらう場合は、基本手数料が1.5倍になるほか、日当(1日2万円、4時間までなら1万円)と交通費実費が必要です。
- 証人の日当:公証役場で証人を紹介してもらう場合は、1人あたり5,000円~15,000円程度の日当が別途必要です。
例えば、妻に3,000万円、長男に2,000万円の財産を遺す場合、妻の手数料は23,000円、長男の手数料も23,000円。合計46,000円に遺言加算11,000円がプラスされ、総額は57,000円、というのが一つの目安になります。正確な費用は、打ち合わせの際に公証人が計算してくれますので、事前に確認しておくと安心です。



ここまで読み進めていただき、ありがとうございます!公正証書遺言の基本は掴めてきましたか?特に費用や証人の話は、皆さんつまずきやすいポイントです。でも、一つ一つ手順を踏めば決して難しくはありません。ここからは、さらに一歩進んで、実際に起こりうるトラブルや、亡くなった後の手続きについて深掘りしていきましょう。
遺言書公正証書作り方と注意点【死後とトラブル】


公正証書遺言があってももめるケースとは
「公正証書遺言さえ作っておけば、相続は万全!」と思いたいところですが、残念ながら、もめるリスクをゼロにすることはできません。遺言書の内容によっては、かえって争いの火種になってしまうケースもあるのです。
特にもめやすいのが、「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害しているケースです。
【事実】相続トラブルは他人事ではない?遺産分割事件の現状
最高裁判所の司法統計によれば、2022年度に全国の家庭裁判所で新たに受け付けられた遺産分割事件(調停および審判)の数は約1万2,000件に上ります。
特に、相続財産が5,000万円以下の事件が全体の75%以上を占めており、「うちは財産が少ないから大丈夫」とは言えないのが実情です。遺言書があっても、特定の人に財産が偏るなど内容に配慮が欠けていると、遺留分を巡る争いに発展しやすくなります。
遺留分とは?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者や子など)に法律で保障された、最低限の遺産の取り分のことです。例えば、「愛人に全財産を譲る」といった遺言は作成できますが、残された配偶者や子は、自身の遺留分にあたる金額を愛人に対して請求(遺留分侵害額請求)することができます。
この遺留分を無視した遺産分割の内容になっていると、財産をもらえなかった相続人が不満を持ち、後から金銭の支払いを求める裁判に発展する可能性があります。
他にも、特定の子どもにだけ著しく多くの財産を渡すなど、相続人の間で不公平感を生む内容は、感情的なしこりを残し、家族関係を悪化させる原因になりかねません。遺言を作成する際は、法的な効力だけでなく、残されるご家族の気持ちにも配慮することが、本当の意味での「円満相続」につながります。
公正証書遺言が無効になる場合を解説
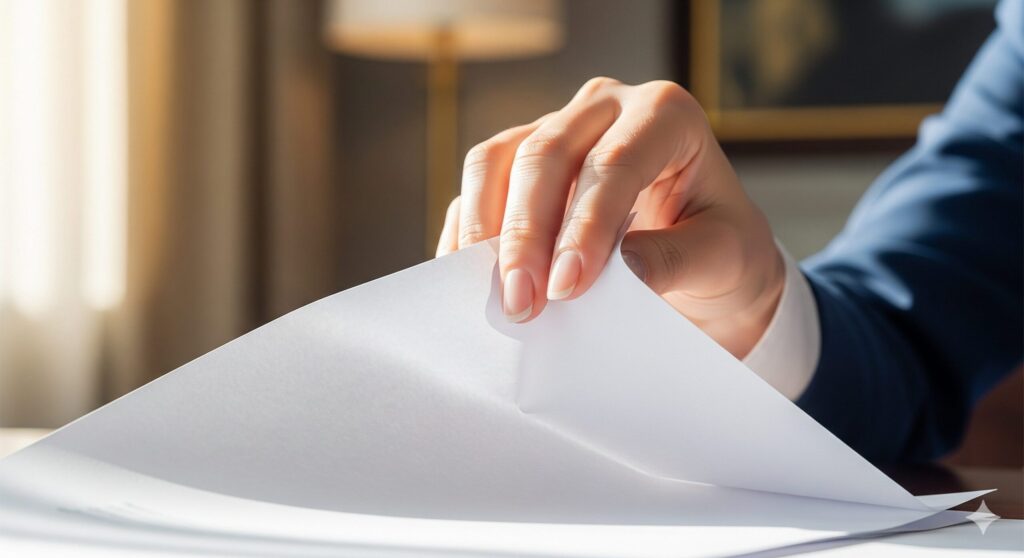
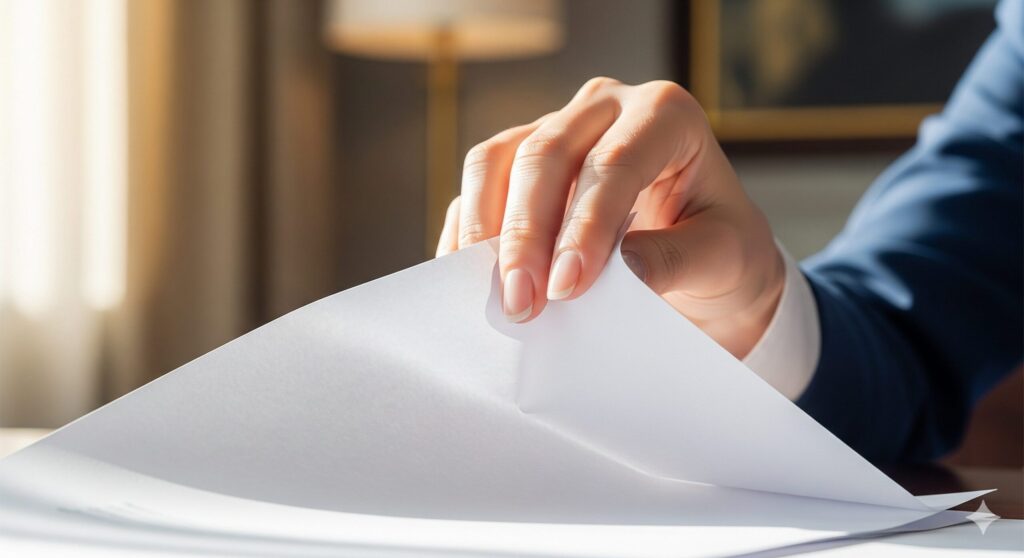
公正証書遺言は無効になりにくい、と説明しましたが、可能性が全くないわけではありません。いくつかのケースでは、せっかく作成した遺言が無効と判断されてしまうことがあります。
最も多い原因は、「遺言能力の欠如」です。
遺言能力とは?
遺言能力とは、「自分が作成する遺言の内容や、それによってどのような法的な結果が生じるのかを、正しく理解・判断できる能力」のことです。認知症が進行しているなど、この遺言能力がない状態で作成された遺言は、たとえ公正証書であっても無効になります。(民法第963条)
公証人も面談の際に遺言者の意思能力を確認しますが、後から他の相続人が「あの時、父はもう正常な判断ができなかったはずだ」と主張し、裁判で争われることがあります。そうした事態を避けるため、もしご高齢の方や病気の方が遺言を作成する際には、事前に医師の診断書を取得しておくといった対策が有効になる場合があります。
前述の通り、証人が欠格者であった場合も無効の原因となります。また、遺言の内容が公序良俗に反する(例えば、犯罪行為を条件に財産を渡すなど)場合も無効です。専門家に相談しながら作成を進めることで、こうしたリスクを大きく減らすことができます。
死亡したら?公正証書遺言の死後の手続き
遺言者が亡くなり、相続が開始された後、公正証書遺言に基づいて手続きを進めることになります。自筆証書遺言(法務局保管制度を利用していないもの)と違い、家庭裁判所での「検認」が不要なため、比較的スムーズに手続きを始めることができます。
死後の大まかな流れ
- 遺言書の正本(または謄本)の確認:通常、遺言書の正本は遺言者が保管しています。まずはそれを探し出します。もし見つからない場合でも、原本は公証役場にあるため、相続人は公証役場で謄本を再発行してもらえます。
- 遺言執行者の選任(指定がある場合):遺言書で「遺言執行者」が指定されていれば、その人が中心となって手続きを進めます。遺言執行者は、預金の解約や不動産の名義変更など、遺言の内容を実現するための権限を持ちます。こうした手続きは死後事務委任とも関連が深いです。
- 相続人・財産の調査確定:遺言書の内容と照らし合わせながら、戸籍謄本を取り寄せて相続人を確定させ、財産の詳細なリスト(財産目録)を作成します。
- 遺産分割の実行:遺言書の内容に従って、預貯金の解約・分配や、不動産の相続登記(名義変更)など、具体的な遺産分割手続きを行います。
- 相続税の申告・納付:相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税が必要です。
特に不動産の名義変更(相続登記)は、司法書士などの専門家への依頼が必要になることが一般的です。遺言執行者が指定されていない場合は、相続人全員で協力して手続きを進めることになります。
公正証書遺言についてよくあるご質問FAQ


公正証書遺言は死亡後に通知される?
これは多くの方が勘違いされているポイントですが、遺言者が亡くなったからといって、公証役場から相続人に対して「遺言書が保管されていますよ」といった通知が自動的に来ることはありません。
遺言書の存在や保管場所を相続人が知らなければ、せっかく作成した遺言が誰にも発見されないままになってしまう恐れもあります。そのため、作成した事実は、信頼できる家族の誰か一人に伝えておくか、遺言執行者に指定した専門家などに正本を預けておくといった対策が重要になります。
もし、遺言書の正本や謄本が見つからず、公正証書遺言を作成した可能性がある、という場合には、相続人は近くの公証役場で「遺言検索システム」を利用することができます。これにより、平成元年以降に作成されたものであれば、全国どこの公証役場で遺言が保管されているかを調べることが可能です。
公正証書遺言の内容は誰が見れるのか


公正証書遺言は重要な個人情報ですので、誰でも自由に見ることができるわけではありません。その内容を閲覧したり、謄本の交付を請求したりできる人は限られています。
閲覧・謄本交付を請求できる人
- 遺言者が生きている間:遺言者本人のみです。たとえ家族であっても、本人の委任状がなければ内容を見ることはできません。
- 遺言者が亡くなった後:相続人や受遺者、遺言執行者などの利害関係者に限られます。請求する際には、自分が利害関係者であることを証明するために、戸籍謄本や本人確認書類などが必要になります。
このように、プライバシーは厳重に守られています。亡くなった後に利害関係者が公証役場へ行けば、手続きを経て内容を確認することができる、と覚えておきましょう。
遺言書公正証書作り方と注意点の総まとめ
最後に、この記事の要点をリスト形式でまとめます。円満な相続の実現に向けて、大切なポイントをもう一度確認しておきましょう。
終活・相続・不動産相続の専門家カズです。最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。たくさんの情報がありましたが、一番大切なのは「残される家族を想う気持ち」です。公正証書遺言は、その気持ちを形にするための、とても有効なツールなのです。この記事が、あなたと大切なご家族の『円満な相続』の一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
- 公正証書遺言は公証人が作成に関与する信頼性の高い遺言
- 原本が公証役場に保管され偽造や紛失のリスクが低い
- 家庭裁判所の検認が不要で相続手続きがスムーズに進む
- 作成手順は自分で主導することも専門家への依頼も可能
- 作成には戸籍謄本や財産資料など多くの書類が必要になる
- 立ち会いには利害関係のない証人2名が必須
- 証人になれない人が立ち会うと遺言が無効になる場合がある
- 費用は財産額に応じて変動し公証人手数料令で定められている
- 遺留分を侵害する内容は後々の相続トラブルの原因になりやすい
- 遺言能力がない状態で作成されると無効になる可能性がある
- 遺言者が亡くなっても公証役場から自動で通知は来ない
- 相続人は遺言検索システムで遺言の有無を調査できる
- 遺言の内容は生前は本人のみ死後は利害関係者のみ閲覧可能
- 遺言の内容はいつでも新しい遺言で変更や撤回ができる
- 作成にあたり不安な点があれば弁護士など専門家への相談がおすすめ
▼あわせて読みたい関連記事▼