
こんにちは!終活・相続の専門家、カズです。生前贈与、気になりますよね。「うちもそろそろ…」なんて考えてはみるものの、相続ブログ体験談なんかを読むと、生前贈与で揉めるケースや遺産相続トラブルで兄弟の仲にヒビが入った事例もあって、正直ちょっと怖い…なんて思っていませんか?
特に、年間110万円の非課税枠のことは知っていても、生前贈与の対象者は誰までOK?とか、贈与が110万円を超える場合や複数人へ渡すときの確定申告はどうするの?なんて具体的な疑問が次々出てきますよね。
さらに、定期贈与とは何か、親子で500万円もらったら贈与税はかかるのか、そもそも生前贈与はなぜバレるのか…なんて考え出すと、もう頭がパンクしそう!なんてことも。
2024年から始まった生前贈与の7年ルールや、110万円の贈与が廃止されるのはいつから?2025年に制度はどうなる?といった最新情報も追いかけないといけません。
今回は、そんなあなたのモヤモヤを吹き飛ばすために、僕が実際に見てきた成功例を基に、賢い生前贈与の進め方を徹底解説します!
- 生前贈与の基本的なルールと非課税制度
- 贈与が税務署に把握される仕組みと対策
- 家族間でトラブルになりやすいケースとその回避法
- 2024年以降の税制改正の重要ポイント
 コンサルタント @KAZU
コンサルタント @KAZU生前贈与は、単なる節税対策ではありません。大切な家族へ「想い」を円満に繋ぐための素晴らしい方法です。しかし、やり方を一つ間違えると、かえって家族の絆を壊す原因にもなりかねません。この記事では、僕が15年以上の実務で見てきたリアルな体験談を交え、成功の秘訣と失敗しないための注意点を具体的にお伝えしますね。
生前贈与体験談成功例から学ぶ基礎知識


生前贈与110万円の対象者は誰か
「そもそも、110万円の非課税枠って誰にでも使えるの?」これ、本当によく聞かれる質問です。結論から言うと、生前贈与の110万円の非課税枠(暦年贈与といいます)は、贈与する相手に制限がありません。つまり、自分の子どもや孫はもちろん、お世話になった友人や内縁の妻など、誰に対しても活用することができます。
僕のお客様で、お子さんがいないご夫婦がいらっしゃいました。その方は、長年可愛がってきた甥っ子さんと姪っ子さんに、毎年少しずつ財産を渡したいと考えていたのです。
この制度を使い、毎年110万円ずつ贈与を続けた結果、10年間で合計2,200万円もの財産を非課税でスムーズに渡すことができました。これは立派な成功体験ですよね。
ただし、注意点が一つ。この非課税枠は、「もらった側」の合計金額で計算されるという点です。例えば、あなたが父親から110万円、母親から110万円を同じ年にもらった場合、合計で220万円受け取ったことになります。この場合、基礎控除110万円を超えた110万円分に対して贈与税がかかってくるのです。この点を勘違いされている方は意外と多いので、気をつけてくださいね。
ポイント
110万円の非課税枠は、贈与する相手を選びません。ただし、非課税かどうかは「財産をもらった人」が「1年間(1月1日~12月31日)に受け取った合計額」で判断されます。
110万円の贈与を複数人へ行う方法


「じゃあ、子ども3人にそれぞれ110万円ずつ贈与するのはアリ?」もちろんです!これも非常に有効な相続対策になります。
前述の通り、非課税枠は「もらった人一人ひとり」にかかるもの。ですから、子ども3人にそれぞれ110万円ずつ、合計330万円を贈与しても、受け取った側はそれぞれ110万円の枠内なので贈与税はかからない、というわけです。
実際に、僕が担当したある会社の経営者の方は、この方法をうまく活用されていました。ご自身の財産を早めに次世代へ移したいという想いから、3人のお子さんと、その配偶者、そして5人のお孫さん、合計11人に毎年100万円ずつ贈与を続けました。年間で1,100万円もの財産が非課税で動くわけです。これを5年間続けただけで、相続財産を5,500万円も圧縮できたのですから、その効果は絶大ですよね。
この方法を成功させるコツは、贈与の証拠をしっかり残すことです。具体的には、面倒でも毎年「贈与契約書」を作成し、贈与は必ず銀行振込で行うことをお勧めします。手渡しだと、後から税務署に「それは本当に贈与ですか?」と指摘されたときに証明が難しくなってしまいますからね。
名義預金と見なされない定期贈与とは
「毎年同じ日に同じ金額を贈与すると、『定期贈与』とみなされて税金がかかるって聞いたけど…」このウワサ、半分ホントで半分ウソ、といったところでしょうか。正確に理解することが大切です。
税務署が問題視するのは、「最初から合計1,000万円を贈与する約束があって、それを毎年100万円ずつ10年間に分割して払っているだけ」と判断されるケースです。これを「連年贈与」または「定期贈与」と呼び、約束した総額(この場合1,000万円)に対してドカンと贈与税が課せられる可能性があります。
これを避けるための対策は、「毎年、新たに贈与の意思決定をした」という事実を作ることです。
定期贈与と見なされないための工夫
- 毎年、贈与契約書を作成する
- 贈与する日付や金額を毎年少し変える(例:去年は110万円、今年は105万円など)
- 誕生祝いや結婚記念日など、贈与の目的を明確にする
- あえて110万円を超す金額(例:111万円)を贈与し、少額の贈与税申告を行う
また、よくある失敗談として「孫のために」と、親が子どもの名義で勝手に口座を作って入金しているケースがあります。これは「名義預金」と判断され、贈与とは認められません。あくまでも、お子さんやお孫さん自身が管理・使用できる状態にしておくことが必要です。通帳や印鑑は、財産をもらった本人が管理するようにしましょう。
110万円贈与で確定申告は必要か
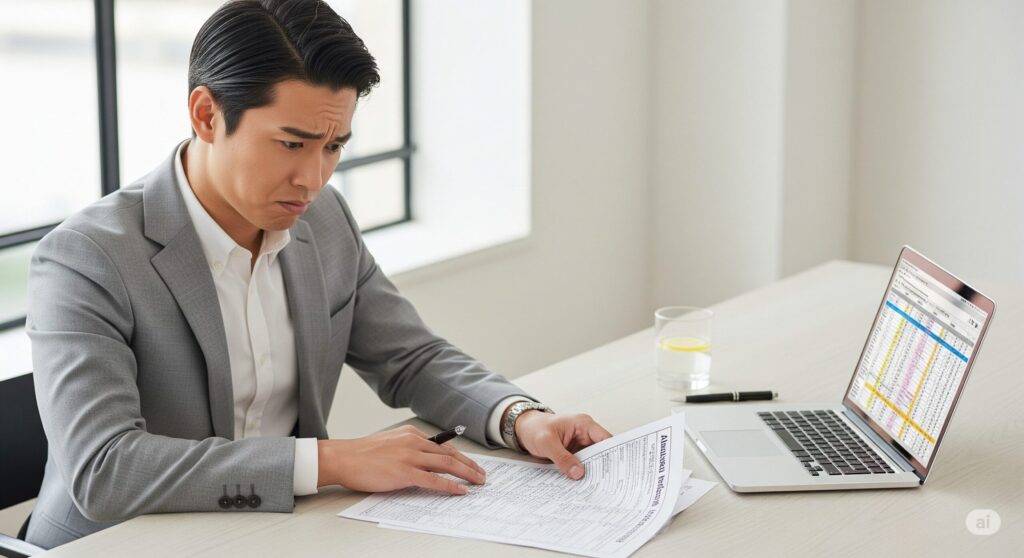
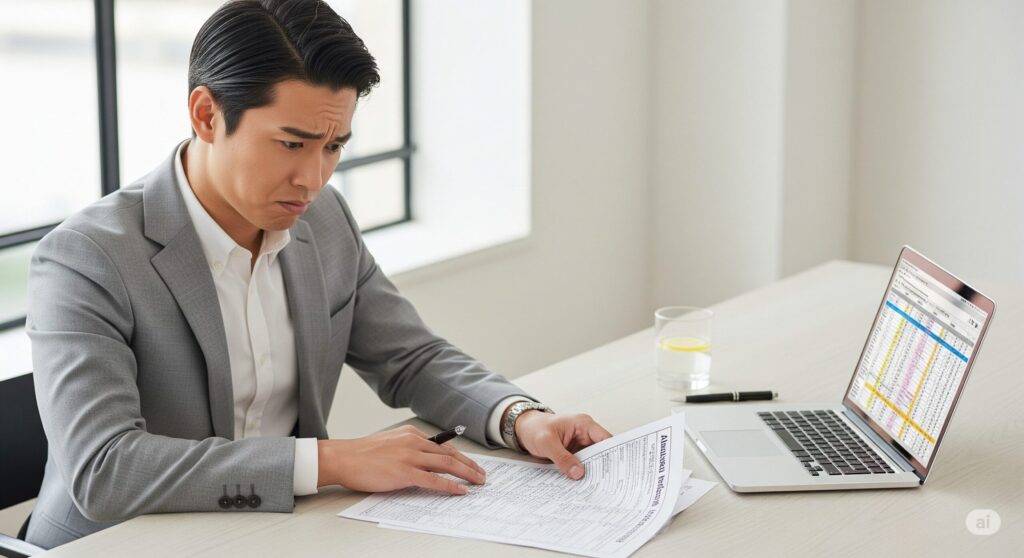
年間110万円「以内」の贈与であれば、贈与税の申告も納税も一切必要ありません。これが暦年贈与の最大のメリットと言えます。手続きが簡単なため、多くの方が相続対策の第一歩として活用しています。
例えば、僕の友人A君は、数年前に実家を建てる際、ご両親から資金援助を受けました。その際、お父さんから110万円、お母さんから110万円の贈与を受ける計画を立てていました。
しかし、前述の通り、これはA君が合計220万円を受け取ったことになるため、申告が必要です。幸い、事前に僕に相談してくれたので、「A君が110万円、奥さんが110万円をそれぞれもらう形にしては?」とアドバイスしました。これなら夫婦それぞれが110万円の枠内に収まるため、申告は不要になります。
ただし、不動産や株式など、現金以外の財産を贈与する場合は注意が必要です。その財産の「評価額」が110万円を超えるかどうかを正確に把握しないといけません。
▼あわせて読みたい▼
不動産名義変更相続で損しないための注意点と費用相場を解説
豆知識:申告が必要な特例制度
住宅取得資金の贈与や教育資金の一括贈与など、110万円を超えても非課税になる特例制度があります。これらの特例を活用する場合は、たとえ納税額がゼロでも税務署への申告手続きが必須となりますので、忘れないようにしましょう。
親子で500万円もらったら贈与税はかかる?
はい、これは明確に贈与税がかかります。先ほどからお伝えしている通り、贈与税の基礎控除は年間110万円までです。
例えば、父親から500万円の贈与を受けた場合、計算は以下のようになります。
| 課税価格 | 500万円 – 110万円(基礎控除) = 390万円 |
|---|---|
| 税率(特例贈与※) | 15% |
| 控除額 | 10万円 |
| 贈与税額 | 390万円 × 15% – 10万円 = 48.5万円 |
※特例贈与:親や祖父母など直系尊属からの贈与の場合に適用される税率です。
「え、結構な金額になるんだな…」と思われたかもしれませんね。しかし、これを将来の相続税と比較してみることが重要です。将来、多額の相続税が見込まれる方の場合、あえて贈与税を払ってでも生前に財産を移した方が、トータルの税負担が軽くなるケースがあるのです。
この判断は非常に専門的になるため、ご自身の財産状況を税理士などの専門家に見てもらい、シミュレーションしてみるのが一番確実な方法です。
▼あわせて読みたい▼
相続税計算の基本と節税のコツを図解で徹底解説



ちなみに、「相続時精算課税制度」という選択肢もあります。これは2,500万円まで贈与税がかからずに贈与できる制度ですが、その分、相続が発生した時にその贈与財産を相続財産に足して相続税を計算するという仕組みです。メリット・デメリットがあるので、これも専門家と相談しながら慎重に検討したい制度ですね。
生前贈与はなぜ税務署にバレるのか
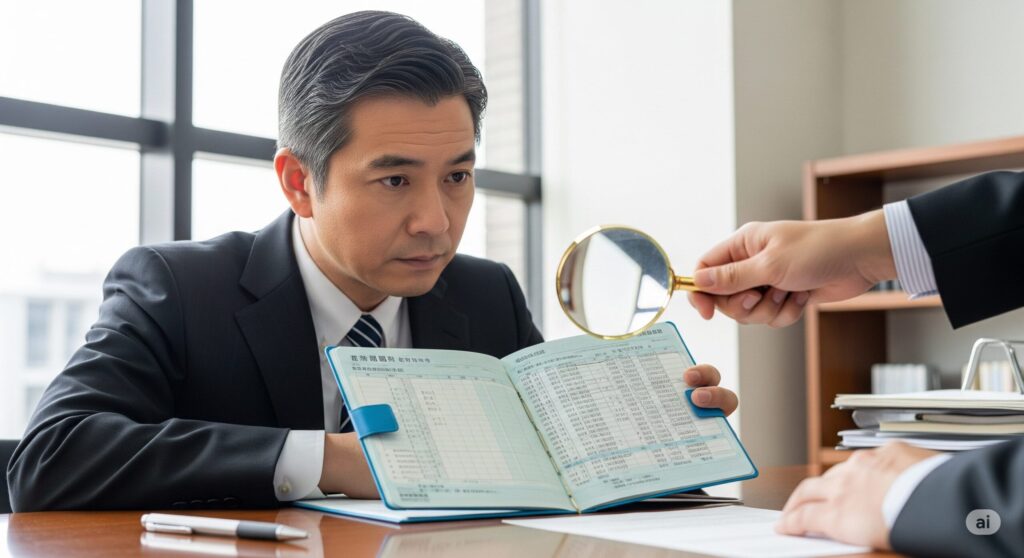
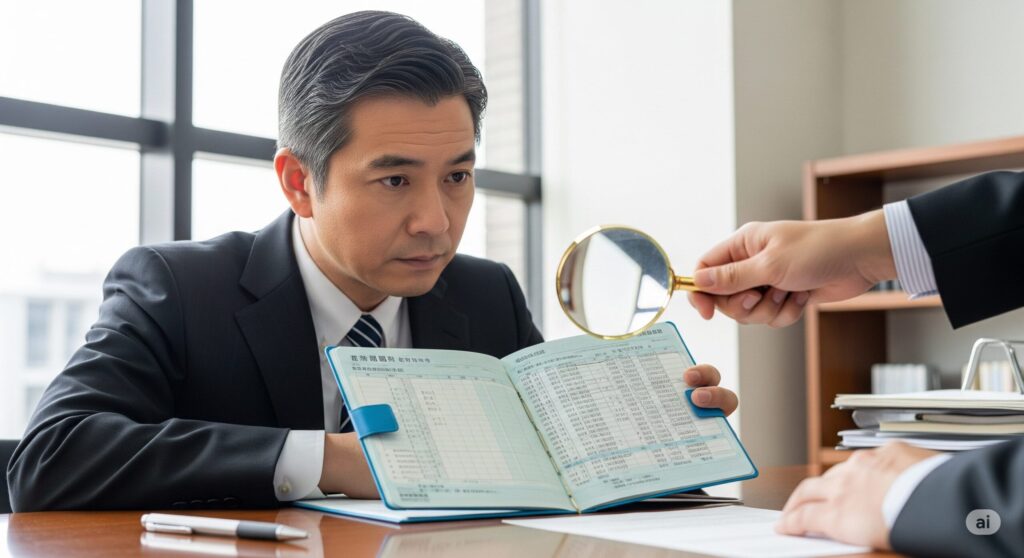
「黙っていればバレないんじゃないの…?」こう考える方が後を絶ちませんが、その考えは非常に危険です。結論から言うと、税務署は高い確率で無申告の贈与を見つけ出します。
では、なぜバレるのでしょうか?主な理由は以下の3つです。
- 相続発生時の財産調査(K S Kシステム)
人が亡くなると、税務署は相続税の調査のため、亡くなった方(被相続人)とその家族の過去10年分のお金の流れを徹底的に調べます。国税庁の「K S K(国税総合管理)システム」というデータベースには、私たちの納税情報や財産情報が集約されており、不自然なお金の動きはすぐに分かってしまうのです。 - 不動産の登記情報
土地や建物を贈与した場合、必ず法務局で名義変更(所有権移転登記)を行います。この登記情報は税務署にも共有されるため、誰から誰へ不動産が移ったかは筒抜けです。 - 支払調書
生命保険の満期金や解約返戻金など、保険会社から個人へ100万円を超える支払いがあった場合、保険会社は税務署へ「支払調書」を提出する義務があります。この情報から、贈与の事実が発覚するケースもあります。
僕のお客様の体験談ですが、亡くなったお父様が内緒でお孫さん名義の口座にコツコツ500万円を貯めていたことが、相続税調査で発覚しました。これは典型的な「名義預金」と判断され、お孫さんへの贈与ではなくお父様の相続財産として扱われ、結果的に追徴課税を支払うことになりました。善意から始めたことでも、正しい知識がないと、かえって家族に迷惑をかけてしまう可能性があるのです。
【事実】税務署は贈与を見逃さない:国税庁の調査実績
「少しくらいならバレないだろう」という考えは非常に危険です。国税庁が公表した「令和4事務年度における相続税の調査等の状況」によると、贈与税の実地調査件数は1,911件あり、そのうち87.8%にあたる1,678件で申告漏れが指摘されています。
追徴税額は合計で233億円にのぼり、1件あたりの追徴税額は過去最高の1,232万円となりました。税務署はKSK(国税総合管理)システムなどを用いて個人の資産情報を一元管理しており、不自然なお金の動きは相続発生時などに高い確率で把握されるのが実情です。
参考情報サイト: 国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm



ここまで生前贈与の基本を見てきました。110万円の枠を上手に使うこと、そして贈与の証拠をしっかり残すことが成功の第一歩です。特に「バレないだろう」という安易な考えは禁物。税務署の調査能力を侮ってはいけません。正しい知識を身につけ、ルールに則って行うことが、円満な資産承継に繋がりますよ。
生前贈与体験談成功例に学ぶ注意点


生前贈与が原因で揉めるケースとは
円満な相続のための生前贈与が、なぜ家族間のトラブル、いわゆる「争族」の火種になってしまうのでしょうか。僕がこれまで見てきた中で、特に揉めやすいのは以下の3つのケースです。
【事実】遺産分割トラブルの約4割が生前の贈与に起因
生前の不公平な贈与が、家族間の深刻な対立(争族)に発展するケースは少なくありません。裁判所が公表している司法統計「令和4年度 遺産分割事件のうち認容・調停成立件数—動機別」によると、遺産分割で揉めた動機として「特別受益(生前の贈与)の有無や評価」を挙げたケースは全体の約40%にのぼります。
これは、「遺産の範囲」や「使い込み」といった他の動機を大きく上回る数字です。このデータは、一部の相続人だけへの生前贈与が、いかに他の相続人の不満を招きやすいかを客観的に示しています。
生前贈与で揉める典型的な3つのパターン
- 「不公平感」による対立
「兄さんだけ親から援助してもらってズルい」「妹は住宅資金をもらったのに、私は何ももらっていない」といった不公平感が、積もり積もって相続時に爆発するケースです。贈与の事実を他の兄弟が知らなかった場合、不信感はさらに増大します。 - 「特別受益」の主張
特定の相続人だけが生前に多額の贈与(マイホーム資金や事業資金など)を受けていた場合、それは「遺産の前渡し(特別受益)」と見なされます。相続が発生した際、他の相続人から「前渡し分を差し引いて遺産分割すべきだ」と主張され、激しい対立に発展することがあります。 - 親の介護負担との兼ね合い
「親の介護を一身に引き受けた長女」と「遠方で何もしなかったが、生前に贈与は受けていた長男」のようなケースです。介護をした側は「これだけ尽くしたのだから多くもらう権利がある(寄与分)」と主張し、もらった側は「贈与と介護は別の話だ」と反論し、泥沼化することが少なくありません。
対策として最も重要なのは、親が元気なうちに家族全員でオープンに話し合うことです。なぜその子に贈与をするのか、その理由や想いをきちんと全員に伝えるだけで、他の家族の納得感は大きく変わります。また、その話し合いの内容を残しておくことも、後のトラブル防止に非常に有効な方法です。
▼あわせて読みたい▼
終活しない親との向き合い方|専門家がその理由と対策を解説
エンディングノート書き方完全ガイド|家族に伝わる残し方
遺産相続トラブルでよくある兄弟の事例


ここでは、僕が実際に相談を受けた、生前贈与が絡んだ兄弟間のトラブル事例をご紹介します。
事例:長男への不動産贈与が招いた亀裂
相談に来られたのは次男のBさん。お父様が亡くなり相続手続きを進める中で、数年前にご実家の土地と建物(評価額3,000万円)が、お父様から長男のAさんに生前贈与されていたことが発覚しました。Bさんはその事実を全く知らされていませんでした。
残された遺産は預貯金500万円のみ。長男Aさんは「遺産は法定相続分通り、250万円ずつ分けよう」と提案しましたが、Bさんは納得できません。「兄さんは既に3,000万円分の財産をもらっているじゃないか!不公平だ!」と主張しました。これはまさに「特別受益」が問題となったケースです。
最終的に、この兄弟は家庭裁判所での調停にまで発展しました。結果として、生前贈与された3,000万円を「みなし相続財産」として遺産総額に加算し(3,000万円+500万円=3,500万円)、そこから法定相続分を計算。
長男Aさんの取り分は既に贈与で超えているため、預貯金500万円は全て次男Bさんが相続することで決着しました。しかし、この一件で兄弟の心には深い溝ができてしまいました。
この事例の最大の失敗点は、お父様が一部の子どもにだけ内緒で多額の贈与をしてしまったことです。もしお父様が「長男が家を継ぐから」といった理由を、きちんとBさんにも説明し、理解を得ていれば、ここまでこじれることはなかったかもしれません。
また、Bさんの取り分について配慮した内容の遺言書を用意しておくべきでした。
生前贈与7年ルールと110万円の関係
2024年1月1日から、相続税のルールが大きく変わりました。これが、いわゆる「生前贈与の7年ルール」です。
これまで、亡くなる前「3年以内」に行われた贈与は、相続財産に持ち戻して相続税を計算するというルールでした。それが、2024年からは「7年以内」に延長されたのです。
「え、じゃあ110万円の非課税贈与も7年分さかのぼって相続税がかかるの?」と不安になりますよね。その通りです。年間110万円以内の贈与であっても、亡くなる前7年以内に行われたものは、相続財産に加算されてしまうのです。
7年ルールのポイント
- 対象となるのは2024年1月1日以降の贈与から。
- 亡くなる前7年以内の贈与が相続財産に加算される。
- ただし、延長された4年分(亡くなる3年前~7年前)については、合計100万円までは加算しなくてよいという控除があります。
- このルールは、あくまで「相続税」の計算上の話。贈与した時点で110万円以内であれば「贈与税」はかかりません。
この改正の意図は、「駆け込み贈与」による過度な節税を防ぐことにあります。つまり、国としては「相続対策は、より早く、計画的に始めなさい」というメッセージを送っているわけですね。このルール変更は非常に重要なので、生前贈与を検討している方は必ず覚えておいてください。
2025年以降の生前贈与はどうなる?


「7年ルールが始まったし、110万円の暦年贈与自体が廃止されるって本当?」というご質問も増えています。現時点(2025年8月時点)では、110万円の暦年贈与がすぐに廃止されるという決定はありません。
ただし、近年の税制改正の流れを見ると、国が「暦年課税」から「相続時精算課税」へ、つまり「資産の世代間移転をより早期に、まとめて行わせたい」という方向に舵を切っているのは明らかです。7年ルールへの延長もその一環と考えられます。
僕たち専門家の間では、今後、暦年贈与の非課税枠が縮小されたり、将来的には相続時精算課税制度に一本化されたりする可能性も議論されています。2025年以降の税制改正で、さらに大きな変更が加えられることも十分に考えられます。
【事実】7年ルール改正の背景にある国の意図
2024年から生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長された背景には、国の明確な意図があります。財務省が公表した「令和5年度税制改正の大綱」では、この改正の目的を「資産の再分配機能の確保」と「資産の早期の世代間移転の促進」としています。
これは、富裕層が亡くなる直前の「駆け込み贈与」によって過度に相続税負担を回避するのを防ぎつつ、若年世代へより早い段階で資産を移転させることを促すための措置です。
国は、年間110万円の暦年贈与をコツコツ続ける節税策よりも、相続時精算課税制度などを活用した、よりまとまった形での早期の資産移転を推奨する方向へ舵を切っていると言えます。
(出典:財務省「令和5年度税制改正の大綱」)



だからこそ、「いつかやろう」ではなく「今すぐ始める」ことが大切なんです。ルールが変わる前に、現行制度のメリットを最大限に活用して計画的に対策を進める。これが、これからの賢い相続対策のスタンダードになっていくはずですよ。
生前贈与に関するよくある質問(FAQ)
▼あわせて読みたい▼
終活いつから始めるメリット満載!専門家が年代別に解説
総括:生前贈与体験談成功例のポイント
これまで解説してきた内容をまとめます。成功する生前贈与には、共通するポイントがあります。以下のリストで最終確認してみましょう。
- 生前贈与は相続税対策として非常に有効な手段である
- 年間110万円の非課税枠は贈与相手を選ばずに活用できる
- 非課税枠は「もらった人」の年間の合計額で判断される
- 複数人へそれぞれ110万円ずつ贈与する方法は節税効果が高い
- 贈与の証拠として「贈与契約書」を作成し銀行振込で行うことが重要
- 毎年同じ日・同額の贈与は「定期贈与」と見なされるリスクがある
- 子ども名義でも親が管理する口座は「名義預金」と判断される
- 年間110万円以内の贈与なら確定申告は不要
- 110万円を超えても非課税になる特例制度は申告が必須
- 税務署は相続時に過去のお金の流れを徹底的に調査する
- 一部の子どもだけに内緒で贈与すると深刻な家族トラブルの原因になる
- 生前贈与については家族全員でオープンに話し合うことが最も大切
- 2024年から贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長された
- 7年ルールを意識し、より早期から計画的に対策を始める必要がある
- 現行制度を最大限活用するためにも専門家への相談が成功への近道となる



いかがでしたか?生前贈与は、正しい知識を持って計画的に行えば、家族の未来にとって大きなプラスになります。大切なのは、家族としっかりコミュニケーションを取ること。そして、分からないことは一人で悩まず、僕のような専門家を頼ることです。あなたの家族の「想い」が円満に繋がるよう、心から応援しています!
▼あわせて読みたい関連記事▼












