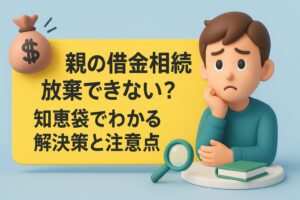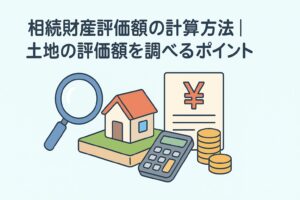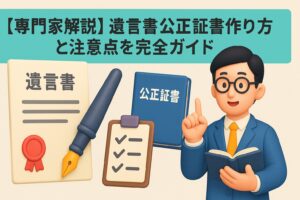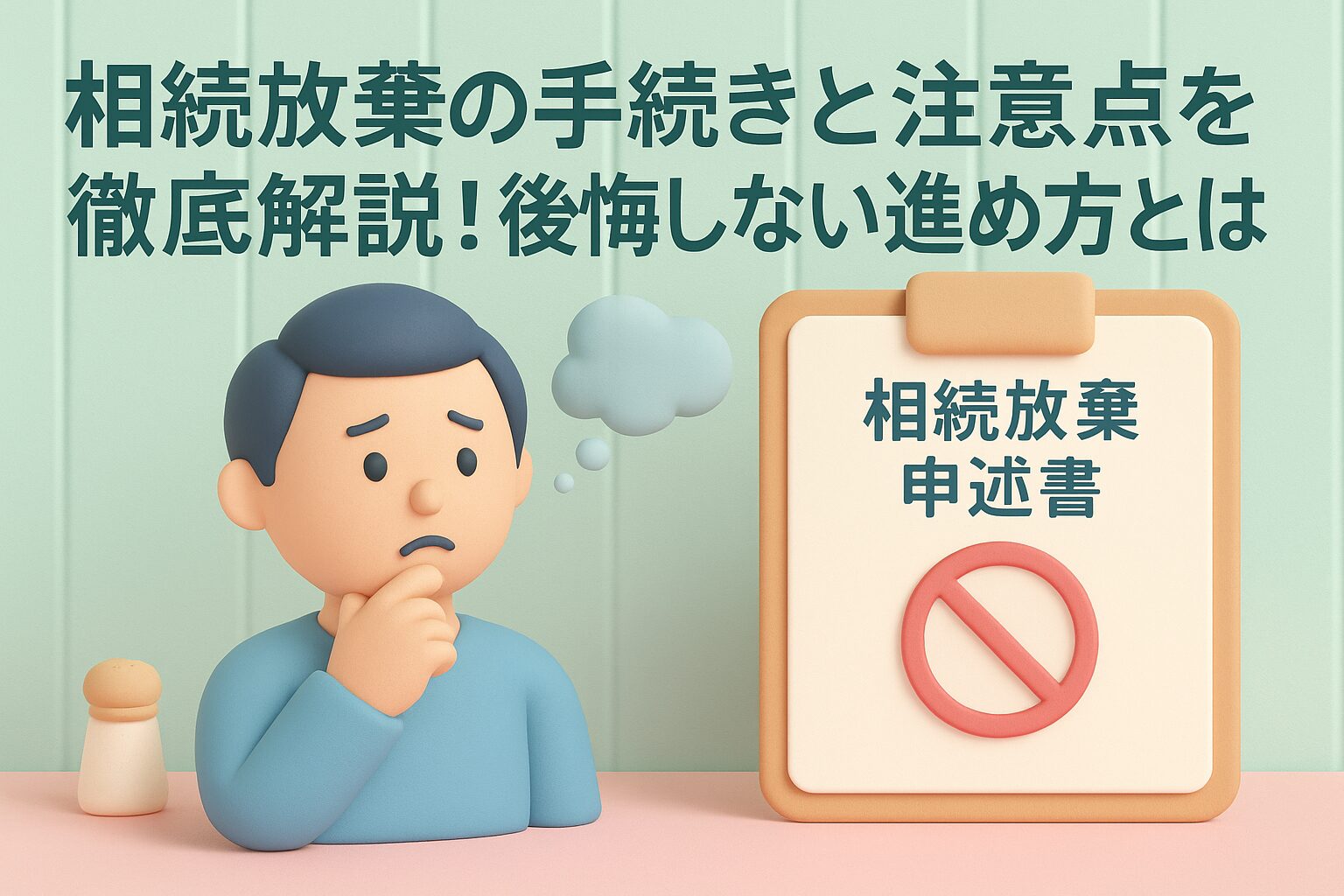
「まさか自分が相続人になるなんて…しかも借金があるみたいなんです。」
「突然のことで何から手をつけていいか分からないし、相続放棄って聞くけど、手続きとか必要書類とか、一体どうすればいいの?」
相続は、誰もが直面する可能性がある問題ですよね。特に被相続人の方が残した借金や負債のほうが多いと分かったとき、頭の中はパニックになってしまいます。
相続放棄する前にやってはいけないことは何なのか、手続きや必要書類、費用、はたまた相続放棄 遺品整理でバレるなんて話も耳にするし、いったい誰に相談すればいいのか分からなくなりますよね。
実は、相続放棄の手続きは、自分で進めることも十分に可能です。また、相続放棄 兄弟など、関係者全員で手続きを進める必要があるケースもあります。この手続きには、相続放棄 申述書という特定の書類を家庭裁判所へ提出する必要があり、期間や費用も決まっています。
この記事を読めば、相続放棄 できないケースを含め、相続放棄の全容を理解でき、もう「どうしよう…」と悩むことはなくなるでしょう。専門家である私の体験談も交えながら、皆さんが抱える不安や疑問を一つずつ解消していきますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
- 相続放棄のメリット・デメリットと手続きの流れ
- 家庭裁判所での手続き方法と必要書類
- 相続放棄にかかる費用や期間について
- 相続放棄する前にやってはいけないこと
 コンサルタント @KAZU
コンサルタント @KAZU相続は人生に何度も経験するものではありませんので、突然直面すると不安になるのも当然です。私も多くの方からご相談をいただきますが、特に「相続放棄」は、専門的な手続きが多く、皆さんが最初にぶつかる壁かもしれません。しかし、焦らず一つずつ解決していけば大丈夫です。この知識が皆さんの心の平穏につながることを願っています。
相続放棄の基本と手続きの流れ


まずは、相続放棄の基本を一緒に見ていきましょう。そもそも相続は、亡くなった方が残したプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
そして、相続人がこれら一切の財産を引き継がないと決めることを相続放棄と呼びます。この手続きを行うと、最初から相続人ではなかったものとして扱われることになります。
【事実】年間26万件以上が相続放棄を選択
最高裁判所が公表している「司法統計」によると、令和4年(2022年)の「相続放棄の申述受理件数」は全国で260,494件にのぼり、10年前の平成24年(2012年)の168,144件と比較して約1.5倍に増加しています。
これは、相続放棄が特別な手続きではなく、多くの方が利用している公的な権利であることを示しています。
相続放棄とは?
相続放棄とは、民法で定められた相続人が、被相続人(亡くなった方)の財産を一切引き継がないと決めることです。この手続きをすると、被相続人の借金からも解放されます。逆に、プラスの財産も受け取ることはできなくなります。
これは家庭裁判所への「申述」という手続きを通じて行われます。限定承認と違い、相続人1人だけでも手続きが可能です。私の経験上、これは特に相続人同士の関係が複雑な場合に有効な選択肢となります。例えば、疎遠になっていた親族が相続人として浮上した場合でも、自分の意志で放棄することができるのです。
相続放棄のメリットとデメリット


相続放棄には、メリットとデメリットが両方あります。主なメリットは、なんといっても被相続人の借金や未払いの税金などの負債から解放されることです。これにより、予期せぬトラブルに巻き込まれるリスクを避けられます。
一方で、デメリットとして挙げられるのが、プラスの財産も一切引き継げなくなる点です。例えば、自宅や預貯金など、本来受け取るはずだった財産も全て手放さなければなりません。
また、相続放棄すると、その地位が次の順位の相続人へと移るため、後続の相続人に連絡を入れる必要が出てくる場合もあります。私は以前、被相続人の兄弟姉妹の方が、まさか自分に相続権が回ってくるとは知らず、後々トラブルになったケースを担当しました。
注意
相続放棄は一度受理されると、原則として撤回できません。慎重な判断が必要です。
相続放棄 期間はいつまで?
相続放棄の手続きには、民法で「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と定められています。この期間のことを「熟慮期間」と呼び、この期間内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
もし3か月を過ぎてしまうと、単純承認とみなされ、自動的にすべての財産を相続したことになってしまいます。
ただし、私の経験上、この「3か月」という期間は、被相続人の死亡を知った日だけでなく、「自分が相続人であること」を知った日を起算点とすることが多いです。
例えば、被相続人の死亡から数年経ってから、借金の督促状が届いて初めて自分が相続人だと知った場合、その督促状を受け取ってから3か月以内に手続きをすれば良いと判断されるケースもあります。このあたりの判断は複雑ですので、困ったときは早めに専門家にご相談ください。
参考情報サイト: 裁判所
参考URL:https://www.courts.go.jp/index.html
【事実】3ヶ月の「熟慮期間」は延長できる
民法第915条では、相続放棄の熟慮期間は原則3ヶ月と定められていますが、但し書きで「利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所においてその期間を伸長することができる」と規定されています。
財産の調査に時間がかかるなど、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで、期間を延長することが可能です。
相続放棄 できないケースとは
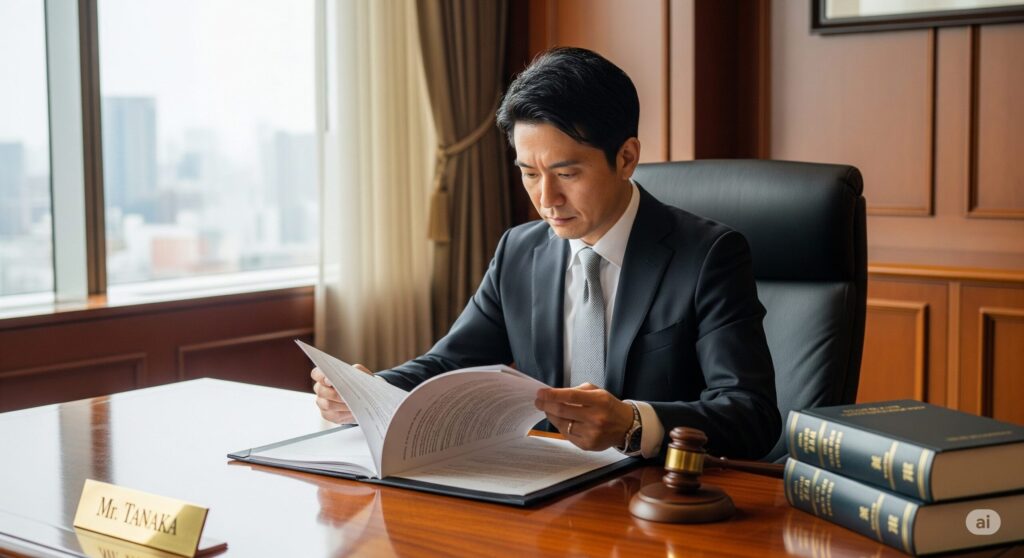
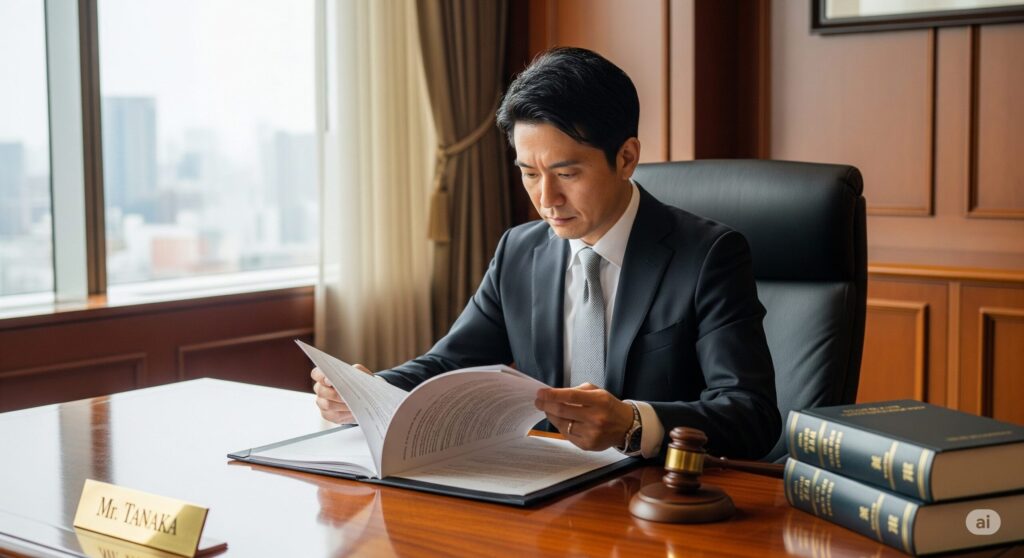
相続放棄は、すべての場合でできるわけではありません。相続放棄 できないと判断されるケースには、主に以下のようなものが挙げられます。
- 相続財産の処分行為があった場合: 預貯金を引き出して使ったり、不動産を売却したりすると、「相続する意思がある」とみなされ、相続放棄はできなくなります。
- 熟慮期間が過ぎてしまった場合: 先述の通り、原則として3か月を過ぎると単純承認したことになります。
- 相続財産を隠したり、不正に消費した場合: 財産を意図的に隠したり、勝手に自分のものにしてしまったりした場合も、放棄は認められません。
特に私がよく耳にするのが、亡くなった方の銀行口座から葬儀費用を支払ったケースです。「葬儀費用だからいいだろう」と安易に考えてしまう方が多いのですが、口座からお金を引き出した時点で「処分行為」とみなされる可能性があります。
たとえ良かれと思ってやったことでも、手続き上はNGになってしまうことがありますので、十分ご注意ください。
相続放棄にかかる費用は?
相続放棄にかかる費用は、主に以下の2つです。
申述人1人あたりにかかる費用
- 収入印紙:800円
- 連絡用郵便切手:数百円〜1,000円程度(家庭裁判所によって異なります)
これはあくまで家庭裁判所に支払う実費です。手続きを司法書士や弁護士に依頼する場合は、別途専門家への報酬が必要となります。相続放棄の手続き自体は、そこまで高額ではありませんが、必要書類である戸籍謄本などを集める際にも費用がかかります。複数の相続人がいる場合、その人数分の費用が必要になります。
相続放棄 遺品整理でバレる?


「相続放棄 遺品整理でバレる」という話を聞いて、不安になる方もいるかもしれません。結論から言うと、遺品整理そのものが相続放棄を阻害するわけではありません。ただし、遺品整理の中で財産価値のあるものを勝手に処分したり、売却したりすると、それは「処分行為」とみなされ、相続放棄が認められない可能性があります。
私の担当したケースで、被相続人の趣味だった高価な骨董品を、価値が分からず捨ててしまい、後でトラブルになった方がいらっしゃいました。後から専門家が見れば、それが「財産の処分」と判断されてしまうこともあります。
そのため、遺品整理をする際は、慎重に、そして財産価値のあるものはむやみに手をつけないことが重要です。



相続放棄の手続きは、家庭裁判所へ申述し、受理されることで完了します。しかし、それ以上に重要なのが「熟慮期間」の3か月をどう過ごすかです。この期間に、相続財産を調査し、放棄するかどうかを判断する必要があります。私もこれまで多くのケースを見てきましたが、慌てて行動して失敗する例が本当に多いんです。冷静に、着実に手続きを進めることが成功の鍵となります。
相続放棄の手続き方法と注意点


ここからは、いよいよ具体的な手続きの方法について解説していきます。専門家に頼まず、相続放棄 手続き 自分で進めたいと考えている方も多いのではないでしょうか。決して難しい手続きではありませんので、ポイントを押さえていきましょう。
知っておきたい!
終活には様々な準備があります。終活の始め方やメリットについて知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてくださいね!
相続放棄 手続きを自分で進めるには
自分で相続放棄の手続きを進める場合、まずは被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所を調べ、必要書類を準備することから始めます。手続きの流れは以下の通りです。
| STEP | 手続き内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 被相続人の死亡と相続開始を知る |
| STEP 2 | 相続財産の調査(借金や負債の確認) |
| STEP 3 | 必要書類の収集(戸籍謄本など) |
| STEP 4 | 家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出 |
| STEP 5 | 家庭裁判所からの照会書に回答 |
| STEP 6 | 相続放棄申述受理通知書を受け取る |
この流れに沿って、着実に進めていくことが大切です。特に、必要書類の収集には時間がかかる場合があるので、早めに行動を開始してください。また、手続きに不安がある場合は、無理をせず、専門家である司法書士や弁護士に依頼することも検討しましょう。
相続放棄 必要書類と戸籍の集め方
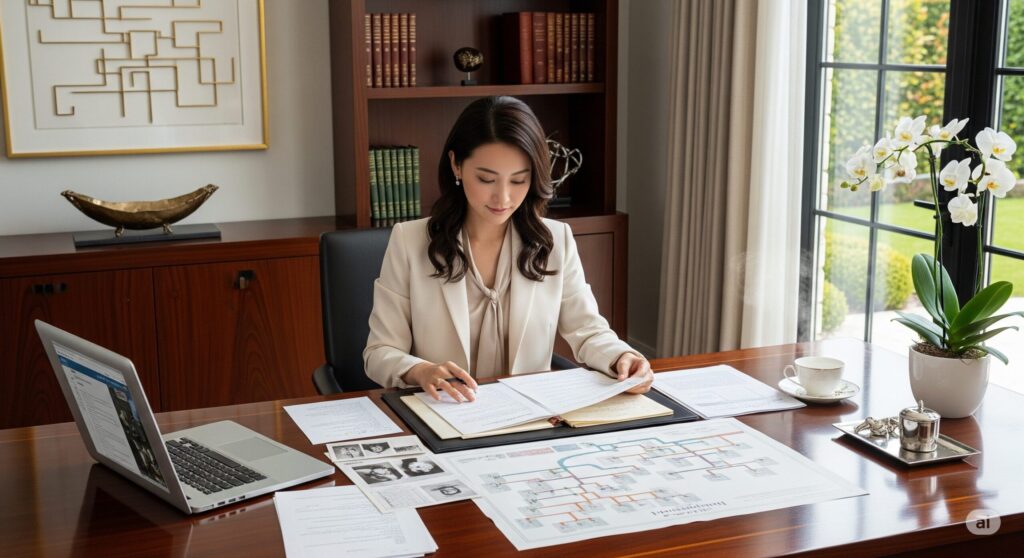
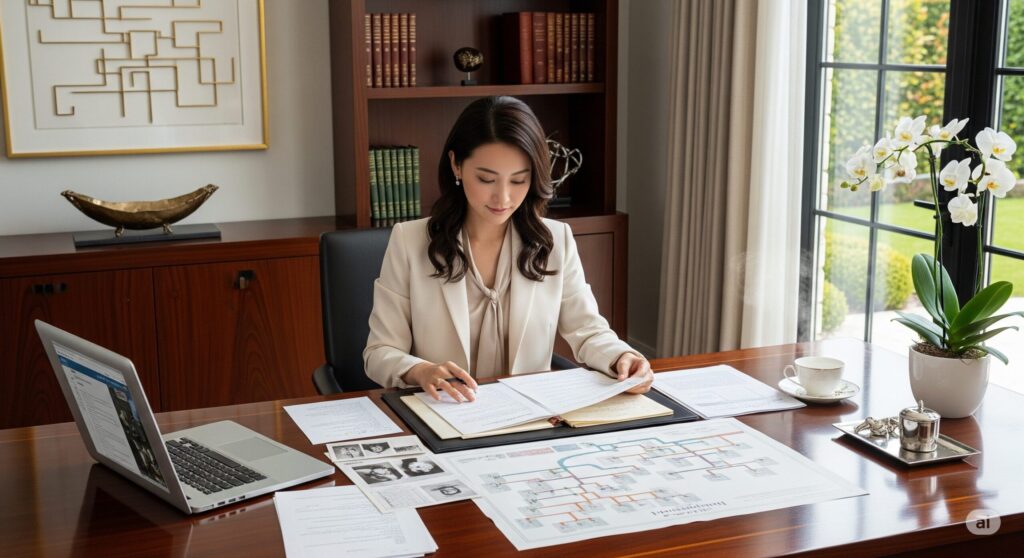
相続放棄の手続きには、様々な必要書類が求められます。中でも重要なのが、被相続人と相続人の関係を証明する戸籍謄本です。相続人の順位によって、必要な戸籍謄本の範囲が変わりますので注意が必要です。
- 配偶者が放棄する場合: 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本など
- 子が放棄する場合: 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本、申述人(子)の戸籍謄本など
- 父母や兄弟姉妹が放棄する場合: 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本など
戸籍謄本は、本籍地の役所で取得できます。また、遠方の場合は郵送での請求も可能です。私のクライアント様で、被相続人の本籍地が遠方で、郵送でのやり取りに数週間かかってしまった方がいらっしゃいました。3か月という期間を考えると、早めに動くことが大切だとお伝えしました。
相続放棄 申述書の書き方
家庭裁判所へ提出する相続放棄 申述書は、裁判所のホームページからダウンロードできます。申述書には、被相続人の氏名や死亡年月日、最後の住所地などを記載します。また、申述に至った理由(借金があるためなど)を具体的に記入する必要があります。
この申述書の内容に不備があると、裁判所から追加書類の提出を求められたり、手続きが長引いたりする原因になります。特に、申述理由については、具体的かつ正直に書くことが大切です。
相続放棄 兄弟も関わる手続き
相続には順位があります。第1順位が子、第2順位が父母、第3順位が兄弟姉妹です。もし第1順位の相続人(子)が相続放棄をすると、相続権は第2順位の父母、そして第3順位の兄弟姉妹へと移ります。そのため、自分が相続放棄をすると、相続放棄 兄弟などの次順位の相続人に影響を与えることになります。
もし、子と父母が全員相続放棄をした場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。このとき、突然借金の督促が来て驚く兄弟姉妹も少なくありません。私が担当したケースでは、相続放棄をしたご依頼者様から、次順位の相続人であるご兄弟にしっかりと連絡をしておくことをお勧めしました。これも一つの親切心ですね。
相続放棄 全員で申し立てるケース
相続人が複数いる場合、全員で手続きをすることも可能です。相続放棄 全員で申述することで、後々のトラブルを避けることができます。
特に、相続財産が複雑で、全員が放棄したいと考えている場合は、共同で手続きを進めるのがスムーズです。限定承認と違い、全員で行うことが義務付けられているわけではありませんが、お互いに状況を共有し、協力し合うことで手続きが円滑に進みます。
家族全員が相続放棄をする場合の注意点
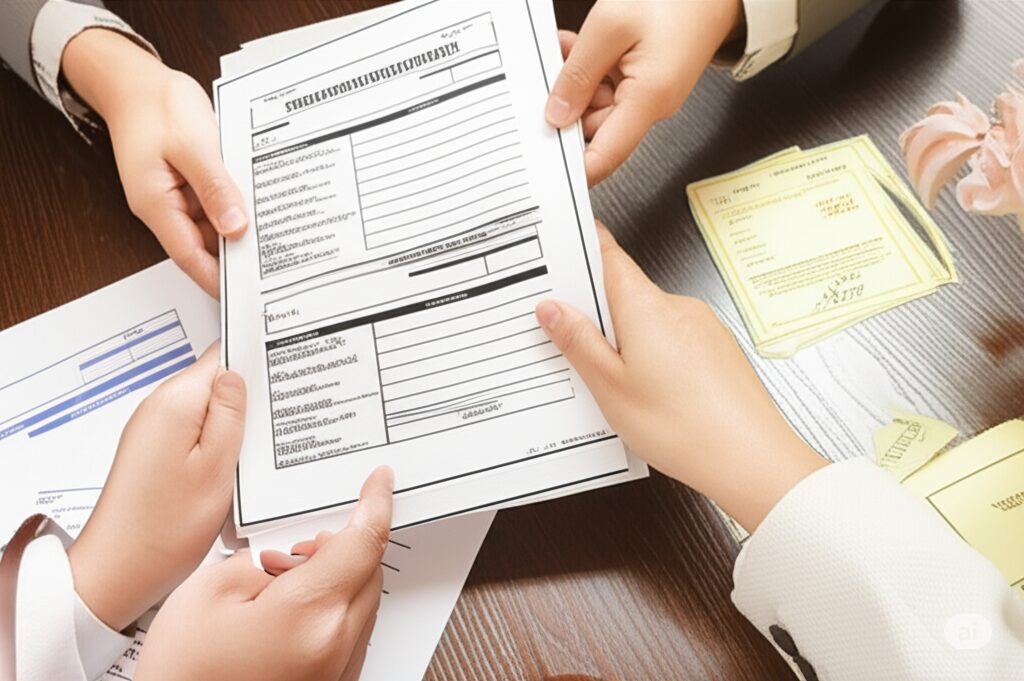
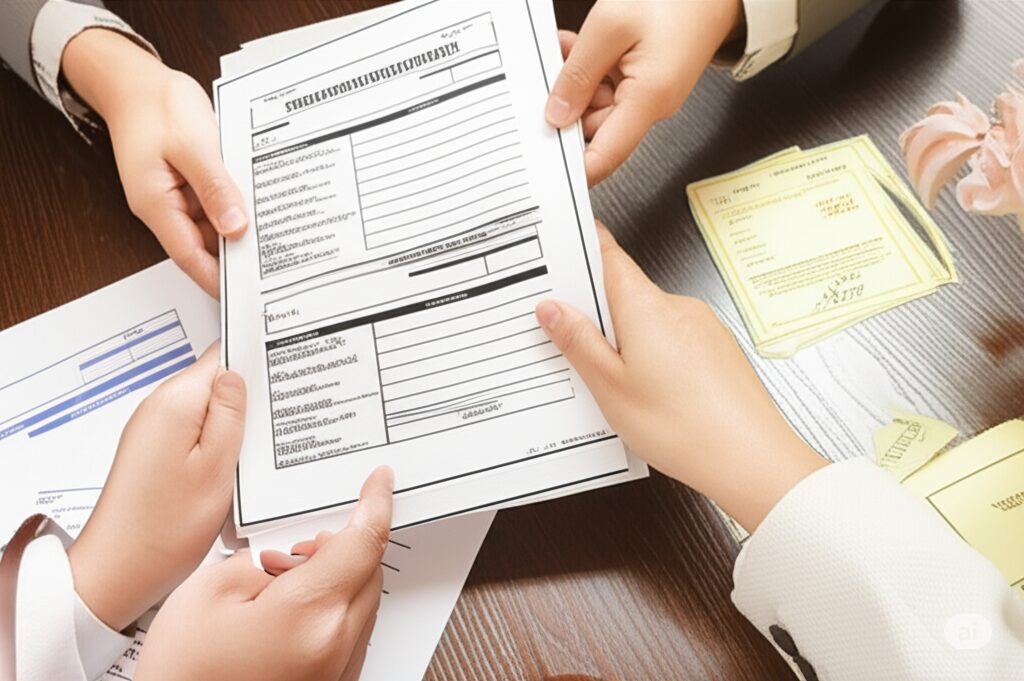
家族全員が相続放棄を検討する場合、注意すべき点がいくつかあります。全員が相続放棄をすることで、相続人がいなくなってしまいます。そうなると、相続財産を管理する人がいなくなります。
この場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。この管理人には、財産を清算し、債権者に支払いを済ませる役割があります。もし、相続放棄をした後も、財産を勝手に管理し続けてしまうと、単純承認とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
【事実】相続財産管理人の選任には高額な費用がかかる場合も
相続人全員が相続放棄をした場合など、相続人が不存在のときには、利害関係人(債権者など)や検察官の申立てにより、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
この申立てには収入印紙800円と郵便切手が必要ですが、それとは別に、管理人の報酬などに充てるための「予納金」を数十万円から100万円以上、家庭裁判所に納める必要がある場合があります。特に不動産など管理が複雑な財産がある場合は、予納金が高額になる傾向があります。
誰も相続しない場合の相続放棄
家族全員が相続放棄をした結果、誰も相続する人がいなくなってしまうことがあります。この場合、相続財産は最終的に国庫に帰属することになります。これは、民法によって定められている仕組みです。ただし、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、財産を清算する手続きが進行します。この手続きには費用と時間がかかります。
しかし、相続放棄は、負債を抱えるリスクから自分自身を守るための重要な手段です。私は、お客様に「誰が相続人になるのか」「財産はどれくらいあるのか」をしっかり把握した上で判断していただくようにお伝えしています。



相続放棄は、家族関係や次順位の相続人に影響を与える大きな決断です。特に、全員で相続放棄をする場合は、その後の財産管理についても考えなければなりません。
突然の出来事に不安を感じるかもしれませんが、この知識を身につけることで、冷静な判断ができるようになるはずです。一人で抱え込まず、まずは信頼できる専門家や行政サービスに相談してみるのも一つの手だと思います。
相続放棄に関するよくある質問
- 相続放棄はいつまでに手続きすればいいですか?
-
相続放棄の手続きは、原則として「ご自身のために相続が開始したことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。もし3か月を過ぎてしまうと、借金なども含めたすべての財産を相続する「単純承認」をしたとみなされるため、注意が必要です
- 相続放棄を考えていますが、故人の遺品整理をしても問題ないでしょうか?
-
遺品整理をすること自体が、直ちに相続放棄をできなくするわけではありません。ただし、遺品整理の際に財産価値のあるもの(骨董品や貴金属など)を売却したり、処分したりする行為は「相続財産の処分行為」とみなされ、相続を承認したことになり、相続放棄が認められなくなる可能性があります。価値の判断が難しいものは、むやみに手をつけないのが賢明です。
- 私が相続放棄をすると、他の兄弟にも影響がありますか?
-
はい、影響があります。相続には順位があり、第一順位の子が全員相続放棄をすると、第二順位である父母(祖父母)へ、そして第二順位の相続人も全員放棄すると、第三順位である兄弟姉妹へ相続権が移ります。そのため、ご自身が相続放棄をする際は、次の順位の相続人になる可能性のある方へ事前に連絡を入れておくことが、後のトラブルを防ぐ上で重要です。
- 相続放棄をしても、生命保険金は受け取れますか?
-
はい、受け取れます。生命保険金は、相続財産とは別に「受取人固有の財産」とみなされるため、相続放棄をした場合でも受け取ることが可能です。借金が多くて相続放棄を選択した場合でも、生命保険金はご自身の生活のために使うことができます。
相続放棄を検討する際に知っておきたいこと


この記事では、相続放棄について知っておきたいポイントを解説しました。ここで改めて、お伝えしたいことがあります。それは、「相続財産の調査を徹底すること」です。借金がないと思っていても、生前に保証人になっていたり、未払いの税金があったりするケースは少なくありません。
プラスの財産だけを見て安易に単純承認してしまうと、後で大変なことになります。だからこそ、相続放棄する前にやってはいけないことは何かをしっかりと理解し、慎重に行動することが大切なのです。
ちなみに、相続放棄をした後に、生命保険金を受け取ることはできます。生命保険金は、受取人固有の財産とみなされるため、相続財産とは別物だからです。このあたりも誤解されやすいポイントです。
相続放棄のまとめ
- 相続放棄は、借金などの負債から逃れるための重要な手続き
- 自己のために相続開始を知った日から3か月以内が申述期間
- 手続きは家庭裁判所で行い、必要書類として戸籍謄本などが必要
- 相続放棄する前に、相続財産の処分行為をしないよう注意
- 費用は実費と専門家への報酬がある
- 全員が放棄すると次順位の相続人に影響するため連絡が必要
- 相続放棄をした場合でも生命保険金は受け取れる
▼あわせて読みたい関連記事▼