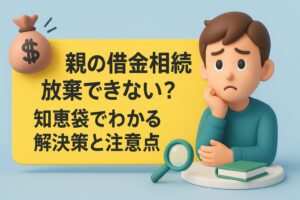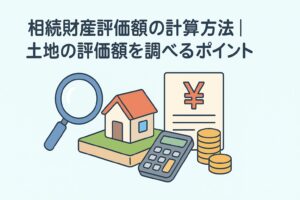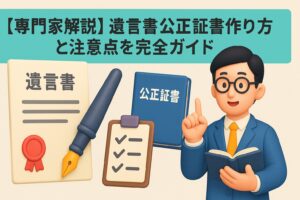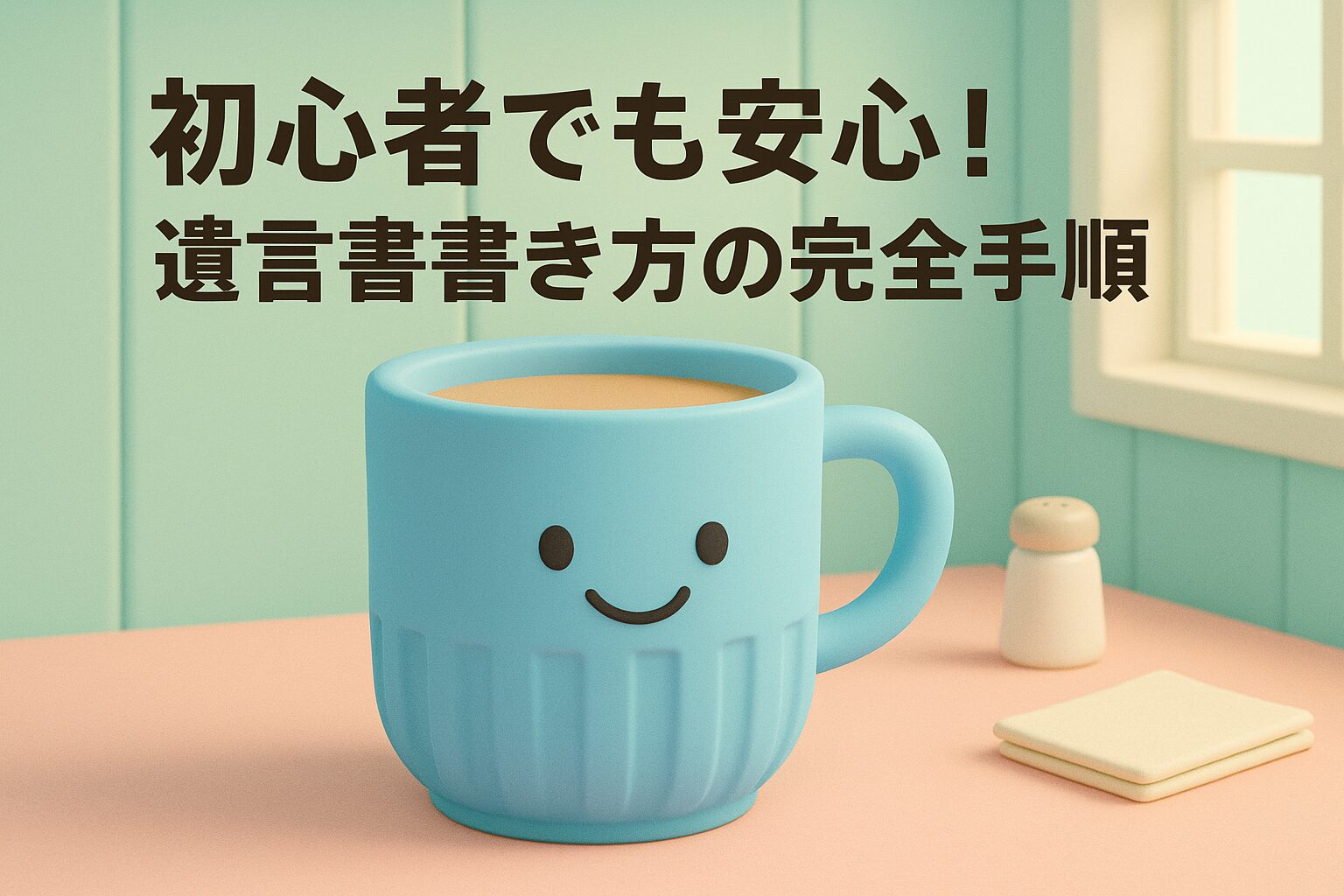
「遺言書の書き方って、何から始めればいいんだろう…」「せっかく書いたのに無効になったらどうしよう…」なんて、頭を抱えていませんか?
僕、終活・相続の専門家カズも、キャリアを始めた頃はチンプンカンプンでした!でも、ご安心ください。実はポイントさえ押さえれば、誰でもちゃんとした遺言書は作成できるんです。
このページでは、簡単な遺言書の書き方から、ちょっと複雑な自筆証書遺言の要件、便利な法務局の保管制度まで、僕がこれまで見てきた数々の失敗談も交えながら解説しますね。
公正証書遺言との違いや、パソコンで作れる財産目録、万が一の訂正方法のルール、さらには特定の相続人に相続させない場合の注意点や遺留分についても触れます。
A4用紙の余白様式や、便利な用紙のダウンロード先、そして相続をスムーズに進める遺言執行者の指定や、全財産の例文まで、あなたの「知りたい!」を全部詰め込みました。さあ、一緒に未来の安心を準備しましょう!
- 無効にならない自筆証書遺言の法的要件がわかる
- パソコンを使った財産目録の作り方がわかる
- 法務局の遺言書保管制度のメリットがわかる
- ケース別の遺言書の具体的な例文を参考にできる
 コンサルタント @KAZU
コンサルタント @KAZU遺言書って、どうしても「難しそう…」というイメージがありますよね。でも、これはご自身の想いを家族に伝えるための大切な「手紙」なんです。僕が15年以上の実務で見てきたのは、ほんの少しの知識不足で想いが届かなかったケースの多さ。この記事では、そんな悲しいすれ違いをなくすため、専門知識を誰にでも分かるように噛み砕いて解説します。一緒に頑張りましょう!
まずはここから!遺言書作成前の3ステップ準備
「よし、書くぞ!」と意気込む前に、ちょっと待ってください。良い遺言書を作るには、実は事前の準備が何よりも大切なんです。ここをしっかりやっておくと、後々の作業が驚くほどスムーズに進みますよ。
- 自分の財産をすべてリストアップする:まずは現状把握から。預貯金、不動産、株式、保険、借金など、プラスもマイナスも全部書き出してみましょう。「こんなところに!」という意外な財産が見つかることもあります。
- 誰に何を遺したいか、想いを整理する:次に、リストアップした財産を「誰に」「どのように」遺したいか考えます。家族構成や関係性を思い浮かべながら、あなたの想いを整理する大切な時間です。
- 必要なものを揃える:想いが固まったら、いよいよ道具を揃えます。長期保存できる筆記用具(ボールペンなど)、印鑑(実印がおすすめ)、そして財産を証明する資料(通帳、登記済権利証など)を手元に用意しましょう。
遺言書書き方の基本!自筆で作成する際のルール


公正証書遺言 違いとメリット・デメリット
「遺言書」と一言で言っても、いくつか種類があるんですよね。特に有名なのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。この二つ、一体何が違うの?って思いますよね。
僕が担当したお客様でも、「手数料がかからないから自筆で!」と意気込んで作成したものの、後で不備が見つかって大慌て…なんてケースもありました。
簡単に言うと、自筆証書遺言は「自分で全部書くDIYタイプ」、公正証書遺言は「専門家(公証人)と一緒に作るプロ仕上げタイプ」です。
それぞれのメリット・デメリットを表で見てみましょう。どっちが自分に合っているか、考えるきっかけになりますよ。
| 種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | ・費用がほぼかからない ・いつでも手軽に作成、修正できる ・内容を秘密にできる | ・要件を満たさないと無効になるリスク ・紛失、改ざん、隠匿の恐れ ・死後に家庭裁判所の「検認」が必要(※) |
| 公正証書遺言 | ・専門家が関与するため無効になる可能性が極めて低い ・原本が公証役場で保管され安心 ・家庭裁判所の「検認」が不要 | ・作成に費用がかかる(財産額による) ・証人2人が必要 ・手続きに手間と時間がかかる |
(※)法務局の保管制度を利用した場合は検認が不要になります。
自筆証書遺言の法的要件は民法で定められている
遺言書を全文自筆で書き、日付・氏名を自署し、押印するという要件は、民法第968条に明確に規定されています。このうち一つでも欠けると、遺言書全体が無効となる可能性があるため、法律の条文に基づいた正確な作成が求められます。
(出典:e-Gov法令検索「民法」第九百六十八条)



どうでしょう?こう見ると一長一短ですよね。手軽さを取るか、確実性を取るか。そもそも遺言書の作成は「終活」の大きな柱の一つです。「終活って、遺言書以外に何をするの?」と気になった方は、まずはこちらの記事で全体像を掴んでみてください。
あわせて読みたい
終活とは何か?今から始める人生の不安を減らす方法
簡単な遺言書の書き方と自筆証書遺言 要件


さて、ここからはDIYタイプの「自筆証書遺言」に絞って、その書き方を解説していきます。「一番簡単な書き方を教えて!」という声が聞こえてきそうですが、残念ながら「これだけ書けばOK!」という魔法のテンプレートはありません。
なぜなら、法律で決められた厳格なルール(要件)があるからです。このルールを守らないと、せっかく書いた遺言書がただの紙切れになってしまうんです。
僕が以前相談を受けたケースで、日付を「令和6年8月吉日」と書いてしまった方がいました。気持ちは分かるのですが、これでは日付が特定できないため、遺言書としては無効になってしまうんです。本当に、もったいない話ですよね。
絶対に守るべき自筆証書遺言の要件は、以下の4つです。呪文のように覚えてください!
自筆証書遺言 必須の4大要件
- 全文を自筆で書くこと(財産目録は除く)
- 日付(年月日)を正確に自筆で書くこと
- 氏名を自筆で書くこと
- 印鑑を押すこと(押印)
たったこれだけ?と思うかもしれませんが、この一つ一つがとても重要です。
- 全文自筆: 代筆やパソコンでの作成は財産目録以外は認められません。自分の手で、想いを込めて書きましょう。
- 日付: 「吉日」はNGです。「2025年8月18日」のように、誰が見ても特定できるように記載が必要です。
- 氏名: 戸籍上の氏名を正確に書いてください。通称やペンネームでは、本人確認が難しくなる場合があります。
- 押印: 認印でも構いませんが、偽造されにくい実印がおすすめです。シャチハタは避けましょう。
この4つのポイントは、遺言書を作成する上での大前提。これさえ守れば、無効になるリスクを大きく減らすことができます。まずは、この基本をしっかり押さえることが、円満な相続への第一歩ですよ。
▼遺言書とセットで考えたいエンディングノート▼
法的な効力を持つ遺言書とは別に、ご自身の想いや希望を家族に伝える「エンディングノート」というものがあります。医療や介護の希望、大切な人へのメッセージなどを書き残せるので、遺言書と合わせて準備しておくと、よりご家族の助けになりますよ。
A4 余白 様式など用紙の決まり
「遺言書って、どんな紙に書けばいいの?」これもよく聞かれる質問ですね。結論から言うと、紙の種類に法的な決まりはありません。便箋でも、コピー用紙でも、極端な話ノートの切れ端でもOKなんです。…ただ、これはあくまで「法的には」という話。
特に、後で解説する「法務局の保管制度」を利用する場合は、話が別です。この制度では、遺言書をデータで長期間保存するため、様式に厳格なルールが定められています。
法務局保管制度の用紙ルール
- サイズ: A4サイズであること。
- 記載: 片面のみに記載し、裏面は白紙にすること。
- 余白: 上部5mm、下部10mm、左側20mm、右側5mmの余白を必ず確保すること。
この「余白」が意外な落とし穴なんです!僕のお客様で、びっしりと文字を書き、余白部分に少しだけ文字がはみ出してしまった方がいました。法務局の窓口で「これでは預かれません」と言われ、その場で書き直し…なんてことも。スキャンする際にはみ出した部分が読み取れない可能性があるため、厳しくチェックされるんです。
保管制度を利用する・しないに関わらず、後々の管理や見やすさを考えると、初めからA4サイズの紙に、余白をしっかり取って書くことを強くおすすめします。長期保存に耐えられるよう、感熱紙など消えやすい紙は避けてくださいね。
用紙 ダウンロードして作成する際の注意点


「余白を自分で測るのは面倒…」という方のために、法務局のウェブサイトでは、あらかじめ余白が設定された遺言書の用紙(様式例)をダウンロードできます。これはとっても便利なので、ぜひ活用してほしいです。
参考情報サイト: 法務省「遺言書の様式等についての注意事項」
URL: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
ただし、ダウンロードして印刷する際にも注意が必要です。
プリンターの設定によっては、印刷時に自動で縮小されてしまい、せっかくの余白が規定のサイズより狭くなってしまうことがあります。僕も一度、自宅のプリンターで「用紙サイズに合わせる」設定のまま印刷してしまい、「あれ?なんか余白が狭いぞ?」と焦った経験があります。
ダウンロード用紙 印刷時のチェックポイント
- 印刷設定で「実際のサイズ」や「倍率100%」などを選ぶ。
- 印刷後、必ず定規で上下左右の余白が確保できているか確認する。
せっかく便利なツールを使っても、最後の最後でミスしては元も子もありません。印刷したら、まずは定規を当てる!これを習慣にしてくださいね。ちなみに、罫線がある用紙を使っても問題ありませんが、文字が読みづらくなるような派手な模様や色付きの紙は避けるのが無難です。
財産目録 パソコン作成のポイント
遺言書の本文は自筆が原則ですが、一つだけ例外があります。それが「財産目録」です。2019年の法改正で、相続財産の一覧である財産目録については、パソコンでの作成や、通帳のコピー、不動産の登記事項証明書の添付などが認められるようになりました。これは本当に大きな変化で、作成の手間がぐっと減りました。
僕が担当した80代の男性は、たくさんの不動産と預金口座をお持ちで、「全部手書きは骨が折れる…」と悩んでいましたが、この制度を説明したところ、「それなら頑張れる!」と大変喜んでいました。
ただし、ここにも大事なルールがあります。
パソコン作成の財産目録 必須ルール
パソコンで作成したり、コピーを添付したりした財産目録のすべてのページ(両面に記載がある場合は両面)に、遺言者が署名・押印することが必要です。
この署名・押印を忘れてしまうと、その財産目録は無効になってしまいます。財産目録だけが無効になるので、遺言書本体の効力には影響がないことが多いですが、どの財産を誰に遺すのかが不明確になり、結局トラブルの原因になりかねません。
また、本文と財産目録が複数ページにわたる場合は、ホチキス止めはせず、すべてのページに「1/3」「2/3」のようにページ番号を振るのを忘れないようにしましょう。これは法務局の保管制度でスキャンする際に必要なルールです。
▼財産リストアップのヒント▼
財産には、家や土地などの不動産はもちろん、最近ではネット銀行の口座やSNSアカウントといったデジタル遺品も含まれます。漏れなくリストアップするためにも、今のうちから整理しておくことが大切ですよ。
間違えた際の訂正方法 ルール


人間誰しも、書き間違いはありますよね。遺言書のような重要な書類なら、なおさら緊張して間違えてしまうかもしれません。でも、慌てて修正液や修正テープを使うのは絶対にNGです!遺言書の訂-訂正方法には、法律で定められた厳格なルールがあるんです。
このルールを知らなかったために、良かれと思ってきれいに修正した遺言書が無効になってしまった…という悲しい事例を、僕は何度も見てきました。
正しい訂正方法のステップ
- 間違えた箇所を二重線で消す。(元の字が読めるように)
- 二重線の上や横など、近くに正しい文字を書き加える。(加入)
- 訂正した箇所の近くに「〇字削除、〇字加入」と書き記す。(付記)
- 付記した部分の横に、遺言者が署名する。
- 訂正した箇所(二重線の上や、加入した文字の近く)に、遺言書本体と同じ印鑑を押す。
…どうでしょう?正直、かなり面倒ですよね。
ええ、本当に面倒なんです(笑)。だから僕がいつもお客様におすすめしているのは、「間違えたら、潔く新しい紙に書き直す」ことです。訂正方法が複雑で、一つでも手順を間違えると、その訂正が無効になってしまいます。財産という重要な事柄を扱う書類ですから、少しでも不安要素があるなら、書き直すのが一番確実で安心ですよ。



ここまで、遺言書作成の基本的な「型」についてお話ししました。要件や様式、訂正方法など、細かいルールが多くて少し疲れてしまったかもしれませんね。でも、これらのルールは全て、あなたの最後の想いを確実に実現するためにあるんです。一つ一つのルールに意味があることを理解すれば、面倒な作業も少しは楽しくなりませんか?…なりませんかね(笑)。
遺言書書き方の応用!トラブルを防ぐための注意点


全財産 例文で書き方を学ぶ
さて、基本ルールを押さえたところで、いよいよ本文の書き方に入っていきましょう。「誰に、どの財産を、どれだけ遺すか」を明確に書くことが何よりも重要です。ここが曖昧だと、せっかくの遺言書が新たな争いの火種になってしまいます。
例えば、「妻に全財産を相続させる」といったシンプルなケースでも、書き方を間違えると意図が伝わらない可能性があります。ここでは、いくつかのパターンに分けて具体的な例文を見ていきましょう。
【例文1】妻に全財産を相続させる場合
第1条 遺言者(氏名)は、遺言者の有する一切の財産を、 遺言者の妻(氏名)(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
ポイント:誰に相続させるのかを特定するため、氏名だけでなく生年月日も記載するとより確実です。「一切の財産」と書くことで、預貯金、不動産、有価証券など、すべての財産が含まれます。
【例文2】複数の相続人に、財産を指定して相続させる場合
第1条 遺言者は、以下の不動産を長男(氏名)(平成〇年〇月〇日生)に相続させる。 【不動産の表示】 所在:〇〇市〇〇町〇丁目 地番:〇番〇 地目:宅地 地積:〇〇.〇〇平方メートル 第2条 遺言者は、以下の預金を長女(氏名)(平成〇年〇月〇日生)に相続させる。 【預金の表示】 〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号 1234567
ポイント:財産は、誰が見ても特定できるように正確に記載することが重要です。不動産なら登記事項証明書の通りに、預金なら銀行名、支店名、口座種別、口座番号を正確に書きましょう。これが財産目録の役割になります。



ちなみに、相続人に対して財産を遺す場合は「相続させる」、相続人以外の人(例えばお世話になった友人や団体など)に遺す場合は「遺贈する」と書き分けるのが一般的です。財産をいただいた後のお礼については、こちらの「相続お礼手紙例文ガイド」も参考になるかもしれませんね。
特定の人に財産を相続させない方法


これは非常にデリケートな問題ですが、「特定の相続人には財産を渡したくない」と考える方もいらっしゃいます。様々な家庭の事情がありますから、それ自体は仕方のないことです。遺言書でその意思を示すことは可能です。
例えば、長男と長女がいる場合に、長女にだけ全財産を相続させたい、というケースを考えてみましょう。
【例文】特定の相続人を除外する場合
第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、 長女(氏名)(平成〇年〇月〇日生)に相続させる。
このように書けば、長男には財産が渡らないことになります。わざわざ「長男には相続させない」と書く必要はありません。財産を渡す人だけを指定すれば良いのです。
「相続させない」場合の超重要注意点
ただし、これで全て解決!とはならないのが相続の難しいところ。次に解説する「遺留分」という権利が関係してきます。遺言で「相続させない」と指定しても、その相続人が法律で最低限保障された取り分(遺留分)を請求してきた場合、それに応じなければならない可能性があるのです。これについては、次の項目で詳しく解説しますね。
注意点 遺留分を侵害しない配分


「遺留分(いりゅうぶん)」、この言葉は絶対に覚えておいてください。これは、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障された、最低限の遺産の取り分のことです。
僕が以前関わった相続で、あるお父様が「全財産を長男に相続させる」という遺言書を残しました。しかし、他に長女もいたため、長女が「私の遺留分をください!」と主張し、結局、長男は遺産の一定割合を長女に支払うことになりました。お父様の「長男に全てを」という想いは、完全には実現できなかったのです。
遺言書は故人の意思を尊重するものですが、残された家族の生活保障という観点から、この遺留分という制度が設けられています。
誰に、どれくらいの遺留分があるの?
- 総体的遺留分: 全体の遺産のうち、遺留分として確保される割合。原則として遺産の1/2です。(相続人が直系尊属のみの場合は1/3)
- 個別的遺留分: 各相続人がもらえる具体的な割合。上記の総体的遺留分に、各自の法定相続分を掛け合わせて計算します。
例えば、相続人が妻と子供2人(長男・長女)の場合、 妻の遺留分は 1/2 × 1/2 = 1/4 子供1人あたりの遺留分は 1/2 × 1/4 = 1/8 となります。



遺留分を侵害する遺言書が、ただちに無効になるわけではありません。ただ、後から遺留分を請求される(これを「遺留分侵害額請求」と言います)可能性があり、新たなトラブルの原因になりやすいのです。財産配分を考える際は、相続税がどのくらいかかるのかも把握しておくと、より親切ですよ。
あわせて読みたい
相続税計算の基本と節税のコツを図解で徹底解説
また、多額の借金があるなど、財産状況によっては相続人側が「相続放棄」を検討するケースもあります。財産の全体像を把握しておくことが大切ですね。
スムーズな相続には遺言執行者 指定
遺言書を作成したら、その内容を実現してくれる人が必要になりますよね。その役割を担うのが「遺言執行者」です。
遺言執行者は、亡くなった方の代理人として、預金の解約や不動産の名義変更など、遺言の内容に沿った相続手続きを一人で行う権限を持ちます。これ、実はすごく重要なんです。
もし遺言執行者がいないと、例えば銀行預金を解約するのに相続人全員の戸籍謄本と実印、印鑑証明書が必要になるなど、手続きが非常に煩雑になります。相続人の一人が非協力的だったり、遠方に住んでいたりすると、手続きが全く進まない…なんてことになりかねません。
そこで、遺言書の中で信頼できる人を遺言執行者に指定しておくことを強くおすすめします。
【例文】遺言執行者を指定する場合
第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、以下の者を指定する。 住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇 氏名:〇〇 〇〇(長男) 昭和〇年〇月〇日生
ポイント:相続人の一人を指名することもできますし、利害関係のない第三者、例えば僕のような専門家(弁護士、司法書士など)を指定することも可能です。相続手続きに不安がある場合や、相続人同士の関係が複雑な場合は、専門家を指定する方がスムーズに進むことが多いです。
▼遺言書以外の相続対策▼
生前の財産管理や、より柔軟な資産承継の方法として「家族信託」という制度もあります。また、遺言執行と合わせて、葬儀や役所手続きなど死後の様々な事務手続きを任せる「死後事務委任」という契約もあります。ご自身の状況に合わせて、様々な制度を検討してみるのも良いでしょう。
安心の法務局 保管制度を活用する


利用件数は右肩上がり!法務局の遺言書保管制度
法務省の発表によると、令和2年7月に開始された自筆証書遺言書保管制度の利用件数は年々増加しており、令和5年3月末時点での累計保管申請件数は約5万7千件に達しています。これは、相続への備えに対する意識の高まりと、制度の信頼性を示していると言えるでしょう。
最後に、自筆証書遺言の弱点(紛失、改ざん、隠匿のリスク、検認手続きの必要性)をカバーしてくれる、非常に便利な制度をご紹介します。それが「自筆証書遺言書保管制度」です。
これは、自分で作成した自筆証書遺言を、法務局(遺言書保管所)で預かってもらえる制度です。手数料は1通につき3,900円かかりますが、それ以上のメリットがたくさんあります。
法務局 保管制度の主なメリット
- 紛失・改ざんの心配がない: 原本が安全に保管されます。
- 形式チェックをしてもらえる: 作成した遺言書が、日付や署名・押印など民法の定める形式に適合しているか、職員が外形的にチェックしてくれます。(内容の有効性を保証するものではありません)
- 家庭裁判所の検認が不要になる: これが最大のメリットかもしれません。通常必要な検認手続きが不要になるため、相続開始後の手続きが非常にスムーズになります。
- 相続人への通知: 遺言者が亡くなった後、あらかじめ指定しておいた相続人等に、遺言書が保管されている旨が通知される仕組みもあります。これにより「遺言書の存在に誰も気づかなかった」という事態を防げます。
僕のお客様にも積極的に利用をおすすめしている制度です。せっかく想いを込めて作成した遺言書です。その想いを確実に届けるためにも、ぜひこの制度の利用を検討してみてください。
参考情報サイト: 法務省「自筆証書遺言書保管制度」
URL: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
【専門家が回答】遺言書に関するよくある質問(FAQ)
失敗しない遺言書書き方の最終チェック
お疲れ様でした!これであなたも遺言書マスターに一歩近づきましたね。知識はもう十分です。あとは、あなたの想いを形にするだけ。さあ、まずはペンと紙を用意して、あなたの財産リストの作成から始めてみましょう!
最後に、この記事で解説してきた大切なポイントをリスト形式で総まとめします。遺言書を作成した後、投函する前の手紙を見直すように、このリストで最終チェックをしてみてください。
- 遺言書には手軽な「自筆証書」と確実な「公正証書」がある
- 自筆証書遺言は「全文自筆」「日付」「氏名」「押印」が必須要件
- 日付は「吉日」ではなく年月日を正確に記載する
- 押印は認印でもOKだが実印が望ましくシャチハタは避ける
- 法務局の保管制度を利用するなら用紙はA4で余白ルールを守る
- 用紙は法務局サイトからダウンロード可能だが印刷設定に注意
- 財産目録はパソコン作成やコピー添付が可能
- パソコン作成の財産目録には全ページに署名と押印が必要
- 書き間違えたら修正液は使わず法律で定められた訂正方法で行う
- 訂正が面倒な場合は潔く書き直すのが最も確実
- 誰にどの財産を遺すか、具体的に特定して記載する
- 相続人以外へは「遺贈する」、相続人へは「相続させる」と書く
- 特定の相続人に財産を渡さない指定も可能だが遺留分に注意が必要
- 兄弟姉e妹を除く相続人には最低限の取り分である遺留分がある
- 相続手続きをスムーズにするために遺言執行者を指定しておく
- 自筆証書遺言は法務局で保管してもらうと検認不要で安心



最後までお読みいただき,本当にありがとうございます。遺言書作成は、決して難しいことばかりではありません。大切なのは、あなたの想いを、正しい形で残すこと。この記事が、その一助となれば、専門家としてこれほど嬉しいことはありません。もし一人で悩んでしまったら、いつでも僕のような専門家を頼ってくださいね。あなたの人生の締めくくりが、最高に素敵なものになるよう、心から応援しています!
遺言書がないと家庭裁判所でのトラブルに?
最高裁判所が公表している司法統計によると、令和4年度に全国の家庭裁判所で新たに受け付けられた遺産分割事件の数は8,969件に上ります。遺言書は、こうした家族間のトラブルを未然に防ぐための極めて有効な手段です。
▼あわせて読みたい関連記事▼