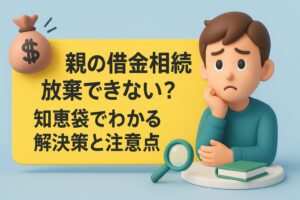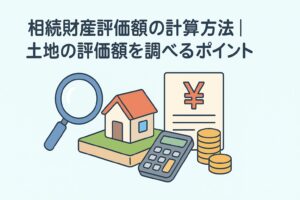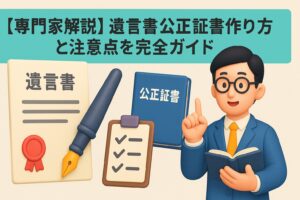相続のこと、考え始めると「一体どこから手をつければ…」と頭を抱えてしまいますよね。特に相続人調査を自分でやるべきか、どこまで調べたらいいのか、悩む方も多いようです。
自治体での手続き方法はもちろん、相続人調査の根拠法令なんて話も出てくると、もうお手上げ状態に。また、法定相続人の確認方法や、相続人を調べたいときの手続き方法、相続人調査に必要な書類集めも一苦労です。
もし他人や第三者が関わる場合、相続人を調べる方法はあるのか、公用請求とは何か、最終的に相続人調査は誰に頼むのがベストなのか、そんな疑問をこの記事でスッキリ解決していきますね!
- 自分で相続人調査を進める手順がわかる
- ケース別に必要な書類が具体的にわかる
- 専門家への依頼を判断する基準がわかる
- 相続人調査でつまずきやすい注意点を理解できる
 コンサルタント @KAZU
コンサルタント @KAZU相続手続きの第一歩は、何と言っても正確な相続人の確定です。ここで間違うと、後の遺産分割協議が全て無効になることも。面倒に感じるかもしれませんが、一番大切な基礎工事だと思って丁寧に進めましょう。後々のトラブルを避けるためにも、最初のこの一手間が肝心ですよ。
基本的な相続人調査方法と必要書類


法定相続人の確認方法から始めよう
相続が始まってまず最初にすべきことは、誰が法的な相続人なのかを正確に確定させることです。これが全ての基本となります。ご家族の中では「相続人はこの人たち」と分かっているつもりでも、法的に見ると想定外の相続人がいるケースは少なくありません。
例えば、被相続人に離婚歴があり前妻(夫)との間に子がいた場合や、家族が誰も知らなかった認知している子がいた場合など、後から判明すると遺産分割協議のやり直しという大変な事態になってしまいます。
民法で定められた相続人(法定相続人)には、相続できる順位が明確に決められています。常に相続人となるのは亡くなった方(被相続人)の配偶者です。配偶者は、他の順位の相続人がいるかどうかに関わらず、常に相続権を持ちます。それに加えて、以下の順位で相続権が移っていきます。
法定相続人の順位
- 第1順位:子、またはその代襲相続人(孫など)
被相続人に子がいる場合、子が相続人になります。養子も実子と同じく第1順位の相続人です。もし子が被相続人より先に死亡していた場合、その子の子、つまり孫が代わりに相続人となります(代襲相続)。 - 第2順位:父母などの直系尊属
第1順位の相続人(子や孫)が誰もいない場合に限り、被相続人の父母が相続人になります。父母が共に亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。 - 第3順位:兄弟姉妹、またはその代襲相続人(甥・姪)
第1順位と第2順位の相続人が誰もいない場合に、初めて兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合は、その子である甥や姪が代襲相続します。
このように、上の順位の人が一人でもいる場合、下の順位の人は相続人にはなりません。この複雑な関係性を公的に証明し、相続人を一人も漏れなく確定させるために、戸籍謄本などを集める作業が必要不可欠となるのです。
相続権を失うケース(相続欠格・廃除)
法定相続人であっても、特定の理由で相続権を失うことがあります。例えば、被相続人を殺害しようとしたり、遺言書を偽造したりした場合は「相続欠格」となり、自動的に相続権を失います。また、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てることで、虐待などの理由があった相続人の権利を剥奪する「相続廃除」という制度もあります。これらも戸籍に記載される場合があります。
相続人調査は自分でできるのか


結論から言うと、相続人調査をご自身で行うことは可能です。実際に、多くの方が時間と労力をかけてご自身で戸籍を集め、手続きを完了させています。特に、相続関係がシンプルで、被相続人の本籍地移動が少ないようなケースでは、比較的スムーズに進められるでしょう。
しかし、この調査は想像以上に骨の折れる作業になる可能性があります。自分で進める場合のメリットとデメリットを比較してみましょう。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 費用面 | 専門家への報酬が不要。戸籍発行手数料などの実費のみで済む。 | 時間と手間がかかるため、自身の労働時間を考えると一概に安上がりとは言えない場合も。 |
| 手続き面 | 相続手続き全体の流れを自分で把握できる。 | 古い戸籍の解読が困難。本籍地が点在していると請求先が多くなり非常に煩雑。書類の不備で何度も役所とやり取りすることも。 |
| 精神面 | 自分のペースで進められる。 | 知らない相続人が判明した場合、精神的な負担が大きい。手続きが滞ると焦りやストレスを感じやすい。 |
もし途中で戸籍の取得が途切れてしまったり、読み解きが困難だったりすると、相続人を確定できず、その後の銀行口座の解約や不動産の相続登記といった重要な手続きがすべてストップしてしまいます。自分で挑戦してみて、「これは思った以上に大変だ…」と感じたら、無理せず早めに専門家への依頼に切り替えるのが賢明な判断と言えます。
【事実】相続トラブルは他人事ではない!家庭裁判所のデータ
「うちは家族仲が良いから大丈夫」と思っていても、相続が「争族」に発展するケースは後を絶ちません。最高裁判所が公表している司法統計によると、遺産分割に関して家庭裁判所に持ち込まれる「遺産分割事件」の新規申立て件数は、毎年1万件を超えて安定的に推移しています。
この数字は、氷山の一角に過ぎません。裁判所には持ち込まれないものの、水面下で深刻な対立を抱えている家族はさらに多いと推測されます。
こうしたトラブルの多くは、相続人の範囲や財産の内容が不明確であることに起因します。面倒に感じても、最初の相続人調査を正確に行うことが、家族の絆を守るための最も重要な第一歩なのです。
(出典:裁判所「司法統計年報」)
相続人調査はどこまで行えばいいか
【大手信託銀行の調査】約6人に1人が「想定外の相続人」の存在を経験
「出生まで戸籍を遡るなんて大げさな…」と感じるかもしれませんが、その必要性を裏付ける衝撃的なデータがあります。三菱UFJ信託銀行が2022年に行った相続に関する意識調査によると、遺産分割協議を経験した人のうち、実に17.2%が「想定していなかった相続人がいた」と回答しています。
これは約6人に1人の割合に相当します。具体的には、被相続人の離婚歴による前妻(夫)の子や、認知した子などが後から判明するケースです。相続人調査を徹底しないと、後から遺産分割協議が無効になるなど深刻なトラブルに発展しかねません。面倒でも出生まで遡る作業は、円満な相続に不可欠な手続きなのです。
相続人調査で最も重要なのは、「被相続人の出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本等を全て揃えることです。これは、相続手続きを行う法務局や金融機関から例外なく求められることであり、絶対に省略できません。「なぜそんなに昔まで遡る必要があるの?」と疑問に思うかもしれませんが、これには明確な理由があります。
例えば、最新の戸籍謄本には、現在の配偶者と、その方との間に生まれた子の名前しか記載されていないかもしれません。しかし、被相続人が若い頃に結婚・離婚を経験し、前の配偶者との間に子がいた場合、その子の情報は現在の戸籍には載っていません。
出生まで遡ることで、そういった全ての婚姻歴や子の有無を洗い出し、「これで全ての相続人を網羅しました」と公的に証明できるのです。
調査が必要な戸籍の具体的な範囲
- 【基本】被相続人について:出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本をすべて。
- 【相続人】相続人全員について:現在の戸籍謄本(相続人が存命であることを証明するため)。
- 【代襲相続が発生する場合】:本来の相続人(先に死亡した子や兄弟姉妹)の出生から死亡までの戸籍謄本。これにより、さらにその子(孫や甥姪)へ相続権が移っていることを証明します。
- 【子がいない場合】:第2順位の相続人(父母や祖父母)が亡くなっていることを証明するための戸籍(除籍)謄本。
- 【子も親もいない場合】:第3順位の兄弟姉妹が相続人となるため、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本。これにより、兄弟姉妹が誰であるかを確定させます。
このように、相続人の構成によって調査範囲は大きく変わってきます。特に兄弟姉妹が相続人となるケースでは、被相続人だけでなく、その両親の戸籍まで遡る必要があり、集める書類の量が膨大になることを覚悟しておく必要があります。
相続人調査に必要な書類とは
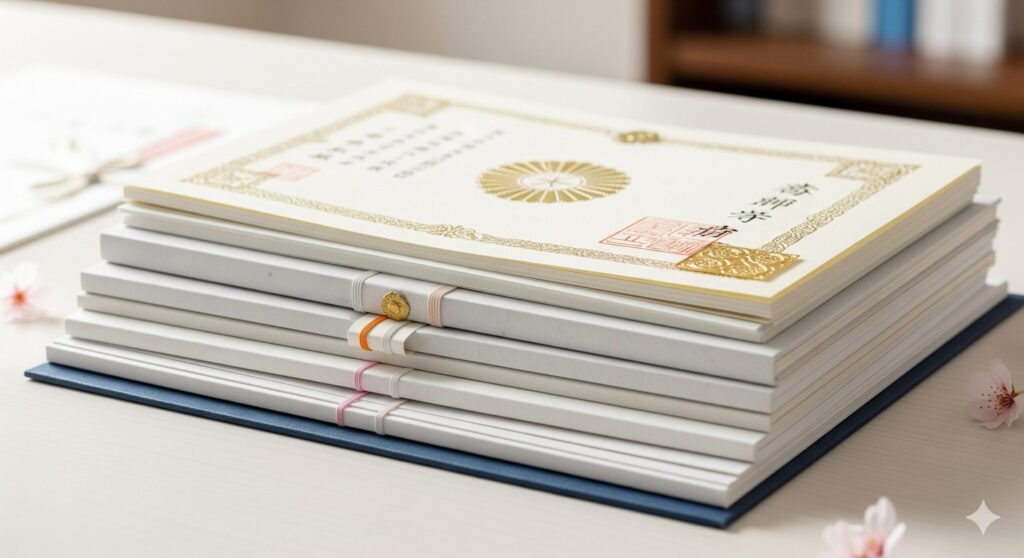
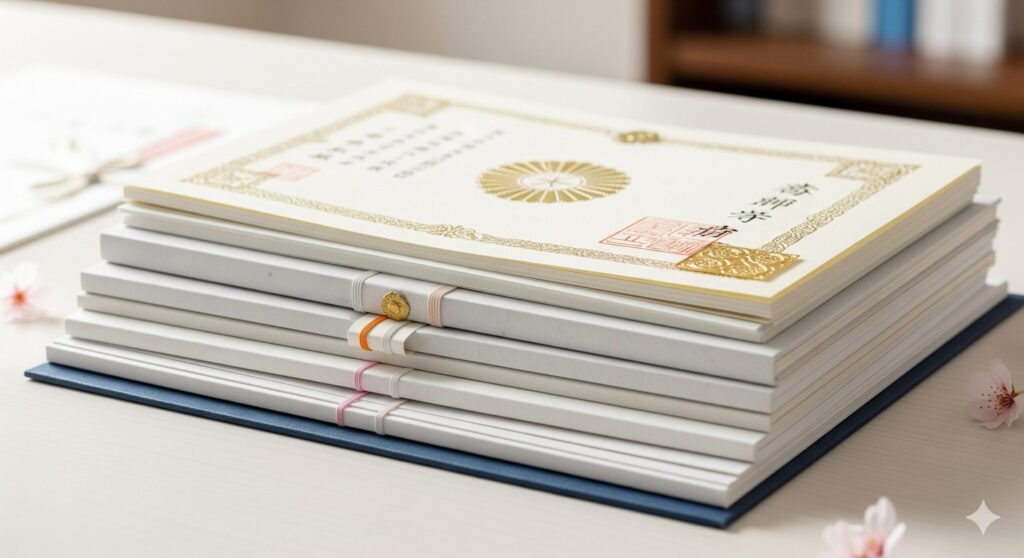
相続人調査で中心となる書類は「戸籍」ですが、一言で戸籍といってもいくつか種類があります。これらの違いを理解しておくと、役所での手続きがスムーズになります。主な書類は以下の通りです。
| 書類の種類 | 内容 | 手数料の目安 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 現在効力のある戸籍で、そこに記載されている全員分の情報が載っている写し。コンピュータ化されたものは横書きです。 | 1通450円 |
| 除籍謄本 | 結婚や死亡、転籍などにより、戸籍に記載されていた全員がいなくなって閉鎖された戸籍の写し。 | 1通750円 |
| 改製原戸籍謄本(かいせいげんこせき) | 法律の改正で戸籍の様式が変更される前の、古い様式の戸籍の写し。多くは縦書きで手書きです。 | 1通750円 |
| 戸籍の附票の写し | その戸籍が作られてからの住所の変遷が記録されている書類。不動産登記などで相続人の現住所を証明するために必要となります。 | 1通300円程度 |
これらの書類を、被相続人の「出生から死亡まで」途切れることなく連続するように集めていくのが、相続人調査の具体的な作業です。手数料は国の法律で定められていますが、附票など一部の手数料は市区町村によって異なる場合があります。詳しくは法務省のウェブサイトで戸籍手数料に関する情報を確認するのも良いでしょう。
謄本(とうほん)と抄本(しょうほん)の違い
役所で戸籍を請求する際、「謄本」と「抄本」のどちらが必要か聞かれることがあります。謄本は「全員の写し」、抄本は「一部の人の写し」です。相続手続きでは、他の相続人の有無を確認する必要があるため、必ず「謄本」を取得してください。「抄本」では手続きができませんので注意が必要です。
相続人を調べたいときの手続き方法
相続人を調べるための具体的な手続きは、戸籍謄本などを市区町村役場で取得することから始まります。やみくもに請求するのではなく、効率よく進めるための手順を知っておきましょう。
まず、被相続人の最後の本籍地の役所で、死亡の事実が記載された戸籍(除籍)謄本を取得します。ここが全てのスタート地点です。次に、取得した謄本の記載内容をよく読み、「いつ、どこからこの戸籍に移ってきたか」という情報(「従前戸籍」や「編製事項」の欄に記載があります)を見つけ出します。
そして、その従前戸籍が置かれていた市区町村役場に、一つ前の戸籍謄本を請求する、という作業を繰り返していくのです。
この「戸籍を遡る」という地道な作業を、被相続人が生まれた時点の戸籍(多くはご両親の戸籍)にたどり着くまで続けます。本籍地が遠方にある場合は、郵送で請求することも可能です。その際は、各自治体のホームページで申請書をダウンロードし、以下のものを同封して送付するのが一般的です。
- 必要事項を記入した申請書
- 手数料分の定額小為替(郵便局で購入)
- 請求者の本人確認書類のコピー(運転免許証など)
- 切手を貼った返信用封筒
- (必要な場合)被相続人との関係がわかる戸籍謄本のコピー
郵送請求は返送までに1〜2週間程度かかることもあるため、時間に余裕をもって進めることが大切です。
【法務省】2024年3月開始!「戸籍の広域交付制度」で相続人調査が劇的に変化
これまで本籍地ごとに請求する必要があった戸籍謄本ですが、法務省によると、2024年3月1日から「戸籍の広域交付制度」がスタートしました。これにより、被相続人の本籍地が全国に点在していても、最寄りの市区町村役場の窓口一箇所で、出生から死亡までの戸籍謄本等をまとめて請求することが可能になりました。
- メリット:全国の役所への郵送請求の手間と時間が大幅に削減できる。
- 注意点:請求できるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)に限られ、兄弟姉妹や代理人(弁護士等を除く)による請求はできません。また、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍は対象外です。
この制度の登場により、相続人調査の負担は大きく軽減されました。該当する方は積極的に活用しましょう。
相続人調査における自治体の役割


【法務省】2024年3月開始!「戸籍の広域交付制度」で相続人調査が劇的に変化
これまで本籍地ごとに請求する必要があった戸籍謄本ですが、法務省によると、2024年3月1日から「戸籍の広域交付制度」がスタートしました。これにより、被相続人の本籍地が全国に点在していても、最寄りの市区町村役場の窓口一箇所で、出生から死亡までの戸籍謄本等をまとめて請求することが可能になりました。
ただし、この便利な制度を利用できるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)に限られ、兄弟姉妹や代理人による請求はできません。また、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍は対象外となるため注意が必要ですが、相続人調査の手間を大幅に削減できる画期的な制度です。
市区町村役場(自治体)は、相続人調査において戸籍に関する証明書を発行する窓口としての、非常に重要な役割を担っています。私たちの調査は、この役場を起点に行うことになります。
以前は、戸籍謄本はその本籍地がある役所でしか取得できず、被相続人が結婚や転勤で本籍地を何度も移している場合、それぞれの役所に個別に請求する必要があり、大変な手間がかかりました。
しかし、2024年3月1日から戸籍法の改正により、本籍地以外の最寄りの市区町村の窓口でも、まとめて戸籍謄本等を請求できる「戸籍の広域交付制度」がスタートしました。
これにより、被相続人の本籍地が北海道から沖縄まで点在していても、例えばお住まいの近くの役所の窓口一箇所で、出生から死亡までの戸籍を(データ化されているものに限り)一括して請求できるようになったのです。
これは手続きの負担を劇的に軽減する、画期的な制度と言えるでしょう。窓口で「相続で使いたいので、被相続人(故人名)の出生から死亡までの戸籍をすべてお願いします」と伝えれば、担当者が丁寧に案内してくれますので、ぜひ積極的に活用したい制度です。
広域交付制度の注意点
非常に便利な制度ですが、いくつか注意点があります。まず、請求できるのは本人、配偶者、直系親族(父母、子など)のみで、兄弟姉妹や代理人による請求はできません。
また、コンピュータ化されていない一部の古い手書きの戸籍(改製原戸籍など)は対象外のため、その場合は従来通り本籍地の役所に直接請求する必要があります。



古い戸籍謄本は、今の様式と違って手書きで達筆な文字で書かれていることが多いんです。まるで古文書の解読みたいで、慣れていないと本当に大変。でも、そこに「認知した子」などの重要な記載が隠れていることも。面倒でも一つ一つ丁寧に読み解くことが、後々の安心に繋がります。
専門的な相続人調査方法と必要書類


相続人調査は誰に頼むべきか
「自分で戸籍を遡るのは、時間的にも精神的にも限界だ…」と感じた場合、専門家に依頼するのが最も確実で安心な方法です。相続人調査を依頼できる主な専門家は、弁護士、司法書士、行政書士の3つの士業です。それぞれの専門家には特徴があり、ご自身の状況に合わせて選ぶことが重要です。
どの専門家に頼むべきか、以下の表を参考に比較検討してみてください。
| 専門家 | 主な業務範囲 | 費用の目安 | こんな方におすすめ |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | 戸籍収集、遺産分割協議の代理、調停・審判の対応など、法律トラブル全般 | 5万円~20万円程度(調査のみ) | ・相続人間で既にもめている ・将来的にトラブルになる可能性が高い ・相続放棄も検討している |
| 司法書士 | 戸籍収集、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記など | 3万円~10万円程度(調査のみ) | ・遺産に不動産が含まれている ・相続登記まで一括で任せたい ・特に争いごとはない |
| 行政書士 | 戸籍収集、遺産分割協議書の作成、自動車の名義変更など、書類作成の専門家 | 2万円~8万円程度(調査のみ) | ・とにかく戸籍収集だけを安価に頼みたい ・遺産分割協議は自分たちでできる ・争いごとや不動産登記はない |
例えば、既に相続人間で「遺産の分け方」について意見が対立している、またはその可能性が高い場合は、交渉や法的手続きの代理人となれる弁護士などの専門家に相談するのが最適です。一方で、特に争いはなく、主な手続きが不動産の相続登記である場合は、登記の専門家である司法書士に依頼するのがスムーズでしょう。
費用を抑えて、まずは面倒な戸籍収集だけを代行してほしいというニーズであれば、行政書士が適しています。専門家を探す際は、日本弁護士連合会などの公式サイトからお近くの専門家を探すこともできます。
相続人調査は他人でも可能か


原則として、戸籍謄本を請求できるのは、その戸籍に記載されている本人、その配偶者、そして直系親族(父母、子、祖父母、孫など)に限られています。
これは戸籍法で定められており、個人のプライバシーを保護するための非常に重要なルールです。したがって、全く利害関係のない他人が、興味本位や個人的な調査目的で他人の戸籍を取得することはできません。
ただし、このルールには例外があります。「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合」など、正当な理由がある第三者は、その理由を客観的に証明する資料を提出することで、戸籍謄本を請求することが認められています。
例えば、お金を貸した相手が亡くなり、その相続人に返済を求める必要がある債権者が、相続人を特定するために請求するケースがこれにあたります。その際は、金銭消費貸借契約書のコピーなどを役所に提示する必要があります。
代理人による請求は可能
相続手続きにおいては、相続人本人が作成した「委任状」があれば、親族や知人などの代理人が戸籍を請求することも可能です。お仕事などで平日に役所へ行けない方は、この方法を利用すると良いでしょう。
相続人調査と公用請求について
「公用請求」や「職務上請求」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。これは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの国家資格を持つ専門家が、受任している業務を遂行するために必要不可欠な場合に限り、戸籍謄本や住民票などを請求できる特別な制度のことです。
この制度があるため、専門家は相続人調査の依頼を受けた際、相続人一人ひとりから委任状をもらわなくても、専用の「職務上請求書」という用紙を使って、職権で必要な戸籍謄本などを収集することができます。
これにより、依頼者は自分で全国の役所に何度も連絡を取ったり、面倒な郵送請求の手続きをしたりする必要が一切なくなります。迅速かつ正確に戸籍を収集できる、専門家に依頼する非常に大きなメリットの一つと言えるでしょう。
相続人調査の根拠法令とは
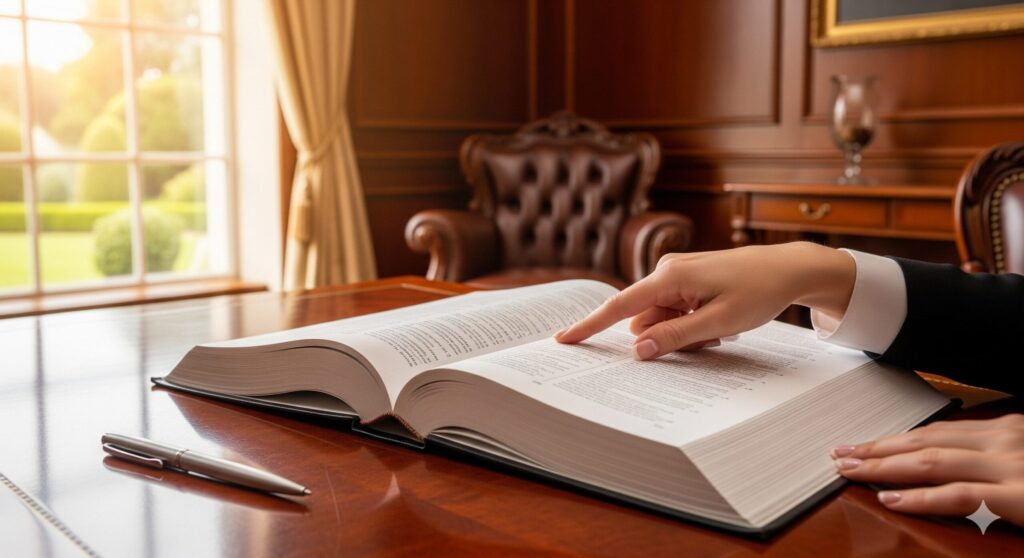
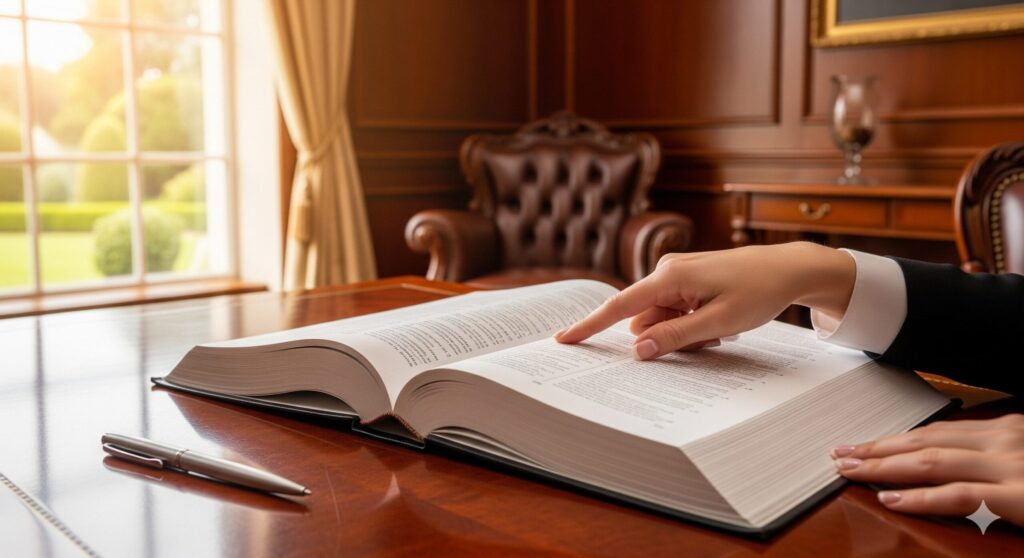
これまでお話ししてきた相続人調査や戸籍制度は、もちろん個人の判断や慣習で行われているわけではなく、しっかりとした法律に基づいて運用されています。その根幹をなすのが「戸籍法」と「民法」という2つの法律です。
それぞれの法律の役割
- 戸籍法:国民の身分関係(出生、結婚、死亡など)を登録し、公に証明するための戸籍制度そのものについて定めた法律です。戸籍の記載事項、届出の義務、証明書の発行手続き、手数料、罰則などが細かく規定されています。私たちが役所で戸籍謄本を請求する際の一連の手続きは、すべてこの戸籍法が根拠となっています。
- 民法:財産や家族に関するルールを定めた法律です。その中の「相続編」において、「誰が相続人になるのか(法定相続人)」や「それぞれの相続人がどれくらいの割合で財産を相続するのか(法定相続分)」といった、相続の基本的な大原則が定められています(民法第882条以下)。
つまり、相続人調査とは、民法で定められた相続人を、戸籍法に則って集めた公的な証明書(戸籍謄本など)で一人残らず確定させるという、2つの法律に基づいた非常に厳格な法的手続きなのです。
相続人調査における第三者の手続き
前述の通り、相続人調査は原則として親族など関係者しか行えませんが、正当な利害関係のある第三者が、自身の権利を守るために手続きを行うケースもあります。その典型的な例が、被相続人(亡くなった方)にお金を貸していた債権者です。
債権者は、貸したお金を回収する権利(債権)を持っています。借主が亡くなった場合、その返済義務は相続人に引き継がれるため、債権者はまず誰が相続人になったのかを法的に特定しなくてはなりません。
この目的のために、債権者は、貸し借りの事実を証明する契約書や借用書などの資料を役所の窓口に提示し、「利害関係人」として戸籍謄本の開示を請求します。これが認められれば、相続人を特定し、その後の請求手続きへと進むことができるのです。
このように、相続は家族だけの問題にとどまらず、時には被相続人の生前の取引関係などを引き継ぎ、第三者を巻き込んだ法的な手続きに発展することもあるということを、心に留めておくと良いでしょう。
相続人調査についてよくあるご質問FAQ





相続人調査は、パズルのピースを集めるような作業です。最後の1ピースが見つからないと全体像が完成しません。自分で行う場合も、専門家に頼む場合も、目的は「全ての相続人を確定させる」という一点です。このゴールを忘れずに、一つ一つの手続きを丁寧に進めていきましょう。
まとめ:相続人調査方法と必要書類
- 相続人調査は遺産分割協議の前提となる最重要の手続き
- まず民法で定められた法定相続人の順位と範囲を正確に理解する
- 調査の基本は被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を全て集めること
- 戸籍には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本など複数の種類がある
- 手続きは死亡時の最新の戸籍から出生時の古い戸籍へ遡って請求していく
- 2024年3月から戸籍の広域交付制度が始まり最寄りの役所で一括請求が可能に
- 相続人調査は自分でも可能だが時間と手間、専門知識が必要となる
- 相続関係が複雑な場合や時間がない場合は専門家への依頼が安心
- 依頼できる専門家は弁護士、司法書士、行政書士でそれぞれ得意分野が違う
- 専門家は職務上請求(公用請求)により委任状なしでスムーズに戸籍を収集できる
- 原則として他人は戸籍を請求できないが債権者など正当な理由があれば可能
- 相続は家族だけでなく債権者など第三者が関わることもある
- 根拠となる法律は手続きを定める戸籍法と権利関係を定める民法
- 会ったことのない相続人が見つかったらまずは丁寧な手紙で連絡を取る
- 手続きで困ったら一人で抱え込まず役所の窓口や専門家に相談することが大切
▼あわせて読みたい関連記事▼